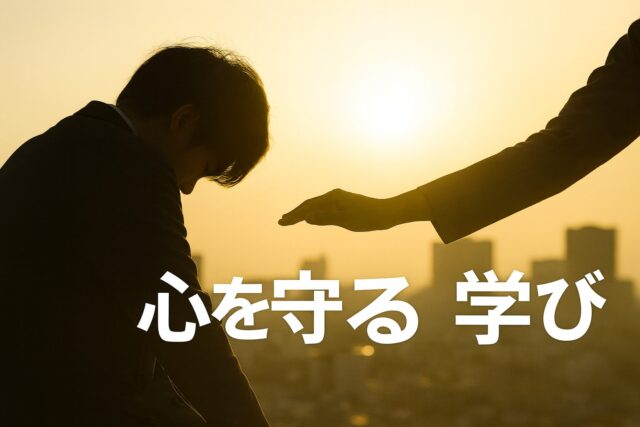
現代の日本は「ストレス大国」とも言われます。
厚生労働省の調査では、働く人の8割以上が強いストレスを抱えており、精神疾患の総患者数は600万人超という規模です。
中でも最も多いのがうつ病で、改善が遅れると最悪の場合「死」を選択してしまうケースも少なくありません。
つまり、いま日本社会が直面しているのは「疲れている人が多い」というレベルではなく、命に直結する深刻な課題なのです。
学校では不登校やいじめが過去最多水準となり、家庭や職場でも「心のケア」は待ったなしの課題になっています。
本記事ではまず、第1章で最新の公的データを基に「日本のストレス社会」の実像を徹底的に可視化し、なぜ今「心を守る学び」が必要なのかを読み解いていきます。
この記事の目次です
第1章|ストレス社会の「今」を数字で把握する
1-1. 日本の「心の危機」についての最新データ
まずは、日本社会の「心の現状」を数字で見てみましょう。
いずれも公的統計・省庁資料の直近公表値です。
驚くほどの規模感に、きっと読みながら息をのむはずです。
| 指標 | 最新値 | 出典(外部リンク) |
|---|---|---|
| 労働者の強いストレスあり | 82.7% | 厚生労働省「令和5年 労働安全衛生調査」 |
| 精神疾患の総患者数 | 約603.0万人(入院26.6万人/外来576.4万人) | 厚労省「精神保健医療福祉の現状等について(R7検討会)」 |
| 自殺者数(年間) | 21,837人(2023年・確定値) | 警察庁「令和5年中における自殺の状況」 |
| 不登校(小中) | 約34.6万人(+高校 約6.9万人) | 文科省「令和5年度 問題行動・不登校等 調査」 |
| いじめ認知件数 | 約73.3万件(重大事態1,306件) | 同 上(概要PDF) |
※各値は公表時点の最新資料に拠ります。定義や推計方法の変更(例:患者調査の「平均診療間隔」見直し等)により、年次比較は注意が必要です。
どうでしょうか?
労働者の8割以上がストレスを抱え、精神疾患の患者は600万人超。
さらに、自殺者が年間2万人を超え、不登校は40万人規模…。
信じられないかもしれませんが、これが「現代日本のリアルな姿」なのです。
1-2. なぜここまで心が疲れるのか:構造的要因
「個人の弱さ」ではなく、環境が構造的にストレス過多になっています。
- 働き方の高度化と責任リスクの可視化:成果主義、即応性、SNS・社内ツール拡散で「失敗への恐れ」が高止まり。
- 量的負荷の慢性化:人手不足・兼務化・タスクの細分化により常時オーバーフロー。
- 対人ストレスの複雑化:対面とリモートが混在し、非言語情報の欠落や孤立感が増幅。
- 学齢期の脆弱性と家庭負担:不登校・いじめの増加、発達特性への支援不足が家庭へ波及。
- ケア需要と供給のミスマッチ:医療に至る前段階の「軽〜中等度」支援を担う人材が不足。
働く人が感じる主なストレス要因(複数回答)も、構造を裏づけます。
これらはすべて、個人の努力で解決できる問題ではありません。
「自分の力不足」ではなく「社会の仕組みの歪み」が背景にあると知るだけでも、少し肩の荷が下りるのではないでしょうか。
1-3. 学校・家庭で広がる心の危機
学校現場では不登校が小中だけで約34.6万人、高校を含めると41.5万人規模。
- 背景には、学習遅れへの不安、対人関係の分断、発達特性への支援不足、家庭のケア負担増大など複合要因。
- 学校の相談体制やスクールカウンセラー配置は拡充中だが、需要に追いつかない地域も多い。
不登校が40万人超。
この数字を聞いて「そんなに?」と驚いた人も多いでしょう。
これは特別な問題ではなく、どの家庭にも起こりうる日常の一部になりつつあるのです。
さらにいじめ認知は73万件。
児童生徒の自殺は397人。
子どもたちの「心の危機」は、大人の社会以上に深刻です。
「学校さえ行けば大丈夫」という時代は、すでに過去のものになっているのです。
1-4. 企業・組織が直面する制度とリスク
ストレスチェックは法令に基づく制度です。
2015年からストレスチェック義務化が始まりました。
常時50人以上の事業場は年1回実施が義務(50人未満は当面努力義務)です。
でも、「チェックさえすれば安心」ではありません。
結果を分析して職場改善につなげなければ、数字はただの数字です。
また、最近注目されるのがプレゼンティーズム(不調のまま働き続けること)。
休まないから問題ないと思われがちですが、実は生産性を大きく損なう隠れた損失なのです。
「仕事はできているけど、心は壊れかけている」。
そんな人が、あなたの周りにもいませんか?
参考:厚労省(東京労働局)「ストレスチェック制度について」/厚労省ポータル「こころの耳」
1-5. 生活者サイド:セルフケアと準専門家の必要性
医療に至る前段階で役立つ日常の心理スキル(感情のラベリング、行動活性化、マインドフルネス等)への関心が高まっています。
同時に、職場・学校・地域で傾聴・受容・共感をベースに一次対応ができる「準専門家」の育成が課題です。
セルフチェック|最近こんなサインはありませんか?
- 眠りが浅い/寝ても疲れが取れない
- 些細なことで動悸・不安・イライラが続く
- 食欲の極端な増減・過食や拒食に近い波
- 遅刻・欠勤・ミスが増え、集中できない
- 「もうどうでもいい」と投げやりな感覚
※受診が必要と思われる症状がある場合は、早めに医療機関や公的相談窓口へ。
1-6. 本章の結論:だから「心を守る学び」が要る
データが示すのは、個人の努力だけではカバーしきれない構造的ストレスと、支援人材の不足です。
これらの数字は、ただの統計ではありません。
ひとり一人の現実であり、私たち自身や身近な人に起こり得ることです。
そして同時に、どうやって心を守るかが社会全体のテーマになっていることを示しています。
次章では、さらに「職場のストレスのリアル」を掘り下げ、具体的にどんな仕組みや学びが必要かを見ていきましょう。
第2章|職場におけるストレスの現実

働いていて「なんだか息苦しい」と感じたことはありませんか?
実はその感覚、あなただけではないのです。
厚労省の調査によれば、働く人の8割以上が強いストレスを抱えていると答えています。
つまり、オフィスで隣に座っている同僚も、画面越しに打ち合わせしている相手も、同じように心の重荷を抱えている可能性が高いのです。
2-1. 職場ストレスのトップ3は「責任・量・人間関係」
「なぜこんなに疲れるのか?」。
その答えはデータに出ています。
厚労省が行った調査では、ストレスの主な要因として仕事の責任、仕事量、人間関係が上位を占めました。
| 主なストレス要因 | 該当割合 | 一言で言えば… |
|---|---|---|
| 仕事の失敗・責任 | 39.7% | 「ミスしたらどうしよう…」という不安が常につきまとう |
| 仕事の量 | 39.4% | 「今日もタスクが終わらない」――常に時間に追われている |
| 対人関係(ハラスメント含む) | 29.6% | 上司や同僚との関係がギクシャクし、心が休まらない |
「あ、これ自分のことだ」と感じた人も多いのではないでしょうか。
職場ストレスの原因は特殊なものではなく、誰もが日常的に直面しているテーマなのです。
2-2. 見えにくい「プレゼンティーズム」の落とし穴
会社を休んでしまう「欠勤」よりも厄介なのが、不調を抱えたまま働き続けることです。
前述しましたが、これを「プレゼンティーズム」と呼びます。
一見、真面目に頑張っているように見えますが、実際は集中力が落ち、判断ミスや生産性の低下につながります。
たとえば営業職のAさん(30代)。
連日の残業で眠れなくなり、朝は動悸が止まらない。
それでも「休んだら迷惑をかける」と出社を続けました。
結果、メールの誤送信や資料の準備漏れが増え、本人の評価だけでなくチーム全体の信頼にも影響してしまったのです。
「気合いで何とかなる」ではなく「早めの支援が必要」。
そう気づくことが大切です。
2-3. 組織ができること:仕組みで支える
「気をつけましょう」で終わらせないために、企業や組織は仕組みで支える必要があります。
具体的にはこんな取り組みが有効です。
- ストレスチェック結果を活かす:部署ごとに傾向を分析し、繁忙期の人員配置や業務フローを改善。
- 管理職への研修:傾聴・共感のスキルを身につけ、部下の「小さなSOS」を見逃さない。
- 相談窓口の整備:産業医や社外カウンセラーへの匿名相談ルートを常時用意。
- 働き方の再設計:不要な会議を減らし、夜間通知を控えるなど「休める環境」を整える。
- 心理的安全性の確保:「わからない」「助けて」と言える雰囲気をチームで育む。
こうした仕組みが整っていれば、「我慢しすぎる前に支援へつなげる」ことができます。
人の努力に頼らず、仕組みで守る。
これが今の時代に必要な発想です。
2-4. 働く私たちにできること
もちろん、組織の取り組みを待つだけではなく、個人でできることもあります。
例えば、
- 感情に名前をつける:「今イライラしている」「不安で落ち着かない」と自覚するだけで心が整理される。
- タスクを小さく刻む:30分単位に分け、「まずは5分だけやってみる」とハードルを下げる。
- 休息のルール化:就寝・食事・入浴のリズムを整えることで、体も心も回復しやすくなる。
- 「考えすぎ」のスイッチを切る:気づいたら席を立つ・深呼吸する・散歩に出るなど、体を動かしてリセット。
- 相談先をスマホに登録:会社・自治体・民間の窓口をすぐ連絡できるようにしておく。
「頑張りすぎない工夫」こそが、実は一番大切なのかもしれません。
もしあなたが最近「ちょっとしんどいな」と感じているなら、ぜひ一つでも取り入れてみてください。
2-5. まとめ:職場ストレスはみんなの課題
職場でのストレスは、誰か一人の弱さではなく社会全体の構造的な課題です。
データが示す通り、多くの人が「責任・量・人間関係」で悩み、不調のまま働き続けています。
だからこそ、個人のセルフケアと組織の仕組み作り、両方が欠かせません。
次章では、学校や家庭で広がる心の危機を取り上げます。
子どもや家庭に迫る現実を知ることで、より一層「心を守る学び」の必要性を実感できるでしょう。
第3章|学校・家庭で広がる心の危機

職場だけでなく、子どもや家庭の世界にも深刻なメンタルの課題が広がっています。
「うちの子に限って」「家庭は安全な場所のはず」、そう思いたい気持ちは誰にでもあります。
でも、最新のデータを見るともはや他人事ではない現実が浮かび上がってきます。
3-1. 不登校は「珍しいこと」ではなくなった
文科省の調査によると、2023年度の不登校は小中で34.6万人、高校を含めると41.5万人。
数字だけ見るとピンと来ないかもしれませんが、「小中学生の約30人に1人が不登校」という割合です。
クラスに1人、2人は来られない子がいる計算になります。
「昔は甘えだと言われていたけれど、今やどの家庭でも起こり得る日常の一部」。
先生や親の努力だけで解決できる問題ではなく、社会全体のサポートが不可欠です。
3-2. いじめと自殺――子どもたちの「叫び」
2023年度のいじめ認知件数は約73.3万件。
これは「全校で1件」ではなく、1つの学校で複数件が当たり前の規模です。
重大事態は1,306件、そして児童生徒の自殺は397人。
数字にするだけで胸が痛みます。
「学校に行けば安心」と信じたいところですが、残念ながらそれは過去の常識。
教室の中で孤立し、心を追い詰められている子が確実に存在しています。
「朝になると子どもが学校に行きたくないと泣くが、無理やり行かせていいものか?」
こうした声は特別ではなく、全国の多くの家庭で日々繰り返されています。
「家庭こそ安心できる場所であってほしい」。
そんな願いと現実のギャップが、親の心をも追い込んでいるのです。
3-3. 家庭にのしかかるケアの負担
不登校や発達特性のある子どもを支える家庭では、親の負担が大きくのしかかります。
仕事を続けながら子どものケアをするのは簡単なことではありません。
「子どもを守りたいのに、自分の心が折れそう」。
そんな親御さんが増えています。
- 日中は子どもの気分に合わせて対応し、夜は仕事の持ち帰りで睡眠不足。
- 学校や病院との連絡調整に追われ、気づけば自分の時間がゼロに。
- 相談したくても「親の責任」と思われるのが怖くて言い出せない。
子どもの問題が家庭全体のストレスにつながり、結果的に親子双方のメンタルを悪化させてしまう。
これもまた、日本社会が抱える「見えにくい課題」のひとつです。
3-4. 学校・家庭に必要な支援とは?
では、どうすればいいのでしょうか。
ポイントは「孤立させないこと」です。
- 学校側の取り組み:スクールカウンセラーの配置、オンライン授業の活用、個別学習の選択肢。
- 地域・自治体の支援:子育て世帯の相談窓口、発達支援センター、親同士の交流会。
- 家庭での工夫:完璧を目指さず「今日は休んでもいい」と柔軟に考える余地。
子どもの心を守るには、親の心を守ることも同じくらい大切。
家庭・学校・地域がそれぞれ役割を分担し、支え合うことが不可欠です。
3-5. まとめ:子どもたちの未来をどう守るか
不登校、いじめ、自殺――どれも数字で語ると冷たい印象を持ちますが、その一つ一つの裏には子どもの悲しみ、親の苦しみがあります。
「そんな現実があるんだ」と気づくこと自体が、第一歩なのかもしれません。
次章では、国や企業がどんな制度を整え、どこに課題が残っているのかを見ていきます。
「仕組みでどう支えるか」を考えることは、学校や家庭を助ける大きなヒントになるはずです。
第4章|国・企業の制度と課題

ここまで「個人」「家庭」に迫るメンタルの危機を見てきました。
では、社会全体ではどう対応しているのでしょうか?
国の制度や企業の取り組みを見てみると、前進はあるものの課題も浮き彫りになっています。
4-1. ストレスチェック制度――義務化はしたけれど
2015年から、従業員50人以上の事業場にはストレスチェック制度が義務化されたということは書きました。
一見すると画期的に思えますが、実際には「やったことにする」だけになっているケースも少なくありません。
せっかくのデータを活かさず、結果を放置してしまえば制度は形骸化してしまいます。
「数字を集めることが目的ではない」。
このことをどれだけ本気で理解できるかが分かれ道です。
4-2. 「働き方改革」とメンタルヘルス
近年よく耳にする働き方改革。
残業時間の上限規制や有給休暇の取得義務化などが進みました。
たしかに労働時間は減りましたが、「短時間で成果を出せ」というプレッシャーが逆に強まったという声もあります。
つまり、制度だけでは解決にならないのです。
「働き方改革=メンタルが楽になる」とは限らないという現実を、私たちは忘れてはいけません。
4-3. 公的な相談窓口の充実
国や自治体も、相談窓口の整備を進めています。
厚労省の「こころの耳」ポータルでは、電話・SNSで相談できる窓口を一覧化。
また、24時間対応の「自殺防止相談ダイヤル」なども設置されています。
「誰かに話すだけで楽になる」。
そんな小さな一歩を後押しする仕組みです。
ただし課題は、「その存在を知らない人が多い」こと。
制度があっても、届かなければ意味がありません。
参考:厚労省「こころの耳 相談窓口案内」
現在は以下のページで最新の窓口情報をご確認いただけます
(電話・SNS・メール各種相談が利用可能です)
4-4. 企業に求められる「仕組み+文化」
制度や窓口があっても、職場の空気が変わらなければ従業員は声を上げられません。
- 「休むと迷惑をかける」
- 「相談すると評価が下がる」
こうした意識が根強いのです。
だからこそ企業には、「仕組み」と「文化」の両方が求められます。
仕組み=ストレスチェックや相談窓口、文化=心理的安全性や上司の傾聴姿勢。
どちらか一方ではなく、両輪で回す必要があります。
4-5. 海外と比べて見える日本の課題
欧米諸国では、心理カウンセラーやセラピストに相談することは日常の一部です。
一方、日本では心のケア=病気になった人が行くものという偏見がまだ残っています。
その結果、支援を必要としている人が「最後まで我慢してしまう」傾向が強いのです。
「相談は恥ずかしいことではない」という価値観を根づかせることも、大きな課題です。
4-6. まとめ:仕組みを活かすのは人
制度は整いつつありますが、実際にそれを機能させるのは現場で働く私たち一人ひとりです。
どれほど立派な法律やガイドラインがあっても、数字を集めるだけで終わってしまえば意味がありません。
では、制度や仕組みだけで本当に十分なのでしょうか?
「心を守る力」を個人が学び、日常の中で実践すること――そこに次のカギがあるのかもしれません。
次章では、いま注目を集めている「心を守る学び」=心理学やカウンセリングの基礎を身につける方法について紹介します。
家庭・職場・学校、あらゆる場面で役立つスキルを学ぶことで、数字だけでは救えない心のリアルに寄り添う力を持つことができるのです。
第5章|心を守る学びという選択肢
5-1. なぜ「個人の学び」が必要なのか
第4章で見たように、国や企業は制度を整えてきました。
でも、制度だけで人の心を守りきれるでしょうか?
答えは残念ながらNOです。
職場・学校・家庭など日常のあらゆる場面で、支え合う知識とスキルを持った人が求められています。
つまり、私たち一人ひとりが「心を守る学び」を身につけることが、今後ますます大切になるのです。
5-2. 「傾聴・受容・共感」を学ぶ意味
その代表的なアプローチが傾聴・受容・共感です。
相手の話を遮らず、評価せず、ただ受け止めて理解する。
これだけで、話し手の心は驚くほど軽くなります。
「誰かに話を聞いてもらえた」という安心感は、医療の手前で人を支える大きな力になるのです。
5-3. 即実践できる心理学テクニック
心理学の学びは、特別な場面だけでなく日常にも役立ちます。
例えば、
- 信頼関係を築きやすくする会話術:初対面や面談での安心感アップ
- 目標達成をサポートする方法:部下や子どもの挑戦を後押し
- 決断をフォローする声かけ:迷っている人の背中を優しく押す
これらは支援の場だけでなく、ビジネスや家庭、人間関係すべてに応用できます。
「心理学を学ぶ=人を助けるだけでなく、自分の生活も豊かにする」というのは大きな魅力です。
5-4. メンタルヘルス支援士という資格

うつ病や不登校、自殺など深刻な社会問題が増える中で、私たち一人ひとりが「心を支える力」を持つことの重要性が高まっています。
医療機関や専門カウンセラーだけに頼るのではなく、家庭・職場・学校といった身近な場で寄り添える人材が求められているのです。
そのニーズに応える学びとして注目されているのが、メンタルヘルス支援士という資格です。
📘 学べる内容
- 傾聴・受容・共感をベースにしたカウンセリング技術
- うつ、不安障害、発達障害などの精神疾患に関する基礎知識
- ストレスマネジメントやセルフケアの実践方法
- 人間関係を良好にするための日常心理学テクニック
これらは「治療行為」を行うためのものではなく、あくまで予防や日常生活の支えに役立つ知識です。
家族や同僚、子どもなど、身近な人が悩んでいる時に適切に寄り添えるようになります。
🌱 学ぶメリット
- 自身のメンタルを整える:セルフケア力が高まり、ストレスに負けにくい生活を送れる
- 家族や友人を支えられる:精神疾患を未然に防いだり、適切な支援の声掛けができる
- 子どもの自己肯定感を育てる:発達障害や不登校に対する理解を深め、前向きな関わり方ができる
- ポジティブ思考が身につく:思考のクセを知り、前向きな考え方を習慣化できる
- ビジネススキルが向上:心理学的アプローチを営業や接客に応用し、成果アップや人間関係改善につながる
💡 こんな人におすすめ
- 家庭や子育てで「心のケア」を学びたい人
- 職場での人間関係やストレス対応に悩んでいる社会人
- 心理カウンセラーや相談員を将来的に目指したい人
- 地域活動やボランティアで人を支えたいと考えている人
📝 履歴書にも書ける
メンタルヘルス支援士は履歴書に記載可能な資格です。
心理カウンセラーや福祉分野を志す人にとって信頼性を高める一歩となり、キャリア形成にもプラスに働きます。
もちろん、就職が保証されるわけではありませんが、「心を守る力を持っている」という証明として十分に活用できます。
📌 よくある質問(FAQ)
お申し込み時に必要なのは受講料のみで、試験料は受験のタイミングで別途お支払いとなります。
DVDを購入する場合は+1,100円が加算されます。
なお、資格の登録料や更新料は一切不要です。
平均的な学習期間は約2か月で、早い方では2週間程度で合格するケースもあります。
ただし受験資格は「本講座を受講していること」です。受講せずに試験だけを受けることはできません。
💴 他の心理資格との料金比較
| 資格名 | 総額費用 | 特徴 |
|---|---|---|
| メンタルヘルス支援士 | 40,260円(税込) | 在宅学習・在宅受験、更新料なし |
| 心理カウンセラー(民間スクール) | 10万〜20万円前後 | 通学型や通信型あり。比較的高額。 |
| 公認心理師(国家資格) | 数百万円(大学・大学院学費) | 国家資格。専門職に必須だがハードル高め。 |
※金額は目安です。実際の費用は各資格の公式情報をご確認ください。
🔗 資格公式情報
学習内容やカリキュラムの詳細は公式サイトで公開されています。
受講の流れや費用など、最新情報はこちらをご覧ください。
5-5. まとめ:数字だけでは救えない心に寄り添う
これまで見てきた統計、うつ病患者数、自殺、不登校、いじめなど。
それらは確かに社会の現状を示していますが、数字だけでは人の心は救えません。
必要なのは、身近な人が寄り添い、話を聞き、理解しようとする力です。
「心を守る学び」を通して、私たちは自分自身を守り、そして大切な人を支えることができます。
制度や仕組みに加えて、個人の学びが広がることで、社会全体のメンタルヘルスは確実に前進していくはずです。
その第一歩として「メンタルヘルス支援士」のような資格を学ぶことは、誰にでもできる現実的なアクションです。
この記事が、あなた自身や周りの人が「心のケア」を始めるきっかけになれたら幸いです。
必要なときは無理せず、支援の扉を開いてください。
🆘 相談窓口
- 自殺防止・いのちの電話:0570-783-110(10時~22時)
- 厚生労働省 こころの健康相談統一ダイヤル:0570-064-556
- 子どもSOSダイヤル:0120-0-78310
身近な人に相談できないときは、専門の窓口を活用してください。
小さな一歩が、大きな安心につながります。
よろしかったらこちらの記事もお読みください。
参考・出典リンク
- 厚労省「令和5年 労働安全衛生調査(概況)」
- 厚労省「同(詳細:ストレス要因内訳)」
- 厚労省「精神保健医療福祉の現状等について(R7)」
- 警察庁「令和5年中における自殺の状況(確定値)」
- 文部科学省「令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等 調査」 / 概要PDF
- 厚労省(東京労働局)「ストレスチェック制度について」
- 厚労省ポータル「こころの耳」
関連リンク
- 不登校支援の最新データ+家庭・学校でできる5つのステップ|いじめ・自殺対策も
- 連休明けの仕事うつと新入社員の五月病について解決法を提案します
- 梅雨の“なんとなく不調”はこれで解決!湿気・冷え・だるさに効くセルフケア10選【2025年版】
- 9月も熱中症要注意!秋バテ・クーラー病との違いと対策まとめ【2025年版】
- インフルエンザ2025|今の流行・検査・ワクチン・薬・出席停止まで完全ガイド
- 人権週間とは?いつから?学校でできる取り組み・標語例・おすすめ絵本まとめ
- オンラインメンタルヘルスサービス比較|特徴・料金・サポート内容で分かる選び方






