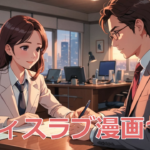もしあなたが「文化の日にどこへ行こう?」と迷っているなら、この記事が解決のヒントになります。
全国で開催される文化の日イベントを分かりやすくまとめました。
文化の日はいつ?──毎年11月3日と定められており、2025年は11月3日(月・祝)です。
由来は「自由と平和を愛し、文化をすすめる日」として1948年に制定されました。
この日は全国の美術館・博物館で無料開放が行われたり、街全体が文化や芸術を楽しむ催しで賑わいます。
東京・大阪・福岡などの都市部だけでなく、地方の自治体でも親子向けワークショップや体験イベントが多数予定されています。
この記事では、2025年の文化の日に訪れたい全国の無料スポット・体験イベント・地域別のおすすめ情報をまとめました。
秋の3連休を利用して、身近に「文化」を感じるお出かけを楽しみましょう。
この記事の目次です
第1章|文化の日とは?由来と意味をやさしく解説
文化の日は「自由と平和を愛し、文化をすすめる日」。
全国で美術館や博物館が無料開放され、芸術・体験イベントが多数行われます。
2025年は3連休にあたるため、お出かけのチャンスも広がります。
文化の日の基本情報
まずは、文化の日の基本を押さえておきましょう。
文化の日は、毎年11月3日に定められた日本の祝日です。
正式には「自由と平和を愛し、文化をすすめる日」として、1948年(昭和23年)に制定されました。
この日付には歴史的な由来があります。
明治天皇の誕生日(1852年11月3日)であり、戦後の日本国憲法が公布された日(1946年11月3日)でもあります。
つまり、文化の日は「文化・自由・平和」を象徴する、特別な意味を持つ祝日なのです。
また、毎年この日には「文化勲章」の授与式が行われ、科学・芸術・学術などの分野で功績を残した人々が表彰されます。
ニュースで皇居での授賞式を見る機会が多いのも、このためです。
なぜ「文化の日」と呼ばれるのか
「文化」とは、単に芸術や学問を指す言葉ではありません。
人々の暮らしや考え方、伝統や創造的な活動のすべてを含む概念です。
つまり、文化の日は日常の中の創造や思いやりを見つめ直す日でもあります。
戦後の混乱期に生まれたこの祝日は、日本が再び平和を取り戻し、教育や芸術を通じて心豊かな社会を築こうとする象徴として設けられました。
現在では、美術館や博物館の無料開放、地域イベント、学校行事などを通して、誰もが文化に触れられる一日となっています。
文化の日の位置づけと2025年の特徴
2025年の文化の日は11月3日(月・祝)です。
前日の11月2日(日)と合わせて3連休になるため、例年以上に観光やイベントへの関心が高まることが予想されます。
特に今年は、感染症による制限が完全に解除され、各地のイベントが本格再開しているタイミングです。
文化の日をきっかけに、地域の伝統行事やアートフェスなど、地元に根付いた催しが活気を取り戻しています。
例えば、東京都では都立美術館や上野の博物館が無料で開放されるほか、関西では「関西文化の日」として11月中旬にかけて各地の文化施設が無料入場を実施します。
全国的にも「文化の秋」を楽しむきっかけが広がっているのが2025年の特徴です。
文化の日がもたらす価値
文化の日は、単なる休日ではありません。日本人が培ってきた伝統や技術、芸術を次の世代へ伝える大切な節目です。
現代社会ではスマートフォンやデジタル文化が主流ですが、こうした便利さの中で改めて「心を動かす体験」に触れる意義があります。
例えば、美術館で名画を眺める時間や、地元の祭りで人と交流する瞬間は、日常では得られない豊かさを感じさせてくれます。
文化の日は、そうした心の余白を取り戻すチャンスともいえるでしょう。
文化の日は「知る」「感じる」「つながる」日
文化の日は、日本人のルーツと未来を結ぶ特別な祝日です。
自由と平和を愛し、文化を広げるという理念は、私たち一人ひとりの行動にも通じています。
2025年は3連休という好条件も重なり、全国で多彩な催しが予定されています。
せっかくの休日を家で過ごすのも良いですが、今年は少し足を伸ばして、文化や歴史を感じるお出かけを楽しんでみてはいかがでしょうか。
この記事の要点を押さえれば、文化の日への理解が一段と深まります。
焦らず、少しずつ行動に移していきましょう。
第3章|子ども・家族で楽しむ文化の日の過ごし方
文化の日は、家族で「学びと体験」を共有できる絶好のチャンスです。
小さな子どもでも参加できるワークショップや、入館無料の博物館を上手に活用すれば、楽しみながら文化に触れられます。
子どもと一緒に楽しむ無料イベント

全国の美術館・博物館では、文化の日に合わせて子ども向けの特別プログラムを実施する施設が多くあります。
例えば、国立科学博物館では体験型展示やサイエンスショーが開催され、親子で学びながら遊べます。
また、東京・上野の「こども文化科学館」や、大阪市立科学館などでも、科学実験やクラフト教室などが人気です。
入館料が無料になるだけでなく、スタッフによるガイドツアーや解説付き展示も増えるため、学びの密度が高くなります。
さらに、各地の図書館や市民ホールでも、読み聞かせ会や子ども向け演奏会が開かれます。
静かな時間を共有することで、親子の会話も自然に増えるでしょう。
屋外イベントで身体を動かそう
文化の日は秋の行楽シーズン真っ只中です。
天気が良ければ、公園や広場で開かれる「文化フェス」「アートマルシェ」などの屋外イベントもおすすめです。
神奈川県の県立あいかわ公園では、手作り工芸体験や地元グルメを楽しめる文化祭が開催されます。
兵庫県・姫路市では、世界遺産・姫路城周辺で行われる「市民文化フェスティバル」が人気です。
屋外イベントは子どもが飽きにくく、写真映えするスポットも多いため、家族の記念日としても思い出に残ります。
遊びながら文化を学ぶ一日は、学校では得られない経験になります。
文化の日に多くの自治体で実施される「文化賞」「芸術祭」は、地域の学校や子ども会が参加できることもあります。
公式サイトや市報をチェックして、地元の行事に親子で参加するのもおすすめです。
ワークショップ・体験イベントに注目
最近は、触って学ぶ「ハンズオン体験」が人気です。
たとえば、愛知県の名古屋市科学館では、化学実験ショーやプラネタリウム見学会が行われます。
子どもたちが自らの手で作る体験は、学びの意欲を高める効果もあります。
静岡県の浜松市楽器博物館では、楽器演奏体験やリズムワークショップが開催予定。
音楽の街・浜松らしい文化的な企画です。
体験を通じて、子どもの表現力や集中力を育むことができます。
お出かけのコツと準備
文化の日は例年、晴天に恵まれる日が多く、家族連れの外出が集中します。
前日までに行きたい場所の公式サイトで開催時間・整理券の有無を確認しておきましょう。
また、公共交通機関を使う場合は混雑時間を避け、早めの移動がおすすめです。
無料開放の施設は午前中が比較的空いている傾向にあります。
屋外イベントでは寒暖差に注意し、羽織れる上着を準備しておくと安心です。
子どもが疲れたときのために、おやつや飲み物を持参しておくのもポイントです。
家族で「文化を体験する」一日に
文化の日は、親子で新しい発見を共有できる特別な祝日です。
博物館やワークショップを通じて、子どもたちが「知る喜び」や「作る楽しさ」を体感できます。
何気ない体験が、子どもの未来の興味や夢につながることもあるでしょう。
ぜひ今年の文化の日は、家族で文化に触れる小さな冒険に出かけてみてください。
小さな一歩でも、確実に変化は起こせますよ。
第4章|全国の無料開放スポットまとめ【美術館・博物館編】
文化の日は、全国の美術館や博物館が一斉に無料開放される特別な日です。
普段は有料の施設もこの日に限り入館無料となることが多く、知識と感動を同時に味わえるチャンスです。
東京|芸術と歴史の拠点をめぐる
東京国立博物館は、文化の日を象徴するスポットの一つです。
毎年11月3日は常設展が無料公開となり、国宝や重要文化財の展示を無料で鑑賞できます。
上野公園一帯では、野外アートや伝統音楽の演奏も行われ、まるで街全体が文化のステージになります。
また、国立近代美術館や東京都美術館でも特別展の割引や入場無料が予定されています。
アート初心者でも気軽に楽しめるイベントが多く、カップルや学生にも人気です。
京都・大阪|伝統とモダンが交わる関西の文化拠点
京都の京都国立博物館では、文化の日に合わせて常設展示が無料になります。
平安から江戸までの日本美術を体系的に学べる貴重な機会です。
二条城や清水寺でも特別公開が行われ、伝統と現代文化が共存する空間を体感できます。
大阪では、大阪歴史博物館や国立国際美術館が無料開放を実施します。
御堂筋オータムパーティーと連動して開催されるため、街全体が芸術フェスティバルのような賑わいになります。
東海地方|家族で学べる科学・産業系施設
名古屋市科学館では、プラネタリウム見学や体験実験が無料で楽しめます。
2025年の文化の日は、地球・宇宙・化学の3テーマを中心に特別展示が予定されています。
トヨタ産業技術記念館も人気の無料開放スポットで、自動車産業の歴史と最新技術を親子で学べます。
静岡県では静岡県立美術館や浜松市楽器博物館などが無料開放を予定。
音楽をテーマにした特別演奏会も同時開催され、聴覚で楽しむ文化体験が魅力です。
文部科学省が公表している統計によると、文化の日の入館者数は通常の約2〜3倍に増加します。
無料開放の対象施設は、前年より拡大傾向にあり、特に地方都市の美術館・資料館の参加が増えています。
北海道・東北|地域文化を感じるミュージアム
札幌芸術の森美術館では、彫刻と自然が調和した展示空間が無料開放されます。
屋外展示も多く、紅葉の中を歩きながら芸術を堪能できます。
宮城県の仙台市博物館では、伊達政宗ゆかりの展示が無料公開され、歴史と文化の深さを実感できます。
福島県では会津若松市の福島県立博物館が無料入館デーを実施予定で、伝統工芸の実演も見どころです。
九州・沖縄|地域色豊かな文化体験
福岡アジア美術館は、アジア各国の現代アートを紹介するユニークな施設です。
文化の日には特別展の観覧料が無料になり、異文化理解を深めるチャンスになります。
熊本県立美術館では、熊本城を望むロケーションで近代絵画の特別展示が行われます。
沖縄の那覇市歴史博物館では、琉球王国時代の衣装や工芸品が無料公開され、南国文化の奥深さを感じられます。
無料開放情報の調べ方
文化の日に無料になる施設は、毎年9月〜10月に各自治体や施設公式サイトで公開されます。
以下のような検索キーワードで調べると最新情報を得られます。
| 目的 | 検索キーワード例 |
|---|---|
| 東京都内の美術館 | 文化の日 無料 美術館 東京 2025 |
| 子ども向け科学館 | 文化の日 子供 科学館 イベント |
| 地域の歴史資料館 | 文化の日 無料 博物館 +都道府県名 |
文化の日は「学ぶ休日」
文化の日は、誰もが無料で芸術や学びに触れられる貴重な日です。
美術館や博物館を訪れることで、教科書の中の知識が「実体験」に変わります。
普段は行かない分野の展示を覗いてみるのも良い刺激になります。
大人も子どもも新しい発見があるはずです。
ぜひ11月3日は、文化を学ぶ一日にしてみてください。
この記事の要点を押さえれば、文化の日のお出かけ計画がより充実します。
次章では、混雑を避けるコツと、おすすめの文化イベントコースを紹介します。
第5章|混雑を避けるコツ&おすすめコース
文化の日は全国的に人気イベントが集中するため、時間帯やルート選びが重要です。
少しの工夫で混雑を避けながら、快適に文化を楽しむことができます。
朝イチの入館でゆったり楽しむ
無料開放の美術館や博物館は、午前10時前後が最も混み合う時間帯です。
開館時間の30分前に到着すると、比較的スムーズに入場できます。
特に、上野・京都・大阪などの大型施設は、午後になると待ち時間が発生することもあります。
一方、地方の施設は午前中でも比較的落ち着いており、展示をじっくり見られる傾向です。
朝の時間を上手に使うことで、同じイベントでも印象がまったく変わります。
屋外イベントは昼〜夕方が狙い目
屋外フェスやアートマーケットは、午前中は設営・準備の時間帯であることが多く、午後のほうが盛り上がります。
昼食後に訪れると、出店数も増えて活気にあふれます。
また、夕方にはライトアップやキャンドル演出を行うイベントもあります。
昼と夜で雰囲気が変わるため、家族やカップルで時間を分けて楽しむのもおすすめです。
・無料入館日は午前より午後のほうが分散しやすい。
・屋外フェスは開始2時間後がピーク。夕方以降は比較的空く傾向。
・混雑を避けたい場合は、郊外や地方都市のイベントを狙うのがコツ。
おすすめモデルコース(関東編)
午前:上野の東京国立博物館で無料開放を満喫。国宝展示を鑑賞後、上野恩賜公園でアートマーケットを散策。
昼:上野駅周辺でランチ。カフェや老舗レストランで文化の余韻を味わう。
午後:東京都美術館や国立西洋美術館へ移動し、絵画・彫刻などを鑑賞。余裕があれば、秋葉原や浅草まで足を伸ばすのもおすすめです。
おすすめモデルコース(関西編)
午前:京都国立博物館で古都の歴史に触れる。混雑前に常設展を見学。
昼:祇園や清水寺周辺でランチ。伝統的な町家カフェや和食店でひと休み。
午後:御堂筋オータムパーティー(大阪)を訪れ、音楽やアートを満喫。夕方には道頓堀や中之島の夜景スポットへ。
地方を楽しむ一泊二日プラン
3連休を活かして、地方都市の文化イベントを巡るのもおすすめです。
たとえば、金沢の兼六園ライトアップや、福岡のアジア美術館イベントなどは、夜の時間帯が特に幻想的です。
温泉地に宿泊して、翌日に地元の伝統工芸体験を組み合わせると、旅行と文化体験を一度に楽しめます。
文化の日は「観光×学び」の両立がしやすい祝日です。
宿泊を伴うお出かけでは、交通手段の混雑にも注意しましょう。
新幹線や高速バスは前週末から混雑が始まります。
早めの予約と、余裕あるスケジュールが快適な旅を支えます。
まとめ|文化を楽しむ「余白」を作ろう
文化の日を快適に過ごすためには、時間配分と気持ちのゆとりが大切です。
予定を詰め込みすぎず、感動や発見の瞬間をゆっくり味わうことで、文化体験の価値が何倍にも広がります。
お出かけ先で出会う人や景色、音楽や作品のすべてが、その日だけの文化になります。
静かな美術館でも、賑やかなフェスでも、あなたなりの「文化の一日」を楽しんでください。
第6章|文化の日の未来とこれからの楽しみ方
文化の日は、これまでの伝統や芸術を守るだけでなく、
次の世代へ「新しい文化」をつなぐための日でもあります。
2025年以降は、リアルとデジタルが融合した多様な楽しみ方が広がっています。
デジタル時代の文化体験へ

近年では、テクノロジーを活用した文化体験が増えています。
たとえば、VR(仮想現実)を使った美術館ツアーや、オンラインで鑑賞できるデジタル展示会などです。
自宅にいながら、国内外の名作を高画質で楽しめる時代になりました。
東京国立近代美術館や京都国立博物館などでは、バーチャルギャラリーの公開を進めており、スマートフォンからでも作品を360度で鑑賞できます。
距離や時間の制約を越え、誰もが文化にアクセスできる社会が実現しつつあります。
地域文化の再発見と継承
文化の日は都市部のイベントだけでなく、地方文化の魅力を再発見する機会でもあります。
伝統工芸・郷土芸能・地域祭りなど、古くから続く文化の継承は、地域コミュニティを支える重要な活動です。
例えば、石川県の九谷焼や高知県の土佐和紙など、地方の工芸品を体験できるイベントも増えています。
観光を通じて地域の文化に触れ、購入やSNS発信を通して応援することが、次世代への文化継承にもつながります。
・地方の伝統工芸体験や文化祭に参加してみる
・オンライン美術館で海外の名作を鑑賞
・文化庁や地方自治体のデジタルアーカイブを閲覧
・家族や友人と「文化を感じた瞬間」をSNSで共有
教育・福祉と文化の融合
文化は、教育や福祉の分野とも深く結びついています。
2025年は全国で「インクルーシブ文化イベント」が広がり、障がいの有無に関係なく参加できるアート体験やワークショップが開催されます。
聴覚障がい者のための「手話による美術解説ツアー」や、触覚で楽しむ「立体アート展示」なども増加中です。
文化を「見る」「聞く」だけでなく、五感すべてで感じる流れが進んでいます。
サステナブル文化への関心
気候変動や環境問題への意識が高まる中で、文化イベントにも「サステナブル(持続可能)」の視点が取り入れられています。
リサイクル素材を使ったアート作品展、廃材アートコンテスト、エシカルファッション展示などが全国で展開されています。
特に若い世代では「文化×環境」「伝統×未来」をテーマにした活動が増え、文化の日が単なる休日ではなく、社会と自分をつなぐきっかけになっています。
・メタバース上での「仮想文化祭」開催(大学・企業主催)
・自治体による「文化NFT」発行プロジェクト
・再生素材を使ったアートイベントの増加
・地域図書館によるデジタルアーカイブの無料公開
これからの文化の日に向けて
文化の日の本質は「自由と平和を愛し、文化をすすめること」。
この理念は時代を越えて受け継がれています。
今後は、デジタル・地域・環境・教育といった多様な分野が交差し、より開かれた文化体験が生まれていくでしょう。
2025年をきっかけに、あなた自身の「文化の楽しみ方」を見つけることが、未来への第一歩になります。
そしてその一歩が、次の世代が文化を受け継ぐための光となるのです。
第7章|SNSで広がる文化の日トレンド【#文化の日】
文化の日はSNS上でも毎年大きな話題になります。
特にX(旧Twitter)では、#文化の日 や #文化の日イベント のハッシュタグを通して、全国の公式アカウントや自治体、文化施設が最新情報を発信しています。
#文化の日 で見つかる最新情報
たとえば、各地の美術館や博物館、自治体公式アカウントが、当日の無料開放やステージイベントをリアルタイムで案内しています。
東京都、京都府、札幌市、福岡市など、主要都市の文化関連機関は毎年この日に向けて公式キャンペーンを展開しています。
X上で「#文化の日」で検索すると、2025年の最新イベント情報や限定公開の詳細をまとめた投稿が多数見つかります。
文化庁や地方自治体の公式ポストも活発で、信頼性の高い情報源として活用できます。
最新の催しや混雑状況を知りたい方は、ぜひX(旧Twitter)で #文化の日 を検索してみてください。
現地の様子や開催直前の変更情報など、リアルタイムで確認できます。
実際の投稿
※投稿の埋め込みが表示されない場合は、ページを再読み込みしてください。
たとえば、文部科学省の公式アカウントでは「教育・文化週間」に合わせた取り組みが紹介されています。
🌟11/1(土)~11/7(金) は #教育・文化週間!🌟#文化の日 を中心に、教育や文化に関するイベントが全国各地で行われます。
学びにふれる瞬間、学びが習慣となる。大人も子供もみんなが楽しく学ぶ週間、「教育・文化週間」でともに学ぶ喜びを味わってみませんか?https://t.co/HuU9qJNusG pic.twitter.com/Fm1MZybfyk
— 文部科学省 MEXT (@mextjapan) October 24, 2025
また、全国の自治体でも地域ならではのイベントが多数。
こちらは岩手県の施設によるイベントの告知投稿です。
【文化の日無料開放】
11月3日(月・祝) は #入館料無料 で、館内をご覧いただけます👀
また #文化の日 ミニイベント「切手でしおりをつくろう!」も開催いたします🔖
この機会にぜひご来館ください😊
#盛岡てがみ館 #盛岡市 pic.twitter.com/lquhKzCUhA— 盛岡てがみ館 (@tegami_museum) October 26, 2025
このほか、地域の音楽祭やワークショップ、親子向けアート体験などもSNSで話題になっています。
気になるイベントは、公式アカウントで最新情報をチェックしてみてください。
#岐阜県 では、11月3日(#文化の日)を「 #岐阜 ~ #ふるさとを学ぶ日 」として、県内の #文化施設 を #無料開放 します。この機会に是非、魅力ある郷土の文化 ・芸術・自然に触れ、親しんでください🥰
▼詳細はコチラhttps://t.co/MbvD6UjCSp pic.twitter.com/VHiYfVOqG7— ミナモだより【岐阜県広報】 (@Gifu_kouhou) October 22, 2025
今週末、10月25日(土)、26日(日)は「 #東北文化の日 」です。その後、11月30日まで、東北各県の文化施設で無料(割引)展示やイベントが行われます。
当館は、11月3日(月・祝)「 #文化の日 」が全館観覧無料日です。 pic.twitter.com/EiNtdZl2l4— 石神の丘美術館〈花とアートの森〉 (@ishigami_muse) October 24, 2025
【入場無料】
さいたま市民音楽祭
11月2日(日)9:30~
さいたま市文化センター 大・小ホールさいたま市内で活動している音楽団体が出演します!
入場無料・途中入退場自由です。#さいたま市 #音楽祭 #文化の日 pic.twitter.com/6ROYuX4uj2— (公財)さいたま市文化振興事業団 (@jigyo01) October 21, 2025
投稿から見えるトレンド傾向
ここ数年の個人のSNS投稿を見ると、「家族で文化体験」「無料開放に行ってきた」「地域のアートフェスが楽しかった」といった声が多く見られます。
文化の日は単なる祝日ではなく、人々がそれぞれの形で文化を感じ、共有する日になっています。
また、文化庁や地方自治体だけでなく、民間企業やショッピングモールなども文化の日に合わせてキャンペーンを展開。
地域経済と文化が融合する流れも広がっています。
SNSで広がる「みんなの文化の日」
リアルとオンラインの両方で楽しめるのが、2025年の文化の日の魅力です。
Xで発信される最新情報をチェックしながら、自分に合った文化体験を見つけてみましょう。
今年は、あなたの投稿も誰かの「文化のきっかけ」になるかもしれません。
ぜひ #文化の日 のタグを付けて、感じたことをシェアしてください。
PR
おうちで「文化と学びの時間」を続けよう
お出かけイベントのあとも、自宅で知育や創造体験を楽しみたい方におすすめ。
Cha Cha Cha(チャチャチャ)は、0〜6歳のお子さま向け知育玩具のサブスクサービスです。
保育士などの有資格者が年齢に合わせておもちゃを選定し、2か月ごとにお届け。
約17,000円相当のおもちゃが月額3,910円〜、初月は1円キャンペーン中!
遊びながら学べる「文化の日の延長体験」としてもぴったりです。
第8章|まとめ|文化の日は「感じて、つなぐ」一日に
文化の日は、自由と平和を愛し、文化をすすめるための祝日です。
そして、私たち一人ひとりが文化の担い手となる日でもあります。
伝統・芸術・学び・人とのつながり——そのどれもが文化を形づくっています。
この記事では、文化の日の由来や意味から、全国で楽しめるイベント、無料開放スポット、そして未来の文化体験までを紹介しました。
文化の日の魅力は「過去・現在・未来」をつなぐことにあります。
歴史を学び、今を楽しみ、未来へ残す。
その循環の中に、文化という言葉の本当の意味が生まれます。
「文化を楽しむ」という生き方
文化は特別な舞台や作品の中だけにあるわけではありません。
通勤途中に聴く音楽、街のギャラリーで見かけた絵、子どもが描いた落書きにも、確かに文化は息づいています。
それらを見つけて大切にすることが、現代の「文化的な生き方」といえるでしょう。
たとえば、休日に美術館へ行くだけでなく、SNSで気に入った作品をシェアしたり、地元イベントを手伝ったりする。
そんな小さな行動が、誰かの心に火を灯し、地域の文化を支える原動力になります。
文化の日は、誰かと一緒に感動を分かち合う日でもあります。
友人や家族と訪れた展示会での会話、SNSで見つけた作品への共感。
そうした共有の瞬間こそが、文化を次の世代へつなぐ力になります。
2025年、そしてその先へ
2025年の文化の日は、AIやデジタル技術の進化によって、文化の形そのものが広がりつつある時代の節目にあたります。
仮想空間で開催されるオンライン展示や、地域と世界を結ぶ文化プロジェクトなど、文化を創る側にも誰もが参加できる時代になりました。
これからの文化の日は、ただ鑑賞するだけでなく、「発信」「参加」「共創」がキーワードになるでしょう。
作品を見るだけでなく、自分の感性を表現すること。
その一歩が、次の時代の文化を形づくるのです。
そして、文化を通して他者を理解し、多様性を尊重する姿勢が、これからの社会をより豊かにしていくはずです。
その始まりの日として、11月3日はますます重要な意味を持つでしょう。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
あなたの毎日が、少しでも前向きになりますように。
文化の日の無料開放や特別展の最新情報は、下記の公式サイトからご確認ください。
リンクはすべて新しいタブで開きます。
関連記事