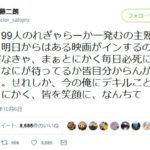この記事の目次です
はじめに
最近再注目されている『今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は』や『ぶぶ漬けどうどす』。
それらを撮った監督たちが、実はすでに過去にとんでもない傑作を世に出していました。
それが、冨永昌敬監督の『南瓜とマヨネーズ』、大九明子監督の『勝手にふるえてろ』です。
この2本を観た時の衝撃は、いま思い返しても強烈に記憶に残っています。
『南瓜とマヨネーズ』:音と余白の中にある人生

臼田あさ美が演じた“ツチダ”の存在感
この映画は、ある女性の”人生の一部”を切り取ったような物語です。
しかしその切り取り方が実に見事で、彼女には映画の前にも後にも確かな人生があると感じさせてくれます。
そしてそれは、私たち自身の人生と地続きでもあります。
世間で言う“立派な人物”はひとりも出てきません。
ただ、ごく平凡な20代の男女が恋をし、つまずき、日常の中でもがきます。
ですがその“平凡”の中にこそ、誰もが共感できる痛みと希望があるのです。
ツチダというキャラクターは、劇的な行動を起こすわけではありません。
ただ、そのまなざしや沈黙にこそ、揺らぎがあり、記憶のような重さが宿っています。
音がすべてを語る映画
冒頭のショット。
シャワーの音、掃除機の音、そして床をこする音。
それらはすべて“労働”の音であり、ツチダの日常の象徴として描かれています。
この映画では、音が感情を伝える手段となっています。
ライブハウスの喧騒、街の雑音、登場人物の泣き声、そして、せいいちの歌。
音楽監修のやくしまるえつこさんによる設計は緻密で、どの音もストーリーと共鳴しています。
観ているうちに、「この映画は音でできている」と感じました。
実際にそのとおりでした。
特に印象的だったのは、掃除機の音やシャワーの音が、ある種の“生活音”でありながら、 彼女の内面のノイズのようにも聴こえてくることです。
つまりこの作品では、音が内面の記録になっているのです。
名シーンたちが刻む余白の強さ
冨永監督の演出は、過剰にならず、それでいて圧倒的な情報量を持っています。
ハギオとの別れの場面、せいいちとツチダのガラス越しの会話、狭い部屋で交わされる視線と間。
本作における恋人たちの描き方は、なによりも空間の分断によって際立っているように感じました。
玄関ドアの外と内に立つふたりは、別れ話を言い出せないまま沈黙を共有しています。
風呂場と廊下という物理的に離れた場所から交わす日常的な会話には、どこかすれ違いの気配が漂います。
そして、窓ガラスという透明でありながら越えられない障壁が、そのままふたりの心の距離を象徴しているのです。
富永昌敬監督は、台詞ではなく“構図”で感情を語ることに長けています。
その静かで計算された構図は、ときに観る者の胸をそっと抉るような切なさを生み出してくれます。
「語らないことで語る」という手法が、ここまで成立していることに驚かされました。
そして、ラストのフラッシュバック。
私は“安易なフラッシュバック”が苦手なのですが、この映画ではまったく違いました。
必要であり、必然であり、強く心を揺さぶるシーンとなっていたのです。
太賀さんが演じるせいいちの歌声、ツチダの泣き顔。
その瞬間、私は劇場で泣きじゃくっていました。
「このシーンだけでも、この映画には十分に価値がある」と思えたほどです。
なお、太賀さんの演技も圧巻でした。
まるで実際のミュージシャンのようで、 何も飾らず、ただそこにいるような佇まいに心を奪われました。
『勝手にふるえてろ』:妄想と現実の“どちらも本当”な感情

ヨシカの物語は“私たち”の感情そのもの
松岡茉優さんが演じるヨシカは、中学生の頃のイチと、現実に存在するニの間で揺れ動きます。
そして観客は、彼女の頭の中と現実との往復運動を、まるで自分のことのように感じ始めるのです。
この作品の最大の魅力は、“おかしさ”と“切なさ”の境界を軽々と超えていくことにあります。
ヨシカの妄想世界は突飛でありながらも、まったく他人事に思えません。
「私にもああいう思考のループがある」と気づいた瞬間、作品との距離が一気に近くなります。
大九明子監督の“ずらし”と“肯定”
1月3日にこの映画を観たときのことを、私はよく覚えています。
客席は満席で、笑いが絶えず、2時間があっという間でした。
ですがその笑いは、ただのコメディではありません。
観終わったあと、じんわりと残るのは“共感”というよりも“許し”のようなものでした。
大九監督は、男性が抱きがちな女性像を壊しながら、女性自身の中にある痛みや違和感も、笑いに変えて抱きしめてくれるのです。
そして、全編ほぼ出ずっぱりの松岡茉優さんが、この物語の芯を見事に貫いています。
その表情の変化、語りのリズム、そして間の取り方。
どれもがヨシカというキャラクターに命を与え、観客の心をつかんで離しません。
赤い付箋──幻想と向き合うラスト
思い出すだけでドキッとする、あの赤い付箋のシーン。
それは決して過激な演出ではないのに、観客の記憶に強烈に焼きつきます。
大九明子監督は、ややセクシュアルにも受け取れる表現を、驚くほど品良く、かつ挑戦的に描いてみせました。
この瞬間、観客の中で“妄想と現実”の線引きがあやふやになり、「私にもこういうことがあった」と思い出してしまう方もいるかもしれません。
それは女子にウケるというだけでなく、男子にとっても、自分の幻想を見つめなおす鏡となるのではないでしょうか。
このシーンこそが、本作のテーマそのものなのだと思います。
赤い付箋が象徴するのは、自己肯定の瞬間です。
観る方の性別や年齢に関係なく、「これが私の人生」と受け止める力をくれる。
男子にこそ、この映画を観てほしいと思います。
2人の監督に共通する“語りすぎない”優しさ
冨永昌敬監督も、大九明子監督も、“演出で語らない”ことに長けた方たちです。
説明しすぎない。
けれど、観た人の中に感情が残る。
日常という、一見するとつまらない風景の中に、どうしようもない揺らぎや決断があることを、私たちは彼らの映画を通して体感できます。
この2人の監督に共通しているのは、“俯瞰”ではなく“寄り添い”の視点で人間を見ているという点です。
そのため、登場人物の欠点すらも、どこか愛おしく感じられます。
そしてその“静けさ”は、何よりも強いのです。
おわりに:この2本を観たなら、次の1本は“今”の作品を
私自身、この2作品に出会ってから、何気ない日常の風景が違って見えるようになりました。
駅のホーム、誰もいない部屋、ふとした音や会話の間。
映画の中で描かれたような瞬間が、確かに私たちの中にも存在しているのだと感じたのです。
『南瓜とマヨネーズ』では、映画が終わってもツチダの人生は続いていくという感覚が強く残ります。
ラストシーンの余韻は、それを観た人それぞれが自分の人生と重ねられる余白でもあります。
あの部屋を出ていったツチダは、いまどこかで別の朝を迎えているのかもしれない──そんな想像が自然と浮かぶのです。
一方で、『勝手にふるえてろ』のヨシカのように、自分の中にあるこじらせた感情や妄想と向き合う時間は、誰にとっても必要なのかもしれません。
現実と幻想の境界が揺らぐとき、私たちはようやく“本当の自分”に出会えるのではないでしょうか。
映画には“自分を変えてしまう力”があります。
『南瓜とマヨネーズ』も『勝手にふるえてろ』も、まさにそうでした。
これらの作品を観たうえで、もしまだ『今日の空が一番好き~』や『ぶぶ漬けどうどす』を観ていないなら、ぜひご覧になってみてください。
冨永昌敬監督も大九明子監督も、変わらず“日常を見つめる映画”を撮り続けています。
だからこそ、彼らの過去作から再評価していくことには意味があるのです。
そして、それはきっと、自分自身の人生を見つめ直すことにもつながっていくのだと思います。
関連リンク