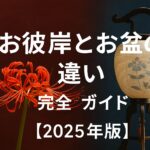七五三の準備を始めると、いつやるのかでまず迷いますよね。
数え年か満年齢か、混雑を避けるならいつが良いのかなど様々なことについて不安になります。
本記事では、読んでくださった方々の判断の基準を明確にするように努めます。
まずは最短の回答。
七五三は10月から11月の都合の良い日で問題ありません。
年齢は数え年でも満年齢でも可ですが、体力とサイズで満年齢が無難です。
写真は前撮り、当日は祈祷中心にすると負担が軽くなります。
衣装は、女の子は3歳が被布、7歳は帯付きの着物が王道です。
男の子は5歳の袴が基本で、歩きやすさを最優先にします。
親の服装は、母は上品フォーマル、父はダークスーツで整います。
主役を引き立てる色と素材感で、家族写真がきれいにまとまります。
費用は衣装、撮影、祈祷、食事の合計で中位の相場になります。
目安は5万から15万円で、体験を分けると予算が組みやすくなります。
初穂料は5千から1万円が一般的で、のし袋は紅白蝶結びを使います。
表書きは初穂料、下段に子どもの氏名で整います。
予約は早いほど選択肢が広がります。
人気日は半年前の仮押さえが安心です。
着物レンタルや写真スタジオは、着付けとヘアセット込みが安全です。
神社の撮影ルールと、出張カメラマンの可否も先に確認します。
当日は導線の短さと待ち時間の少なさが成功の鍵。
午前の早い時間に集約し、移動を最小限に抑えます。
着崩れ対策の小物と、飲み物や軽食を小分けにすると安心です。
草履は前週から室内で慣らしておくと転倒を防げます。
本記事では、
- 日程の決め方
- 年齢の考え方
- 衣装選び
- 親の服装
- レンタルと写真の実務
- 初穂料とお祝いマナー
- 当日の持ち物
までを整理します。
表とチェックリストで、準備の抜け漏れも防ぎます。
七五三は家族の節目です。
伝統を尊重しつつも、等身大で楽しむ選択が結果を良くします。
このガイドを指標に、無理のない段取りを今日から整えてください。
思い出が未来の宝物になるよう、実践的な手順で伴走します。
この記事の目次です
第1章|七五三とは?意味と基本を3分で理解
七五三の本質|子どもの成長に感謝する通過儀礼
七五三は、3歳・5歳・7歳の節目に神社へお参りし、子どもの健やかな成長を祈る行事です。
現代では華やかな記念撮影のイメージが強いですが、もともとは「神に感謝を伝える儀式」が原点にあります。
古来の日本では、幼少期の生存率が高くありませんでした。
そのため、3歳・5歳・7歳を迎えられること自体が、家族にとって大きな喜びだったのです。
七五三の由来|平安時代から続く3つの儀式
七五三は平安時代に始まり、江戸時代に現在の形が整いました。
当時は武家や公家の子どもたちが行っていた儀式が庶民にも広まり、現在に続いています。
| 年齢 | 名称 | 意味・由来 |
|---|---|---|
| 3歳 | 髪置(かみおき)の儀 | 髪を伸ばし始める節目。健康成長の祈願。 |
| 5歳 | 袴着(はかまぎ)の儀 | 初めて袴を着て社会性を身につける儀式。 |
| 7歳 | 帯解(おびとき)の儀 | 帯を使い始める節目。少女から一人前の女性へ。 |
この3つの儀式が合わさり、現在の「七五三」という名称が生まれました。
数字の並び「七・五・三」は縁起が良く、奇数が吉とされる陰陽道の考え方にも基づいています。
3=成長の始まり、5=心身の独立、7=知恵と社会性の完成を象徴します。
七五三の目的|伝統を守りながら現代的に楽しむ
現代の七五三は、単なる儀式ではなく「家族の記念日」としての意味が強まっています。
写真撮影やレンタル着物、レストランでの食事会など、スタイルは家庭ごとに自由です。
ただし、形式を守るよりも「感謝と願いの心」を伝えることが本質。
子どもにとっても、自分が祝われる喜びを感じる大切な経験になります。
七五三は、子どもが家族の愛情を実感する貴重な機会です。
伝統と笑顔をつなぐ家族の節目
七五三は、古くから続く伝統と現代の家族文化が交わる行事です。
由来を知ることで、単なるイベントではなく、感謝と希望の意味を再確認できます。
この基本を理解した上で、次章では「いつやるのが正しいか」という実践的な疑問に答えていきます。
第2章|七五三はいつやる?日程と混雑回避
七五三の日にちの基本|正式日は11月15日
七五三は、毎年11月15日が正式な日とされています。
この日は江戸時代、徳川家の五代将軍・徳川綱吉の子ども「徳松君」の祝いに由来すると伝わります。
当時は健康祈願の儀式として宮中で行われ、それが全国に広まったのが始まりです。
しかし、現在では11月15日にこだわる必要はありません。
多くの家庭が10月中旬から11月下旬にかけて、都合の良い週末や祝日にお参りをしています。
特に写真撮影や神社のご祈祷予約が混み合うため、早めの行動が安心です。
大切なのは日付よりも「家族全員で笑顔になれる日」を選ぶことです。
地域による違い|北海道・東北は1か月前倒しが主流
寒冷地では気候の関係で、11月中旬だと雪や寒さが厳しくなるため、10月中旬にお参りを行う地域が多いです。
北海道・東北・北陸などは、早めの10月上旬に祈祷を済ませる家庭もあります。
一方、九州や四国など温暖な地域では、11月後半でも快適に行えるケースが多く、七五三のシーズンは全国的に1か月程度ずれる傾向があります。
| 地域 | おすすめ時期 | 気候の特徴 |
|---|---|---|
| 北海道・東北 | 10月上旬〜中旬 | 寒冷で早い雪対策が必要 |
| 関東・中部 | 10月中旬〜11月中旬 | 晴天率が高く撮影日和 |
| 関西・九州 | 11月上旬〜下旬 | 穏やかな気候でお参り向き |
写真スタジオや神社の公式サイトで、地域ごとの推奨時期を事前に確認しましょう。
六曜と縁起|大安が人気だがこだわりすぎなくて大丈夫
多くの家庭が「縁起の良い日」を意識して大安を選びますが、実際は友引や先勝でも問題ありません。
神社の祈祷はどの日でも受け付けており、六曜はあくまで目安です。
特に共働き家庭では、土日や祝日の予定調整が最優先になります。
六曜にこだわりすぎると予約が集中し、かえって混雑や費用増につながることもあります。
| 六曜 | 意味 | 七五三向き? |
|---|---|---|
| 大安 | 何事も吉。最も人気。 | ◎ |
| 友引 | 「友に福を分ける」とも。 | ○ |
| 先勝 | 午前中が吉。 | ○ |
| 赤口 | 午前11〜13時のみ吉。 | △ |
| 仏滅 | 基本的に凶日とされる。 | × |
神様は日付よりも「感謝の心」を重んじます。
六曜よりも、家族全員が集まれる日を優先しましょう。
早生まれ・年中児の場合|どちらの年に祝うべき?
「うちの子は早生まれだから、どの年にやればいいの?」という質問も多いです。
七五三は「数え年」でも「満年齢」でもどちらでも構いません。
ただし、写真映えや体力面を考えると満年齢でのお祝いが主流になっています。
たとえば4月生まれと翌年3月生まれでは、体格や集中力に大きな差があります。
同級生との比較よりも、その子が落ち着いて楽しめる年齢で決めるのが最善です。
家族が動きやすく、本人が楽しめるタイミングを選びましょう。
混雑回避のコツ|平日・午前・分散参拝でゆったり
七五三シーズンの週末は、神社や写真館が最も混雑します。
混雑を避けるには「平日」「午前中」「早期前撮り」がポイントです。
- 平日午前(10時前後)は祈祷も撮影もスムーズ
- 11月第2・第3土日は特に混みやすい
- 撮影とお参りを別日に分けると子どもの負担が軽減
最近は神社でも分散参拝を推奨する動きが広がっています。
分散参拝(ぶんさんさんぱい)とは?
七五三のお参りを特定の日(11月15日前後)に集中させず、10月〜12月など複数の時期に分けて行う方法のことです。
もともとは新型コロナ対策から広がった考え方で、混雑を避けてゆっくり祈祷を受けられるメリットがあります。
大勢の参拝客が重なると、待ち時間や写真撮影の順番待ちが発生するため、神社や写真館も「分散参拝」を積極的に推奨しています。
例えば、お参りは10月・写真は11月・お食事会は別日と分けることで、子どもの負担を軽減できます。
体調不良や天候にも柔軟に対応できるのが魅力です。
- 10月上旬:早めの祈祷で混雑回避
- 11月中旬:気候が安定して撮影に最適
- 12月上旬:後撮りや家族都合に合わせやすい
このように日程をずらすことで、焦らず、家族全員で楽しめる七五三になります。
神社によっては公式に「分散参拝」を案内している場合もあるため、予約ページやSNSで事前に確認しておくと安心です。
写真スタジオでは「前撮り特典」や「秋先取りキャンペーン」が多く、9月撮影が最もコスパが高い傾向です。
秋晴れの日を狙えば、写真も美しく仕上がります。
天候と時間帯の選び方|子どもの機嫌を左右する要素
七五三は、子どもにとって初めて長時間外出する儀式でもあります。
気温が高すぎたり、風が強い日は疲れやすくなり、せっかくの撮影も笑顔が減ってしまいます。
快適な環境で過ごすには、午前9〜11時頃がベストです。
昼過ぎになると眠気や空腹が重なり、集中力が落ちやすくなります。
涼しく光が柔らかい時間帯は、写真も自然で綺麗に撮れます。
日付よりも「気持ちと体調」を最優先に
七五三は11月15日に限定されません。
地域・気候・家庭の都合によって、最適な時期はそれぞれ異なります。
混雑を避け、子どもの笑顔を最優先に計画することが大切です。
早めの準備と柔軟なスケジュールで、余裕のある七五三を迎えましょう。
次章では、「数え年と満年齢、どちらで祝うのがよいか」をさらに掘り下げて解説します。
第3章|数え年と満年齢どちらで祝う?年齢の決め方と考え方
七五三の年齢は2通りある
七五三の年齢には「数え年」と「満年齢」の2つの考え方があります。
どちらが正解というわけではなく、家庭の状況や子どもの成長に合わせて自由に選べます。
| 年齢の数え方 | 特徴 | 向いている家庭 |
|---|---|---|
| 数え年 | 生まれた年を1歳とし、元日を迎えるごとに1歳加算する。 | 伝統重視・祖父母と相談して決めたい家庭 |
| 満年齢 | 誕生日を迎えてから1歳加算する。現在の公的な年齢表示に近い。 | 現代的・体格やスケジュールを優先したい家庭 |
昔は「数え年」が一般的でしたが、今は約7割が満年齢でお祝いしています。
その理由は、子どもの発達や衣装サイズが合いやすいこと、集中力が続くことなどが挙げられます。
体の成長と気持ちの安定、そして家族の都合を基準に決めましょう。
数え年で行うメリットと注意点
数え年は、古くから伝わる伝統的な考え方です。
祖父母世代の理解も得やすく、神社や地域の慣習に沿うという安心感があります。
ただし、2歳や4歳での参加になる場合もあり、着物のサイズや集中力の面で負担が大きくなることがあります。
体格が小さい子は、草履や袴が合わず、当日にぐずってしまうことも少なくありません。
どちらが正しいではなく、家庭ごとの最適解を見つけることが大切です。
満年齢で行うメリットと安心感
満年齢は、子どもが成長してからお祝いできるため、負担が少なく笑顔の写真を残しやすいのが特徴です。
3歳の七五三を満年齢で行うと、すでに4歳近くになっているケースもあり、落ち着いて祈祷や撮影をこなせます。
衣装の選択肢も増え、着物レンタルのサイズに余裕があるため、費用も抑えやすくなります。
「無理せず楽しむ七五三」を目指す家庭には、満年齢がおすすめです。
スケジュールの自由度が高く、撮影も落ち着いて行えます。
兄弟・姉妹がいる場合の合わせ方
兄弟・姉妹がいる場合は、同時にお祝いする「合同七五三」が人気です。
特に3歳と5歳、あるいは5歳と7歳が近い年齢なら、一度に行うと費用と手間が半減します。
ただし、衣装や祈祷の内容が異なるため、子どもごとの主役感を出す工夫が必要です。
一緒に撮る写真だけでなく、ソロカットを別日に撮影する家庭も増えています。
撮影は別日、祈祷は同日という形が最もスムーズです。
年齢をずらしてもOK|柔軟な考え方が主流に
現代の七五三では、「早生まれ」「発達の個人差」「家庭の都合」に応じて、1年前後ずらす家庭も珍しくありません。
特に、3歳の七五三を4歳で行う、5歳を6歳で行うケースは自然な流れです。
「今年は下の子の出産が重なる」「引っ越しで余裕がない」などの事情がある場合も、翌年にずらして問題ありません。
七五三は神社への感謝の行事であり、年齢を厳密に合わせる必要はないのです。
家庭のペースで祝うことが、子どもにとって一番の思い出になります。
再撮影・後祝いの選択肢
もし当日に体調不良や天候不良で参加できなかった場合、「後撮り」「再祈祷」も可能です。
神社によっては、年明けや節分まで七五三祈祷を受け付けているところもあります。
特に近年は感染症対策や混雑回避のため、柔軟なスケジュールが認められるようになっています。
12月でも受け付けてくれる神社が多く、焦らずに準備できます。
当日が無理でも、後日改めて祝えば心に残る七五三になります。
年齢よりも「家族のタイミング」を優先しよう
七五三は、年齢の数字にとらわれず、その子に合ったタイミングで祝うのが理想です。
数え年でも満年齢でも、早くても遅くても、家族の思いがあればそれが正解になります。
次の章では、いよいよ七五三の華である「衣装と親の服装」を詳しく解説します。
主役をより美しく引き立てるためのコーディネートを見ていきましょう。
第4章|七五三の着物と親の服装ガイド
子どもの衣装選びの基本
七五三は、子どもの成長を祝い「節目」を残す行事です。
そのため、着物や袴といった伝統衣装は、神社での祈祷や写真撮影に最もふさわしい装いとされています。
ただし、近年では和装と洋装を組み合わせるスタイルも人気です。
お参りは着物で、写真撮影はドレスやスーツなど柔軟に使い分ける家庭も増えています。
一度きりの行事だからこそ、家族で納得できる形を選びましょう。
女の子の衣装|3歳と7歳で異なるスタイル
女の子の七五三は、3歳は「被布(ひふ)」、7歳は「帯付き着物」が基本です。
3歳(初めての七五三)
3歳はまだ着物を着慣れていないため、重ね着の少ない被布が主流です。
軽くて動きやすく、着崩れしにくいのが特徴。
色は淡いピンクやクリーム系が人気で、髪飾りは小ぶりのリボンやつまみ細工がよく合います。
7歳(本格的な帯結び)
7歳になると、帯を結ぶ「四つ身の着物」で大人の装いに近づきます。
金糸や花柄、古典文様など華やかな柄が映え、髪型もアップスタイルや日本髪が人気です。
レンタルでは帯・草履・バッグがセットになっており、撮影用にフルコーディネートできます。
| 年齢 | 基本衣装 | 人気カラー |
|---|---|---|
| 3歳 | 被布セット(着物+被布+髪飾り) | ピンク/白/ベージュ |
| 7歳 | 帯付き着物(四つ身・袋帯) | 赤/水色/紫/古典柄 |
同じ子でも年齢で衣装の意味が変わります。
男の子の衣装|5歳の袴スタイル
男の子は5歳で七五三を迎えます。
この年齢での祝いは「袴着の儀(はかまぎのぎ)」に由来し、成長の証として袴を初めて身につけます。
定番は羽織袴スタイルで、黒・紺・グレーが中心。
龍や鷹、兜など勇ましい柄が多く、近年は白やベージュなどナチュラル系のモダン袴も増えています。
袴の丈が長すぎると転倒しやすいため、レンタル前に試着やサイズ確認を忘れずに。
着物レンタルのポイント
着物を購入するよりも、最近はレンタルサービスの利用が主流です。
スタジオアリスやらかんスタジオ、VASARA(バサラ)などが定番ブランドとして人気を集めています。
料金相場は以下の通りです。
| 項目 | レンタル相場 | 備考 |
|---|---|---|
| 3歳女の子 | 1〜3万円 | 被布+小物+着付け込み |
| 5歳男の子 | 1.5〜3.5万円 | 袴・羽織・草履込み |
| 7歳女の子 | 2〜5万円 | 帯・髪飾り・ヘアセット込み |
ブランド着物や新作デザインを希望する場合は+1万円前後を目安に。
楽天レンタルなどのネットサービスなら、往復送料無料で自宅着付けも可能です。
早撮り割引や「秋前レンタル」プランを上手に使うとコスパが上がります。
母親の服装|上品で主役を引き立てる
母親の服装は「控えめで上品」が鉄則です。
着物の場合は訪問着・色無地・附け下げが代表的。洋装の場合はワンピースやセットアップが人気です。
- 和装:淡いベージュ・水色・薄紫が定番
- 洋装:膝下丈のワンピースにジャケット
- 靴:ヒール低めのパンプス(黒・ベージュ系)
子どもの着物とのバランスを意識し、全体のトーンをやさしくまとめましょう。
父親の服装|フォーマル感と清潔感を両立
父親の服装はダークスーツ+白シャツ+ネクタイが基本です。
黒一色では重くなりやすいので、ネイビーやチャコールグレーが自然。
家族写真のバランスを考え、ネクタイはシルバー系や淡いブルーを選ぶと上品に見えます。
カジュアルな神社や写真撮影なら、ノーネクタイ+ジャケットスタイルでも可。
ただし、スニーカーやサンダルは避けましょう。
控えめな装いでも、姿勢や清潔感で全体の印象を引き上げられます。
祖父母・兄弟姉妹の服装マナー
祖父母はスーツやセミフォーマル、兄弟姉妹は落ち着いた色味の洋服を選ぶと写真が整います。
派手すぎる色は主役の印象を分散させるため、淡色をベースにまとめましょう。
兄弟が未就学児の場合、長時間の神社参拝は疲れやすいので、軽装+防寒具を持参すると安心です。
服装の打ち合わせを前日に行っておくと、当日慌てません。
装いは「思い出を残すための舞台装置」
七五三の衣装や服装は、単なるファッションではなく家族の記憶を形にする大切な要素です。
派手さよりも「清潔感」「調和」「季節感」を意識すると、後から写真を見返しても好印象が続きます。
次の章では、七五三の写真撮影とポーズ・ロケーション選びについて詳しく解説します。
スタジオ撮影と屋外撮影、それぞれのメリットを比較していきます。
第5章|写真撮影・ロケーション・ポーズ完全ガイド
七五三写真は「前撮り」が基本になりつつある
近年、七五三の撮影スタイルは「お参りと別日」に行う前撮りが主流です。
理由は明確で、混雑を避けられるうえに、子どもの機嫌や天候にも合わせやすいからです。
スタジオによっては、5月〜9月にかけて「早撮りキャンペーン」を実施しており、撮影料無料や衣装2着目サービスなど、秋の本番よりもお得なプランが選べます。
秋のお参り前に撮影を済ませると、家族も余裕を持って当日を迎えられます。
ロケーション撮影とは?
ロケーション撮影とは、スタジオではなく神社や公園などの屋外で撮る写真スタイルです。
自然光でのびやかな雰囲気が残せるため、Instagramでも人気が高まっています。
特に紅葉シーズンは、朱色の鳥居や金色の落ち葉と着物のコントラストが美しく、家族写真としても一生の記念になります。
ただし、神社によっては境内撮影に許可が必要な場合があります。
出張カメラマン(ラブグラフ・OurPhotoなど)を利用する際は、撮影可否と祈祷中の撮影ルールを必ず確認しましょう。
事前に神社の撮影ルールを確認し、出張カメラマンと時間を調整しましょう。
スタジオ撮影のメリット
スタジオ撮影は、天候に左右されず衣装チェンジが自由にできるのが利点です。
照明設備が整っており、子どもの動きや表情を逃さず撮影できます。
背景を変えた家族写真や兄弟カットもスムーズで、スタッフのサポートが手厚いため、小さな子どもでも安心です。
| 撮影タイプ | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| スタジオ撮影 | 天候に左右されず安定。衣装変更・ヘアセットも可。 | 自然光は使えないため、屋外感は薄め。 |
| ロケーション撮影 | 自然光・神社背景で映える。自由な表情が出やすい。 | 天候とスケジュール調整が必要。 |
写真のポーズと構図のコツ
子どもは緊張すると笑顔が硬くなりがちです。
スタジオではカメラマンが自然な笑顔を引き出してくれますが、家庭で撮る場合は「動きを止めない」のがコツです。
- 歩きながらの後ろ姿
- 草履を履く瞬間
- 千歳飴を持つ笑顔
- 家族で手をつなぐシーン
こうした「日常の中の一瞬」こそが、後から見返したときに温かい記憶として残ります。
親もカメラを意識しすぎず、日常のやり取りを楽しむ気持ちで臨みましょう。
写真データとアルバムの相場
七五三撮影の費用は、スタジオ・プラン・データ数によって大きく異なります。
平均的な相場は以下の通りです。
| プラン内容 | 相場価格 | 備考 |
|---|---|---|
| データのみ(全カット) | 2〜4万円 | 自宅プリントやSNS投稿向け |
| 台紙付きアルバム | 3〜6万円 | 祖父母プレゼントに人気 |
| ロケーション出張撮影 | 2.5〜5万円 | 撮影時間1時間前後、データ100枚程度 |
スタジオによっては「家族写真無料」「きょうだい一緒プラン」などの特典もあります。
後からデータを追加購入すると割高になるため、最初から全データ付プランを選ぶのが安心です。
写真は「今を残す贈り物」
七五三の写真は、子どもの成長を「目に見える形」にする記録です。
完璧なポーズを目指すより、家族が笑って過ごす空気感を残す方が価値があります。
プロの技術と家庭の温もりを掛け合わせて、何年たっても見返したくなる「未来への贈り物」を作りましょう。
第6章|お祝い・初穂料・マナー完全ガイド
初穂料(はつほりょう)とは?
初穂料とは、神社で祈祷を受ける際に納めるお礼金のことです。
もともとは「その年初めて収穫した稲穂を神様に捧げる」という意味があり、今では祈願に対する感謝の気持ちを込めてお渡しする金銭として定着しています。
3,000〜10,000円程度(5,000円が最も一般的)
兄弟姉妹で祈祷を受ける場合は、1人ずつ包む神社もあります。
封筒は「のし袋(紅白蝶結び)」を使用し、表書きは「初穂料」または「御初穂料」。
子どもの名前をフルネームで記入します。
神社によっては祈祷申込書と一緒に納める方式を取っている場合もあるので、受付で確認しましょう。
お祝い金・プレゼントの相場
祖父母や親戚からの七五三祝いとして、お祝い金やプレゼントをいただくケースも多いです。
| 贈り主 | 金額の目安 | 内容例 |
|---|---|---|
| 祖父母 | 1〜3万円 | 着物代・写真代・お祝い金など |
| 親戚 | 5,000〜1万円 | おもちゃ・図鑑・ギフトカード |
| 友人・知人 | 3,000〜5,000円 | お菓子・フォトフレーム・商品券 |
金額よりも「気持ち」が大切です。
現金で渡す場合は、新札を用意し、のし袋に「祝七五三」または「御祝」と記載します。
お祝いの食事会マナー
お参り後に行う食事会は、子どもの成長を家族でお祝いする時間です。
高級レストランや料亭だけでなく、最近は自宅やホテルの個室など、さまざまな形式で行われています。
服装はフォーマルを維持しつつ、食べやすさや子どもの動きを考慮しましょう。
母親はシンプルなワンピース、父親はジャケットスタイルでも十分です。
・お子様ランチ風の和洋折衷メニュー
・お赤飯や鯛の塩焼きなど縁起料理
・ケーキで「七五三おめでとう」を演出
食事会のタイミングは、祈祷のあとすぐでも、日を改めても問題ありません。
祖父母が遠方に住んでいる場合は、写真付きメッセージカードを送るのも喜ばれます。
神社でのマナーと注意点
- 境内では大声で騒がず、他の参拝者に配慮する
- スマートフォン撮影は祈祷中NGの神社が多い
- 記念写真は他の家族を避け、端や外で行う
- お賽銭は家族で順番に。金額は気持ちでOK
特に祈祷中は静かにし、子どもにも「神様にありがとうを言う日」と説明すると理解しやすいです。
「無事にここまで育ちました、ありがとうございます」という気持ちを込めて参拝しましょう。
七五三のお返し(内祝い)
お祝いをいただいた場合は、1〜2週間以内に「お礼の言葉」とともにお返しを贈りましょう。
品物は半返し(いただいた金額の半分程度)が目安です。
- 菓子折り・紅白まんじゅう・焼き菓子
- 写真付きメッセージカード
- 名入れタオルやカタログギフト
メールやLINEで済ませるのではなく、できれば手書きのメッセージを添えると気持ちが伝わりやすいです。
七五三は「感謝と未来をつなぐ日」
七五三は、子どもの無事な成長を祈り、家族で感謝を分かち合う大切な行事です。
衣装や写真、マナーに正解はなく、「家族全員が笑顔で過ごせるかどうか」がいちばんのポイントです。
慌ただしい日常の中で、改めて子どもの成長を感じられる日。
小さな「ありがとう」を写真や言葉に残し、未来の記念日にしていきましょう。
写真・祈祷・お祝い、どの瞬間も心をこめて楽しむことが何よりのご利益です。
第7章|七五三のよくある質問(FAQ)
Q1. 七五三は数え年?それとも満年齢?
昔は数え年(生まれた年を1歳として数える)で行うのが一般的でした。
ただし現代では、保育園・幼稚園の予定や兄弟の年齢に合わせて、満年齢で行う家庭が多数派です。
特に3歳の女の子はまだ小さいため、満3歳の春〜秋に合わせると無理なく参加できます。
家庭の都合と子どもの成長ペースを優先して選びましょう。
Q2. 七五三は兄弟同時でもいい?
はい、もちろん問題ありません。
5歳と3歳、7歳と5歳など、年齢が近ければ一緒にお祝いする「合同七五三」が効率的です。
衣装や祈祷料はそれぞれ用意しますが、家族写真をまとめて撮影できるため、祖父母にとっても記念になります。
Q3. お参りは午前・午後どちらが良い?
午前中がおすすめです。
理由は、子どもが元気で機嫌が良く、神社も混雑しにくいからです。
午後は光の加減が柔らかくなるため、ロケーション撮影をする場合は午後撮影も人気です。
一日の流れをゆったり組むと、子どもも疲れにくくなります。
Q4. 七五三の着物は購入・レンタルどっちがいい?
使用回数が少ないため、レンタルが7割以上を占めています。
最新デザインや小物がセットになっているので、管理やクリーニングの手間がかかりません。
一方で、祖父母から譲り受けた着物やオーダー品は、代々受け継ぐ「記念の一着」として価値があります。
| 方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| レンタル | 安価・種類豊富・小物も一式揃う | 返却期限あり・サイズ調整が限定的 |
| 購入 | 記念として残る・兄弟姉妹に使える | 高価・保管に注意が必要 |
Q5. 七五三の撮り直しはできる?
もちろん可能です。
子どもの体調や天候で撮影がうまくいかないこともあります。
スタジオによっては「撮り直し無料サービス」が付いている場合もあります。
写真は一度きりのものではなく、「子どもの笑顔を残す」ことが目的です。
焦らず柔軟に日程を調整しましょう。
混雑を避けつつ、自然な笑顔が撮りやすい時期です。
Q6. 七五三の記念品は何を残すべき?
定番はアルバムと写真データですが、最近はフォトフレーム・アクリルスタンド・ムービー化など、デジタルとアナログを融合した記念の形も増えています。
特に、祖父母向けのフォトギフトや「子どもの声を入れた動画」は感動的です。
SNS投稿時は位置情報や氏名を避けて、安全面にも注意しましょう。
PR
家族の「今」を美しく残そう
七五三の思い出を自然な笑顔で残したい方へ。
出張撮影サービスOurPhoto(アワーフォト)なら、プロのフォトグラファーが神社や公園などお好きな場所に出張し、50分間たっぷり撮影してくれます。
撮影料・出張費・データ30枚込みで11,000円(税込)〜。
フォトグラファーは全国1,900名以上。
七五三・お宮参り・お誕生日など、家族の記念日にぴったりです。
PR
写真をかたちに残すならフォトレボ
フォトレボ(PhotoRevo)は、パソコンから簡単に作れる高品質フォトブックサービスです。
七五三やお宮参りの写真を、美しく一冊にまとめたい方におすすめ。
1冊1,200円〜から作成可能。
7色印刷で色あざやかに再現し、最短3営業日で出荷されます。
テンプレートも豊富で、初心者でも簡単に編集できます。
第8章|まとめ|七五三は「家族の物語」を祝う日
七五三は、ただの行事ではなく「家族の節目を祝う日」です。
日程・衣装・写真・マナー・・・すべてに共通するのは「感謝の心」と「子どもの笑顔」です。
本記事で紹介した内容をまとめると、次のようになります。
| 項目 | 要点まとめ |
|---|---|
| 日程 | 11月15日前後が基本。混雑回避には分散参拝がおすすめ。 |
| 衣装 | レンタル主流。家族でテーマカラーを揃えると写真映え。 |
| 写真 | 前撮りが人気。自然な笑顔を大切に、プロ撮影と家庭撮影を併用。 |
| 初穂料 | 5,000円前後が目安。紅白蝶結びののし袋で丁寧に。 |
| お祝い | 祖父母から1〜3万円が相場。半返しの内祝いも忘れずに。 |
形よりも心を大切に──それが最高の思い出をつくる近道です。
準備は大変に感じても、当日は一瞬です。
その日の笑顔と空気を、写真や記憶にたっぷり刻んでください。
何年後かに振り返ったとき、きっとあの一日が家族の宝物になります。
家族の「ありがとう」が届く日、それが七五三です。
関連記事
- 文化の日イベント特集|全国の無料開放・お出かけスポットまとめ【2025年版】
- 唐津くんち2025完全ガイド|日程・曳山・見どころ・アクセス・屋台情報【保存版】
- お彼岸とお盆の違い完全ガイド|意味・由来・お参り・食べ物まで徹底解説【2025年版】
- 自衛隊音楽まつり2025|当選発表・倍率・入場証メール・セトリ・持ち物まとめ【武道館】
- 勤労感謝の日2025|いつ・由来・意味・手作りプレゼント完全ガイド
- 【2025→2026】年賀状の最終受付はいつまで?郵便局・コンビニ・宅配を完全比較
- 2025年の最強開運日「12月21日」は天赦日×一粒万倍日!やるべきこと・避けること完全ガイド
- お年玉 総まとめ|意味・相場・マナー・贈与税・歴史・LINE送り方まで最新トレンド完全ガイド
- 成人の日はいつ?何歳を祝う?祝日・休み・由来まで完全ガイド【2026年最新版】
- 七草粥とは?意味・由来・いつ食べるのかを完全解説|由来から分かる食べる日の理由