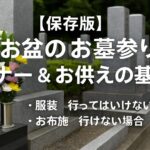「お彼岸」と「お盆」は、どちらもご先祖さまを供養する大切な行事ですが、実は意味や時期、過ごし方に大きな違いがあります。
簡単にまとめると、
- お彼岸:春分・秋分を中心に年2回行われる。先祖供養に加え「自然を敬う」意味合いがあり、ぼたもち・おはぎを供える習慣がある。
- お盆:夏に一度だけ行う行事。ご先祖の霊を自宅に迎え、盆踊りや精霊流しなど地域色豊かな風習が根付いている。
つまり、お彼岸=自然や仏教的な節目、お盆=ご先祖の霊を迎えて共に過ごす行事という点が最大の違いです。
本記事では、
- お彼岸とお盆の意味・由来
- 行事内容やお参りの仕方
- お供え・食べ物の違い
- 現代ならではの過ごし方
までを、わかりやすく解説していきます。
違いを正しく理解すれば、ご先祖を敬う気持ちがより深まり、日々の供養や行事も自然と丁寧なものになります。
この記事の目次です
第1章:お彼岸とは?
お彼岸の意味と由来
「お彼岸」とは、春分の日・秋分の日を中日とした前後7日間(計14日間)に行われる仏教行事です。
「彼岸(ひがん)」は仏教用語で「悟りの境地」を意味し、私たちが生きている世界=「此岸(しがん)」と対比されます。
昼と夜の長さがほぼ同じになるこの時期は、太陽が真西に沈むことから、西方浄土(極楽浄土)に通じる特別な期間と考えられてきました。
目的と行事の特徴
お彼岸は、ご先祖を供養し、自分自身の心を見つめ直す時間として大切にされてきました。
お墓参りをして手を合わせるだけでなく、写経・座禅・読経・善行などを実践し、六波羅蜜(布施・持戒・忍辱・精進・禅定・智慧)を修める習慣とも深く結びついています。
お参りの仕方
- お墓や仏壇をきれいに掃除する
- 季節の花(菊・彼岸花など)を供える
- 家族そろって手を合わせる
お彼岸は「お墓参りの季節行事」というイメージが強いですが、もともとは自己修養と先祖供養を両立させる行事なのです。
お彼岸の食べ物

お彼岸といえば 「ぼたもち」「おはぎ」。
実際は同じものですが、春(牡丹の季節)は「ぼたもち」、秋(萩の季節)は「おはぎ」と呼び分けられます。
小豆の赤色には古来より「魔除け」の意味が込められており、先祖供養とともに家族の無病息災を祈る習わしが続いています。
第2章:お盆とは?
お盆の意味と由来
「お盆(盂蘭盆会/うらぼんえ)」は、毎年7月または8月に行われる先祖供養の行事です。
語源はサンスクリット語の「ウラバンナ」で、「逆さに吊るされるような苦しみ」を意味し、先祖の霊を供養することでその苦しみから救うという教えに基づいています。
仏教伝来とともに日本に広まり、平安時代以降は庶民にも定着しました。
目的と行事の特徴
お盆は、ご先祖の霊を迎え入れ、家族とともに過ごし、再び送り出す行事です。
迎え火・送り火、盆踊りなどはその象徴的な風習。
特に盆踊りは、先祖供養の意味に加え、地域の交流や娯楽としても大切にされてきました。
お参りや準備
- 迎え火を焚いて先祖の霊を家に迎える
- 仏壇や精霊棚(盆棚)を用意する
- 野菜で作った精霊馬(きゅうりの馬・なすの牛)を供える
- 送り火を焚いて霊を見送る
地域によっては灯籠流しや花火大会など、多彩な風習が見られるのもお盆の特徴です。
お盆の食べ物
お盆では、精進料理や季節の果物、そうめんなどを供えるのが一般的です。
特に「精霊馬」は、お盆を象徴する供え物で、きゅうりの馬はご先祖を早く迎えるため、なすの牛はゆっくり帰っていただくためといわれています。
第3章:お彼岸とお盆の違い
共通点と違いの全体像
「お彼岸」と「お盆」は、どちらもご先祖を供養する大切な行事ですが、目的・時期・行事内容に明確な違いがあります。
ここでは、両者を比較しながら整理してみましょう。
違いをわかりやすく一覧表で整理
| 項目 | お彼岸 | お盆 |
|---|---|---|
| 時期 | 春分・秋分の日を中日とした前後7日間 | 7月または8月(地域によって異なる) |
| 由来 | 仏教の「彼岸(悟りの境地)」思想 | 盂蘭盆会(ウラバンナ)の供養行事 |
| 目的 | ご先祖供養と自己修養 | ご先祖の霊を迎え入れ、共に過ごし、送り出す |
| 行事 | 墓参り・仏壇供養・写経や座禅 | 迎え火・送り火・盆踊り・灯籠流し |
| 食べ物 | 春はぼたもち、秋はおはぎ | 精霊馬(きゅうりの馬・なすの牛)、精進料理 |
| 宗教的背景 | 太陽が真西に沈む=極楽浄土に通じる | ご先祖の霊を苦しみから救い、共に過ごす |
共通点
両者に共通するのは、「ご先祖を敬い、感謝を伝える」という点です。
時期や形式は違っても、家族が集まって供養を行う行事であることに変わりはありません。
また、どちらも仏教の影響を受けつつ、日本独自の風習として発展してきた点も共通しています。
違いを知ることの意義
お彼岸とお盆の違いを理解することで、それぞれの行事の意味をより深く感じながら過ごすことができます。
「お彼岸だからぼたもちを供える」「お盆だから精霊馬を作る」といった習慣の背景を知れば、ご先祖への感謝の気持ちも自然と高まるでしょう。
お彼岸はいつからいつまで?【2025年版】
お彼岸は、春分・秋分の日を「中日」とし、その前後3日を合わせた計7日間です。
中日を中心にお墓参りや供養を行うのが一般的です。
| 季節 | 期間 | 中日 |
|---|---|---|
| 春彼岸 | 2025年3月17日(月)〜3月23日(日) | 3月20日(木・春分の日) |
| 秋彼岸 | 2025年9月19日(金)〜9月25日(木) | 9月23日(火・秋分の日) |
期間中は仏壇やお墓を整え、先祖供養を行うのが習わしとされています。
第4章:お参り・お供えのマナー

お参りに行くタイミング
お彼岸やお盆でのお参りは、一般的に午前中〜日中の明るい時間帯に行うのが望ましいとされています。
ただし、絶対的な決まりはなく、家族の予定や地域の習慣に合わせて差し支えありません。
大切なのは「心を込めて手を合わせる」気持ちです。
服装のマナー
法事のような正式な場では喪服を着用しますが、通常のお彼岸・お盆のお参りは地味で清潔感のある服装で十分です。
派手な色柄や露出の多い服装は避け、落ち着いた雰囲気を意識すると良いでしょう。
お彼岸のお供えと金額相場
お彼岸では、お菓子や果物、季節の和菓子(ぼたもち・おはぎ)などをお供えするのが一般的です。
最近では線香や花束、果物ギフトも選ばれています。
- 花:菊や彼岸花など季節の花が定番。トゲのあるバラや毒性のある花は避ける。
- 食べ物:お彼岸は「ぼたもち・おはぎ」、お盆は「精霊馬」「精進料理」が代表的。
- 果物:リンゴ・ぶどう・梨など旬の果物を少量ずつ。
- 線香:香りで霊を導くとされる。火の扱いに注意。
地域や家庭によってしきたりは異なるため、「供えすぎない・食べ物は新鮮なうちに下げる」といった配慮も大切です。
また、お供えや金額の目安は以下の通りです。
| 関係性 | 金額の目安 | 表書き(のし) |
|---|---|---|
| 親族・身内 | 3,000〜5,000円程度 | 御仏前/御供 |
| 知人宅へ訪問 | 1,000〜3,000円程度 | 御供 |
| お寺(御布施) | 5,000〜10,000円程度 | 御布施 |
お金を包む場合は、白黒や双銀の水引を用い、「御仏前」「御供」と書くのが一般的です。
大切なのは金額よりも、ご先祖や故人を思う気持ちを表すことです。
お墓参りの流れ
- 墓石や周囲をきれいに掃除する
- 花立や水鉢に水を入れ直す
- お供えを並べ、線香をあげる
- 家族そろって静かに合掌する
一連の流れを通して、ご先祖に感謝を伝えることが最も大切です。
仏壇での供養
自宅の仏壇での供養も忘れてはいけません。
花や果物を供え、線香を焚いて合掌するだけでも十分。
特にお盆では精霊棚(盆棚)を設けて先祖の霊を迎える習慣が残っています。
注意点と現代的アレンジ
最近ではお墓が遠方にある家庭も多く、お供えを現地で購入する・オンライン供養サービスを活用するといった方法も増えています。
大切なのは「形式に縛られること」ではなく、先祖を思う気持ちを形にすることです。
第5章:地域ごとの違い・豆知識
地域による時期の違い
お盆の時期は地域によって異なります。
多くの地域では8月13日〜16日に行われますが、東京や一部の地域では7月13日〜16日に行う「新盆(しんぼん/7月盆)」の習慣が残っています。
一方でお彼岸は全国的に春分・秋分の日に合わせて行われるため、時期の違いはほとんどありません。
行事内容の違い
- 北海道:気候の関係でお盆行事が簡素化されることも多い。
- 関西地方:盆踊りが盛んで、地域ごとに独自の踊りや音頭が伝わっている。
- 沖縄:「旧盆」にあたる時期に盛大に行われ、三線や舞踊を伴う賑やかな供養が特徴。
同じ「お盆」でも、地域性によって雰囲気が大きく異なるのは興味深いポイントです。
食べ物や供物の違い
お供えする食べ物にも地域色が見られます。
関東では落雁や果物、関西では精進料理やお菓子を重視する傾向があり、沖縄では豚肉料理や郷土料理を供える家庭もあります。
お彼岸の「ぼたもち・おはぎ」も、地域によって砂糖をまぶす・きなこで仕上げるなどアレンジが異なります。
ぼたもちとおはぎの違い
「ぼたもち」と「おはぎ」は実は同じ食べ物で、呼び名が季節によって変わるだけです。
- 春(彼岸):牡丹の花にちなんで「ぼたもち」と呼ぶ。
- 秋(彼岸):萩の花にちなんで「おはぎ」と呼ぶ。
餡の種類にも違いがあり、春は「こしあん」、秋は「つぶあん」を使うことが多いとされています。
これは、小豆の収穫時期が秋で皮が柔らかく食べやすいため、秋はつぶあん、春は冬を越して皮が固くなった小豆を漉してこしあんにした名残だといわれています。
※投稿の埋め込みが表示されない場合は、ページを再読み込みしてください。
だから
おはぎ じゃ無いっつ〜のぼたもち だってばよ
で、つぶあんでも無い
こうして
日本の文化は
無くなってゆくのであった…70年 作り続けているなら
ちゃんとしてくれぃっっっ#死別#お彼岸#ヤマザキ製パン #和菓子🍡#ぼたもち #牡丹餅 #おはぎ https://t.co/ZIIIREKurX— rescue@わたしの息子をかえして… (@rescue81636606) April 1, 2025
この方がおっしゃってるのが正論です。
海外との比較
日本だけでなく、アジア各国にも先祖供養の文化が存在します。
中国では「中元節」、韓国では「秋夕(チュソク)」、フィリピンでは「死者の日」があり、墓参りや供物を通じて先祖を敬う習慣が根付いています。
こうした海外の風習と比較すると、日本のお彼岸・お盆が静かで落ち着いた雰囲気を持つことがよく分かります。
豆知識:お彼岸と彼岸花
秋のお彼岸の頃に咲く花として有名なのが彼岸花(曼珠沙華)です。
毒性を持つことから「墓地に植えて動物を避ける」という実用的な役割がありました。
一方で、その鮮やかな赤色は先祖を導く花としても親しまれています。
第6章:現代のお彼岸・お盆の過ごし方
ライフスタイルの変化と行事の簡略化
核家族化や都市部への人口集中により、従来のように大人数でお墓参りをする家庭は少なくなってきました。
そのため最近では、短時間で済ませる「簡略化したお参り」や、オンライン供養サービスを利用するケースも増えています。
伝統を守りつつ、無理なく続けられる方法を選ぶことが大切です。
お供えやギフトの多様化
お供え物や手土産も現代的にアレンジされています。
定番の果物や和菓子に加えて、日持ちする焼き菓子やコーヒー、プリザーブドフラワーなども人気です。
近年は通販サイトやギフト専門店で「お彼岸・お盆ギフト特集」が組まれることも多く、遠方の親戚に直接届ける人も増えています。
人気のお供えギフト例
- 長期保存ができる焼き菓子セットやゼリーギフト
- 糖質オフやグルテンフリーなど健康志向のお菓子
- 季節のフルーツ盛り合わせ
- 線香やアロマキャンドルなど「香り系ギフト」
- 仏花に代わるプリザーブドフラワー
ギフトの選び方は「日持ちする・家族で分けやすい・処分に困らない」がポイントです。
SNSでの文化の広がり
近年では、InstagramやX(旧Twitter)に「#お盆 #お彼岸」の投稿が多数見られるようになりました。
ぼたもちやおはぎを手作りして写真をシェアしたり、精霊馬を子どもと一緒に作った様子を発信したりする人もいます。
※投稿の埋め込みが表示されない場合は、ページを再読み込みしてください。
みなさまおやっとさあ。
咲きだしました。
お彼岸は来週ですが…😄#お彼岸 #g7xmark3 #彼岸花 pic.twitter.com/vfEniJDHNS— kashin.m (@otsunoro) September 12, 2025
来年は電飾つけようかな(つけない)#精霊馬2025 pic.twitter.com/tsnBG8WX2O
— とりぱん💩₎₎₎💙💛 (@toripan2) August 16, 2025
来る時は速いキュウリ 帰りはナスでゆっくり!#精霊馬#精霊馬2025
(昨年の動画の再掲です) pic.twitter.com/iqJhO13bkA— ようたろう (@YTR_OKS) August 12, 2025
特にSNSでは「ユニーク精霊馬」が話題になることもあり、ペットボトルキャップやお菓子で作ったアレンジ例が拡散されるなど、供養と遊び心を両立した新しい文化も生まれています。
海外在住者の新しい供養スタイル
海外に暮らす日本人にとって、お盆やお彼岸を日本と同じように行うのは難しい場合があります。
そのため、現地の和食レストランでおはぎを用意したり、ビデオ通話を使って家族と一緒に墓参りをしたりするなど、海外ならではの供養スタイルが広がっています。
また、現地コミュニティで「盆踊り大会」を行う地域もあり、日本文化を共有するイベントとして定着している例もあります。
帰省・旅行との兼ね合い
お盆は長期休暇と重なるため、帰省ラッシュや旅行シーズンとしても有名です。
その一方で「実家に帰れないけれど気持ちだけは伝えたい」という人が増え、オンライン帰省やリモート法要といった新しい形も注目されています。
現代ならではの意義
お彼岸やお盆の形は時代とともに変化していますが、「ご先祖に感謝し、命のつながりを感じる」という本質は変わりません。
形式にとらわれすぎず、自分や家族に合ったスタイルで取り入れることが、現代における供養の形といえるでしょう。
第7章:お彼岸とお盆の違いまとめ&よくある質問
ここまで見てきたように、「お彼岸」と「お盆」はいずれもご先祖さまを思い、感謝を伝える行事ですが、起源や目的、過ごし方には明確な違いがあります。
まとめると、
- お彼岸:春と秋の年2回。自然を敬う意味が強く、仏教的な修行や供養と結びついている。
- お盆:夏に行う一度きりの行事。ご先祖の霊を自宅に迎え、家族や地域とともに過ごす文化的要素が大きい。
両者の違いを理解すると、それぞれの行事をより丁寧に迎えることができます。
最後に、よく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。
Q1:お彼岸とお盆の違いは一言で言うと?
お彼岸は「仏教的な修行・供養の節目」、お盆は「霊を迎えて共に過ごす行事」です。
時期も春秋と夏で異なります。
Q2:お彼岸とお盆、どちらもお墓参りは必要?
はい、どちらでもお墓参りを行うのが一般的です。
ただし、お彼岸は「仏壇やお墓を整える節目」としての意味合いが強く、お盆は「霊を迎えるための準備」としての意味があります。
Q3:おはぎとぼたもちの違いは?
材料は同じもち米+あんこですが、春は「ぼたもち(牡丹にちなむ)」、秋は「おはぎ(萩にちなむ)」と呼び方が変わります。
季節の花に合わせて名付けられたものです。
Q4:お盆は7月と8月どちらで行うの?
地域によって異なります。
東京などの都市部では「7月盆」、地方では「8月盆」が主流です。
最近では多くの人が帰省しやすい8月盆を選んでいます。
Q5:両方きちんと行わないと失礼になる?
いいえ、家庭や地域の風習に合わせれば大丈夫です。
大切なのは「ご先祖を思う気持ち」であり、形式よりも心が重視されます。
第8章:未来の供養スタイルと新しいお彼岸・お盆のかたち
社会の変化やライフスタイルの多様化に伴い、お彼岸やお盆の過ごし方も少しずつ変わりつつあります。
近年では「帰省できない」「お墓が遠い」といった事情から、従来の形を工夫した新しい供養スタイルが広がっています。
1. オンライン墓参り・リモート供養
コロナ禍をきっかけに普及したのが「オンライン墓参り」です。
お寺や霊園が墓前をライブ配信し、遠方に住む家族が画面越しに手を合わせる仕組み。
実際に現地へ行けなくても、ご先祖を思う時間を持てることから利用者が増えています。
2. デジタル位牌やアプリでの供養
近年は「デジタル位牌」や「供養アプリ」も登場。
スマートフォンやタブレットから日々の祈りを捧げられる仕組みで、若い世代を中心に注目されています。
写真や思い出を記録し、家族でシェアできる機能もあり、形にとらわれない新しい供養文化が根付き始めています。
3. 海外在住者や多様なライフスタイルに対応
海外に住む日本人にとっても、オンライン供養やアプリは心強い存在です。
また「仕事で帰省が難しい」「核家族で伝統行事に参加しづらい」といった人々にとっても、柔軟に取り入れられるスタイルが広がっています。
4. サステナブルな供養のあり方
近年は環境意識の高まりから、エコな供養方法も注目されています。
たとえば、使い捨てではなく再利用可能な供花や、お線香に代わるLEDキャンドルなど。
自然や環境を大切にする姿勢は、お彼岸・お盆の「自然を敬う心」にも通じています。
このように、現代社会では「伝統を守りつつ、新しい形でご先祖を敬う」スタイルが多様化しています。
お彼岸やお盆の本質は変わらず、「ご先祖を思い、感謝する心」こそが最も大切だといえるでしょう。
第9章:まとめ|違いを知って、より豊かな供養を
本記事では「お彼岸」と「お盆」の違いについて、意味・由来・お参り・食べ物・現代の過ごし方まで解説しました。
いずれもご先祖を敬う心が根底にあり、形式や地域の違いよりも、気持ちを込めて行うことが大切です。
現代の暮らしに合わせた供養
「忙しくて帰省できない」「お墓が遠い」といった事情を抱える方も少なくありません。
そんなときは、
- 自宅で手を合わせる
- オンラインで参加する
- 日常の中でご先祖を思い出す
など、自分に合った方法で十分です。
形式にとらわれず、できる範囲で供養することが、ご先祖への誠実な思いにつながります。
読者へのメッセージ
お彼岸とお盆は、どちらも「過去と現在をつなぐ大切な時間」です。
違いを理解したうえで迎えることで、ご先祖への感謝がより深まり、心の安らぎや家族の絆も強まるでしょう。
ぜひ今年は、あなたのライフスタイルに合った形でお彼岸・お盆を過ごしてみてください。
その一歩が、家族や自分自身の心を豊かにするはずです。
関連リンク
- 【2025年完全版】七夕の由来・風習・イベントまとめ|願い事の意味や織姫と彦星の物語まで
- 十五夜(中秋の名月)2025年はいつ?由来・お団子・全国イベントまとめ
- お盆帰省の手土産おすすめ10選|お供えにも喜ばれる“日持ち&センス良し”ギフトを厳選【2025】
- 十三夜・十日夜とは?2025年の日付・意味・十五夜との違いを解説【保存版】
- 七五三完全ガイド|いつ・着物・写真・親の服装・お祝いマナーまで丸わかり!
- 【12/10まで最大11,000円OFF】人気おせち通販2026|早割ラストチャンス&在庫情報まとめ
- 勤労感謝の日2025|いつ・由来・意味・手作りプレゼント完全ガイド
- 【2026年版】楽天「食品福袋」おすすめトップ10&徹底比較|共働き・子育て家庭向け1推しはコレ!
- 2025年の最強開運日「12月21日」は天赦日×一粒万倍日!やるべきこと・避けること完全ガイド