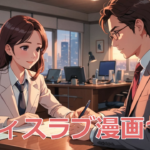気温が下がる冬、肌のカサつきや粉ふき、つっぱり感に悩む人が急増します。
とくに冷たい風や暖房の影響で、肌の水分と皮脂のバランスが崩れ、乾燥トラブルが悪化しやすい季節です。
「化粧のノリが悪い」
「顔がかゆい」
「保湿してもすぐ乾く」
…。
そんな悩みを解決するために、正しい乾燥肌対策を知っておくことが大切です。
本記事では、乾燥の原因からスキンケア・生活習慣・食べ物までを徹底解説。
今日からできる小さな見直しで、「うるおいのある冬肌」を取り戻しましょう。
・乾燥肌の原因と見直すべき生活習慣
・スキンケアの正しい順番とおすすめ成分
・乾燥を防ぐ食べ物・飲み物・インナーケア
・乾燥肌を守る最新スキンケアの考え方
・今日からできる簡単な乾燥対策チェックリスト
この記事の目次です
第1章|冬に肌が乾燥する原因とは?
冬になると、顔のつっぱりや粉ふき、メイクのノリが悪くなるなど、乾燥肌のトラブルが増えます。
一見、外気の冷たさだけが原因のように思われがちですが、実際にはいくつもの要因が重なって乾燥を引き起こしています。
ここでは、冬の乾燥肌を悪化させる主な原因を3つの視点から詳しく見ていきましょう。
気温・湿度の低下によるうるおい不足
冬の空気は非常に乾燥しており、湿度が40%を下回る日も少なくありません。
肌の表面では、空気中の水分が少なくなることで角質層に含まれる水分が蒸発しやすくなります。
さらに冷たい風が顔に直接あたることで、皮膚の温度が下がり、血行が悪化。
その結果、皮脂の分泌量が減少して、肌を守る天然のバリア膜が薄くなってしまいます。
気象庁のデータでも、12月〜2月は全国的に湿度が最も低い季節とされます。
つまり、私たちの肌は「外気による乾燥」と「屋内の暖房乾燥」の両方にさらされている状態なのです。
暖房の使用による室内乾燥
エアコンやファンヒーターなどの暖房機器は、空気中の水分を奪いやすく、室内の湿度を一気に下げます。
暖房を長時間使用する冬のオフィスや寝室では、湿度が20〜30%まで下がることもあります。
このような状態では、どれだけスキンケアをしても肌の水分は逃げていってしまうのです。
また、エアコンの風が直接顔や首まわりにあたると、皮脂膜が崩れやすくなり、肌表面がかさつきやすく…。
加湿器を使わない部屋や、風向きを調整していない環境では、肌が慢性的に乾燥状態に陥っている可能性もあります。
肌のバリア機能が低下している
肌の一番外側にある「角質層」は、わずか0.02mmほどの薄い膜で構成されています。
この層には「セラミド」「天然保湿因子(NMF)」「皮脂膜」という3つのうるおい要素が存在し、外からの刺激や水分蒸発を防いでいます。
しかし、洗顔のしすぎ・摩擦・紫外線・加齢などによってこのバリアが壊れると、内部の水分がどんどん失われてしまいます。
特に冬はターンオーバーが乱れやすく、古い角質が肌表面に残ることで、ごわつきやくすみが発生。
バリア機能が低下した状態では、保湿をしても十分に浸透せず、「塗っても乾く」状態に陥ることも少なくありません。
生活習慣の乱れも乾燥を悪化させる
睡眠不足やストレス、偏った食生活も乾燥肌を悪化させる大きな要因です。
夜更かしが続くと、肌の再生を促す「成長ホルモン」の分泌が減り、ターンオーバーが遅れます。
また、糖分・脂質の摂りすぎや野菜不足も、皮脂バランスや血行を乱す原因になります。
乾燥を感じやすい時期こそ、スキンケアだけでなく、「睡眠・食事・ストレスケア」という生活面の見直しが欠かせません。
外から塗るケアと内側のケアを両立することで、肌の回復力を高めることができます。
加齢による皮脂・セラミドの減少
年齢を重ねるごとに、皮脂やセラミドの分泌量は自然と減っていきます。
30代を過ぎると皮脂量が20代の約70%に、40代では約半分にまで低下するという研究もあります。
特に頬や目のまわりは皮脂腺が少なく、もともと乾燥しやすい部位です。
さらに女性の場合、ホルモンバランスの変化も影響します。
生理周期・出産・更年期などの時期には、エストロゲンの減少により水分保持力が低下。
このため、以前よりスキンケアを頑張っているのに「なぜか乾く」という状態が起こるのです。
マスク・花粉・空気汚染などの外的刺激

近年はマスク生活や花粉・PM2.5の影響で、肌が刺激を受けやすくなっています。
マスクの摩擦や蒸れによって角質層が傷つき、バリア機能が低下すると、外部刺激に反応しやすい「ゆらぎ肌」状態に。
そのまま放置すると、赤みやヒリつきを伴う乾燥炎症に発展することもあります。
こうした外的刺激から肌を守るには、保湿でバリアを再構築しつつ、刺激の少ない化粧品を選ぶことが重要です。
とくにアルコールフリー・無香料・セラミド配合のスキンケアは、乾燥肌の人にとって心強い味方になります。
まとめ|乾燥肌の原因は「環境×習慣×バリア機能」
冬の乾燥肌は、気温・湿度の低下といった外的要因だけでなく、暖房や生活リズムの乱れ、バリア機能の低下など、複数の要素が絡み合って起こります。
まずは自分の生活環境を見直し、肌が本来持つ保湿力を取り戻すことが第一歩!
次の章では、乾燥を防ぐための「基本のスキンケアステップ」を詳しく紹介します。
第2章|乾燥肌を守る!基本のスキンケアステップ
乾燥肌を改善するには、「高価な化粧品を使うこと」よりも、正しい順番とやさしい手入れを続けることが大切です。
肌に必要な水分を補い、それを逃さない仕組みを作る。
それが乾燥対策の基本です。
ここでは、朝と夜のケア方法を中心に、乾燥肌を守る正しいスキンケアの流れを紹介します。
洗顔は「落としすぎない」を意識する
まず見直したいのが洗顔の仕方です。
強い洗浄力の洗顔料を使うと、必要な皮脂まで落としてしまい、かえって乾燥を招きます。
乾燥肌の人は、朝も夜も「泡で包み込むようにやさしく洗う」ことを意識しましょう。
おすすめは、低刺激のアミノ酸系洗顔料です。
熱いお湯は皮脂を奪うため、32〜34℃のぬるま湯で洗うのが理想。
タオルはこすらず、清潔なものを軽く押し当てて水分を拭き取ります。
・洗顔は「泡で洗う」が基本
・お湯はぬるま湯を使用
・摩擦を避けてやさしく拭き取る
化粧水で「素早く」水分を補給
洗顔後の肌は水分が急速に失われるため、1分以内の保湿が理想です。
洗顔を終えたら、できるだけ早く化粧水を手に取り、顔全体にやさしくなじませましょう。
コットンを使う場合は、摩擦を避けるためにたっぷり含ませて使用します。
化粧水を選ぶときは、「ヒアルロン酸」「アミノ酸」「グリセリン」などの保湿成分が配合されたものがおすすめ。
刺激が気になる人は、アルコールフリー・無香料タイプを選ぶと安心です。
美容液でうるおいを閉じ込める
化粧水で補った水分を、次は美容液でしっかり閉じ込めます。
特に乾燥がひどい部分には、指先で軽く重ねづけすると効果的です。
美容液は悩みに合わせて選ぶのが基本ですが、乾燥肌には「セラミド」「ナイアシンアミド」「コラーゲン」配合のものが最適です。
中でも「セラミド」は角質層の水分保持に欠かせない成分。
ヒト型セラミド配合の美容液は刺激が少なく、敏感な乾燥肌にもおすすめです。
乳液・クリームで水分を逃さない

スキンケアの仕上げは、乳液やクリームで肌表面に油分の膜を作ること。
これが水分の蒸発を防ぐフタの役割を果たします。
化粧水や美容液だけではうるおいが逃げてしまうため、仕上げのステップを省かないことが大切です。
乾燥しやすい頬や口もとを中心に、手のひらで包み込むように塗布します。
クリームを少し温めてからなじませると、浸透力が上がり、ベタつきにくくなります。
乾燥肌の人は「水分+油分」の両方が不足しがち。
乳液やクリームでうるおいを守ることが、バリア機能を整える第一歩です。
朝と夜でケアを使い分ける
朝と夜では肌の状態も目的も違います。
朝は外気や紫外線から守る準備、夜はダメージを回復させる時間。
それぞれの特徴を理解してケアを分けると、うるおいが長持ちします。
朝のケア
朝は洗顔後に化粧水で保湿し、軽めのクリームでフタをします。
その上からUVケアを重ねて、外的刺激から肌をガード。
化粧下地を使う場合は、保湿成分入りのタイプを選ぶと乾燥崩れを防げます。
夜のケア
夜はメイクや汚れを丁寧に落としたあと、化粧水→美容液→クリームの順で保湿。
就寝中は肌の再生が活発になるため、この時間にしっかり栄養を与えましょう。
加湿器や濡れタオルを使って湿度を保つのも効果的です。
週1〜2回のスペシャルケアも効果的
通常の保湿に加えて、週に1〜2回はパックやオイルを取り入れると良し。
シートマスクは10〜15分を目安に外し、クリームで水分を閉じ込めます。
フェイスオイルは、化粧水の後に1〜2滴をなじませるだけで保湿力がアップ。
・お風呂上がりの血行が良いとき
・季節の変わり目で肌がゆらぐとき
・日焼けや乾燥が気になる日の夜
乾燥肌の人が避けたいNG習慣
- 熱いお湯で洗顔する
- タオルでゴシゴシこする
- アルコール入り化粧水を使う
- 乳液・クリームを省略する
- 日中の乾燥を放置する
どれも肌のバリア機能を弱らせてしまう行動です。
「保湿しているのに乾く」と感じる人は、まずこれらの習慣を見直しましょう。
小さな工夫で、肌の調子はぐっと変わりますよ。
まとめ|「正しい順番とやさしい継続」が乾燥改善の鍵
乾燥肌を整える近道は、高価なコスメではなく正しい順番と継続です。
洗顔→化粧水→美容液→クリームという基本を守り、摩擦を避けながら丁寧にケアを続けましょう。
毎日の積み重ねが、季節に負けないうるおい肌を育てます。
次の章では、外気・暖房・湿度など「環境から守る乾燥対策」を紹介します。
第3章|加湿器なしでもできる!乾燥を防ぐ環境づくり
冬になると、部屋の湿度が一気に下がり、肌だけでなく喉や髪も乾燥しがちになります。
加湿器を使うのが理想ですが、電気代や設置スペースの問題で使えない人も多いでしょう。
ここでは、「加湿器がなくてもできる乾燥対策」を中心に、部屋の湿度を保つ工夫を紹介します。
最適な湿度は40〜60%をキープ
まず意識したいのが、部屋の湿度を40〜60%の範囲で保つこと。
湿度が30%を下回ると、肌の水分は空気中にどんどん逃げてしまいます。
逆に60%を超えるとカビやダニの繁殖リスクが高まるため、適度なバランスが大切です。
湿度計を1つ置くだけでも、日々の環境管理がぐっとしやすくなります。
1000円前後の簡易タイプでも十分なので、まずは「見える化」から始めてみましょう。
・理想の湿度は40〜60%
・湿度が下がると肌・喉・髪に影響
・まずは湿度計でチェックを習慣に
タオル・洗濯物を「自然加湿器」にする

「乾燥対策 部屋にタオル」という検索が多いように、濡れタオルを部屋に掛けるのは手軽で効果的な方法です。
洗面器やバケツに水を張り、そこにタオルを垂らしておくと、自然に水分が蒸発して加湿されます。
寝室やリビングなど、人が長く過ごす場所に1〜2枚吊るしておくだけで湿度が数%上がりますよ。
また、夜の室内干しもおすすめ。
洗濯物から出る水分がゆっくりと部屋全体に広がるため、乾燥を防ぎながら朝にはちょうど良く乾きます。
ただし、換気をしないと結露やカビの原因になるので、日中に軽く窓を開けて空気を入れ替えましょう。
・濡れタオルを椅子やドアノブに掛ける
・洗濯物を夜干しして「自然加湿」
・洗面器にお湯を張って枕元に置く
加湿器以外でもできる「湿度アップ術」
加湿器を使わずに湿度を上げるには、生活動作を少し工夫するだけでOKです。
たとえばお湯を沸かす・お風呂のドアを少し開ける・観葉植物を置くなど、日常の中にうるおいを増やす方法はたくさんあります。
- 鍋料理・スープを作る:調理中の蒸気で部屋の湿度を自然に上げる
- お風呂上がりにドアを開放:浴室の蒸気を利用して加湿
- 観葉植物を置く:葉から水分が蒸発し、空気のうるおいを保つ
- 濡れマスクを活用:喉や鼻を乾燥から守る
特に観葉植物は、見た目にも癒やし効果があり、乾燥対策としても優秀です。
サンスベリアやポトスなどは蒸散量が多く、空気清浄効果も期待できます。
暖房の使い方にも注意する
冬の乾燥を悪化させる大きな要因が暖房の使い方です。
エアコンの風が直接肌や顔にあたると、水分がどんどん奪われます。
風向きを上に設定し、タイマーや弱運転を活用して過剰な乾燥を防ぎましょう。
石油ストーブやファンヒーターを使う場合は、上にやかんを置いてお湯を温めるだけでも効果的。
お湯が沸騰することで蒸気が発生し、自然に湿度を上げてくれます。
暖房を使うと湿度が10〜20%下がるといわれています。
風の向きを調整するだけでも、乾燥を軽減することが可能です。
家具・インテリアの配置も意外と重要
部屋のレイアウトも、乾燥の感じ方に影響します。
エアコンの風が直接あたる位置にベッドやソファを置くと、肌や髪が乾きやすくなります。
風の通り道を避ける、壁際に家具を寄せすぎないなど、空気の流れを調整するのもポイントです。
また、床にラグやカーテンを敷くと、冷気の侵入を防ぎ、室内温度が安定します。
結果として暖房の設定温度を下げられ、湿度の低下を抑えることにもつながります。
喉・肌を守るナイトケア環境を整える

就寝中の乾燥は、肌荒れや喉の痛みの原因になります。
寝る前に水を一口飲む、マスクをつける、濡れタオルを枕元に置くなど、小さな工夫でかなり違いが出ます。
💤 マスク就寝のメリットと注意点
就寝時にマスクを着けると、喉や鼻の乾燥を防げるため、朝の喉の痛み対策には効果的です。
特に冬場やエアコンを使う季節には、口呼吸による水分蒸発を軽減できます。
息苦しさを感じたり、睡眠の質が下がる場合もあるため、無理に続けるのはおすすめできません。
快適に使うためのコツ
| コツ | 内容 |
|---|---|
| 素材 | シルクやガーゼなど、通気性がよく肌にやさしい素材を選ぶ |
| フィット感 | 耳が痛くならないゆるめの設計を |
| 保湿補助 | ワセリンやナイトパックを軽く塗ってから着用すると乾燥防止効果UP |
マスクが苦手な人は?
マスクの着用が合わない場合は、濡れタオルやペットボトル加湿器を枕元に置くだけでも十分な効果があります。
また、アロマディフューザーを活用すれば、リラックスしながらうるおいを保てます。
・寝る前に水分補給をする
・濡れタオルやお湯の入ったカップを枕元に置く
・喉を守るために就寝用マスクを活用
・起床後はすぐに換気して空気をリセット
まとめ|暮らし方を変えるだけでうるおいは守れる
冬の乾燥は、加湿器だけが解決策ではありません。
タオルや洗濯物、お風呂の蒸気など、日常の中でできる工夫がたくさんあります。
小さな積み重ねで、部屋の湿度も肌のうるおいも守ることができます。
次の章では、体の内側からうるおいを支える「食べ物・飲み物・インナーケア」を紹介します。
第4章|内側からうるおう!食べ物・飲み物・インナーケアで乾燥を防ぐ
肌の乾燥は、外からのケアだけでは完全に防ぎきれません。
体の中が乾いていれば、どんなに保湿してもすぐに水分が逃げてしまいます。
ここでは、食べ物・飲み物・サプリなど、内側からうるおいを支える乾燥対策を紹介します。
うるおいを支える栄養素とは?
まず意識したいのが、肌のバリア機能を整える栄養素です。
乾燥肌を防ぐには、以下の3つが基本の柱になります。
| 栄養素 | 主な働き | 多く含む食材 |
|---|---|---|
| ビタミンA・E | 皮膚の再生を助け、血行を促す | にんじん、かぼちゃ、アーモンド、アボカド |
| オメガ3脂肪酸 | 細胞膜の水分保持を助け、炎症を防ぐ | サーモン、くるみ、えごま油、チアシード |
| たんぱく質 | コラーゲンや角質のもとをつくる | 卵、豆腐、鶏むね肉、納豆 |
・肌の水分保持には「ビタミン+油分+たんぱく質」が必須
・偏った食事は乾燥を悪化させる
・毎日の食卓に色の濃い野菜と良質な油を取り入れる
乾燥肌におすすめの食べ物10選
次の食材は、冬の乾燥対策として特におすすめです。
「乾燥対策 食べ物」として検索される代表的な成分を中心にまとめました。
- アボカド:良質な脂質とビタミンEで肌の柔らかさを保つ
- 鮭:アスタキサンチンが肌の酸化を防ぐ
- 卵:必須アミノ酸がバリア機能をサポート
- 納豆:ポリグルタミン酸で保湿力アップ
- にんじん:βカロテンが肌のターンオーバーを促す
- ブロッコリー:ビタミンCがコラーゲン生成をサポート
- オリーブオイル:オレイン酸でしっとり感をキープ
- くるみ:オメガ3脂肪酸が炎症を抑える
- 豆乳:イソフラボンで肌のハリを保つ
- キウイ:水分とビタミンCを一度に補える
どれもコンビニやスーパーで簡単に手に入るものばかり。
特別な食事制限をしなくても、日々の食卓で意識するだけで違いが出るんですよ。
飲み物でもうるおいチャージ
「乾燥対策 飲み物」で人気なのが、体の中から水分バランスを整える温かいドリンクです。
冷たい水やお茶ばかり飲むと体を冷やしてしまい、血行が悪くなります。
冬はできるだけ常温〜ホットの飲み物を選びましょう。
- 白湯:体を温めながら代謝を促進。朝の一杯がおすすめ
- ルイボスティー:抗酸化作用で肌ストレスを軽減
- ハトムギ茶:余分な老廃物を排出し、透明感をアップ
- 豆乳ココア:イソフラボンとポリフェノールのW効果
- 生姜湯:血流を促して冷え・乾燥をWケア
カフェインを多く含むコーヒーや緑茶は、利尿作用で水分が失われやすいため、飲みすぎには注意しましょう。
1日1〜2杯を目安に抑えるのが理想です。
肌の水分量は「飲んだ水の量」ではなく、「体に吸収された水分量」で決まります。
一度に大量ではなく、こまめに少しずつ飲むのがうるおい肌への近道です。
サプリやインナーケアで不足を補う
忙しい日常では、毎日バランスよく食事を取るのが難しい場合もあります。
そんなときは、サプリメントやインナーケア商品を活用してみましょう。
「乾燥対策 サプリ」で人気が高いのは、次のような成分です。
- セラミド:肌のバリア機能を内側からサポート
- ヒアルロン酸:水分保持能力を高める
- コラーゲンペプチド:弾力とハリを維持
- オメガ3(DHA・EPA):炎症を抑えて肌荒れを防ぐ
ドリンクタイプやゼリータイプも多く、無理なく取り入れられるのが魅力。
特に冬場は肌の乾燥だけでなく、髪や唇の荒れにも効果を感じやすい人が多いです。
・医薬品よりも「機能性表示食品」タイプが安心
・毎日続けやすい味・価格を選ぶ
・複数成分配合よりも、まずは1成分から試す
まとめ|食事もケアの一部と考える
乾燥を防ぐには、スキンケアと同じくらい「食習慣」が重要です。
体の内側が整うと、肌は自然にうるおいを取り戻します。
ビタミン・良質な脂質・たんぱく質を意識しながら、温かい飲み物で体を冷やさない工夫を。
次の章では、「外出時・職場でできる乾燥対策」を紹介します。
第5章|外出先でも乾かない!オフィス・マスク内の乾燥対策
冬の乾燥は自宅だけでなく、職場や外出先でも深刻です。
暖房の効いたオフィス、冷たい外気、長時間のマスク着用…。
肌や唇がパサつくのを感じる人は多いのではないでしょうか?
ここでは、「外出時」「職場」「マスク内」の3シーン別にできる乾燥対策を紹介します。
オフィスの乾燥は「デスクまわり」で防ぐ
エアコンが効いたオフィスでは、湿度が30%を切ることもあります。
加湿器を設置できない職場でも、デスク周りにちょっとした工夫をするだけで乾燥を軽減できます。
- マグカップにお湯を入れて置く:蒸気で自然に加湿できる
- 卓上加湿器を活用:USBタイプなら静音・コンパクトで便利
- 観葉植物を置く:空気をやわらげ、目の乾きも緩和
- 霧吹きスプレーを常備:乾燥を感じたら空間に軽くミストを
また、パソコンのディスプレイから出る熱やブルーライトも肌の乾燥を促します。
画面との距離を40cm以上空け、定期的にまばたきをして目の乾きを防ぎましょう。
・お湯入りマグカップを置く
・加湿器の代わりに濡れタオルをかける
・保湿ミストやリップを手元に常備
・定期的に伸びをして血流を促す
外出時は「持ち歩き保湿アイテム」を味方に

冷たい風や日中の気温差は、肌の水分を奪う大きな原因です。
外出時は、持ち歩きできる保湿アイテムを上手に使いましょう。
- ミスト化粧水:メイクの上からでも使える細かいミストタイプがおすすめ
- スティックバーム:唇・目元・頬など、部分ケアに便利
- ハンドクリーム:手洗い後すぐに塗ることで荒れを防ぐ
- 保湿リップ:マスクの下でもベタつきにくいタイプを選ぶ
バッグの中には、これらをコンパクトにまとめて「ポーチ1つ」に。
移動中や待ち時間のちょっとしたタイミングでケアできるようにしておくと、乾燥がひどくなる前に対処できます。
・ミスト化粧水
・スティックバーム
・リップクリーム
→ これさえあれば「外出中の乾燥トラブル」はほぼ防げます。
マスク内の乾燥にも注意
意外と見落とされがちなのが、マスク内の乾燥です。
長時間のマスク着用は呼吸による蒸発と乾燥を繰り返す「ミニサウナ状態」。
肌表面の水分バランスが乱れ、かえって荒れやすくなります。
対策としては、マスクをつける前に保湿ケアをしておくことが重要。
化粧水と乳液をなじませたあと、保湿バームやワセリンを薄く塗っておくと、蒸発による乾燥を防げます。
また、肌荒れを感じる場合は「不織布+布マスクの重ね使い」も効果的。
布マスクがクッションになり、摩擦ダメージを軽減します。
・呼気による湿気と蒸発の繰り返し
・素材による摩擦刺激
・保湿不足のまま長時間着用
外気・紫外線にも要注意
冬でも油断できないのが紫外線です。
肌の乾燥を悪化させる「光老化」の原因にもなるため、UVケアは年間を通して必須です。
特に頬や鼻の頭など、日差しを受けやすい部分は重点的にケアしましょう。
- SPF20〜30程度の保湿系UV下地を使用
- 外出時間が長い日はパウダータイプでこまめに塗り直し
- 首や手の甲にもUVケアを忘れずに
UVケアをすることで、乾燥・シミ・くすみなどの肌トラブルをトータルで防ぐことができます。
外出後の「アフターケア」も大切
帰宅後は、冷たい外気やマスク摩擦でストレスを受けた肌をリセットしましょう。
まずぬるま湯でやさしく洗顔し、すぐに化粧水・美容液・クリームで保湿を。
乾燥を感じたら、シートマスクを短時間で取り入れるのも効果的です。
また、リップやハンドケアも同時に行うと、翌朝のコンディションが格段に違います。
夜のケアを「補修タイム」と考えて、肌をしっかり休ませましょう。
・帰宅後すぐにメイク・汚れをオフ
・ぬるま湯洗顔+保湿を徹底
・唇・手先・頬を重点的にケア
・寝る前の水分補給も忘れずに
この章のまとめ|「持ち歩く保湿習慣」が冬の肌を守る
外出時やオフィスでの乾燥対策は、特別な道具がなくても十分可能です。
マスク前の保湿、デスクでの工夫、ポーチに入れるミニアイテム。
どれも小さなことですが、日々続けることで大きな違いになります。
次の章では、冬の乾燥を防ぐ「生活習慣と睡眠・入浴の整え方」を紹介します。
第6章|生活習慣と睡眠・入浴で整える「乾燥しない体づくり」
肌の乾燥はスキンケアや食事だけでなく、生活リズムの乱れや睡眠不足、入浴方法にも大きく関係しています。
「乾燥対策 生活習慣」「乾燥対策 睡眠」といった検索が多いのも、根本的な改善を求める人が増えている証拠です。
ここでは、日々の暮らしの中でうるおいを守るコツをご紹介。
睡眠で「肌の修復時間」を確保する
肌は眠っている間に再生・修復されます。
特に午後10時〜午前2時のゴールデンタイムは成長ホルモンの分泌が活発になり、乾燥やダメージの回復が進みます。
寝不足が続くとターンオーバーが乱れ、肌のバリア機能が低下。結果として乾燥が進んでしまいます。
寝る前1〜2時間はスマホやPCを控え、部屋を暗めにして副交感神経を優位に。
また、枕元に濡れタオルをかけて湿度を保つのもおすすめです。
・就寝前のスマホは30分前にOFF
・室温は18〜20℃、湿度は50〜60%が理想
・カフェインは夕方以降控える
・入浴後1時間以内に就寝する
入浴で血流を促し、乾燥しにくい体へ

冬の乾燥対策で意外と重要なのが入浴法です。
熱すぎるお湯は皮脂を奪うため、38〜40℃のぬるめのお湯に15分ほど浸かるのが理想的。
血行が良くなることで、肌の新陳代謝や水分保持力が高まります。
入浴剤を選ぶ際は「セラミド」「ヒアルロン酸」「ミルク成分」など保湿系のものを選びましょう。
香りのリラックス効果もあり、睡眠の質向上にもつながります。
シャワー派の人も、最後に手足を温める「足湯・手湯」を取り入れるだけで体の巡りが改善されます。
・お湯の温度は40℃以下
・タオルで強くこすらず「押し拭き」
・入浴後は5分以内に保湿
・保湿入浴剤を活用して“ながらケア”
ストレスと乾燥の関係にも注目
ストレスが続くと、ホルモンバランスが乱れ、肌のターンオーバーが遅れます。
交感神経が優位になると血流が悪くなり、肌細胞に十分な栄養が届かなくなるのです。
これが「保湿しても乾く」状態を引き起こす原因のひとつ。
ストレスを感じたときは、深呼吸や軽いストレッチで体をゆるめましょう。
好きな音楽を聴く、アロマを焚くなどのリラックス法も効果的です。
・5分の深呼吸タイムを設ける
・夜は温かいハーブティーで体を温める
・香り(ラベンダー・ベルガモットなど)で自律神経を整える
・休日はスマホを「オフデー」にして心も休ませる
運動と水分補給で代謝を上げる
乾燥を防ぐには、体全体の血流を良くすることも欠かせません。
軽い運動で代謝を上げると、肌細胞に酸素や栄養が届きやすくなります。
ウォーキングやストレッチ、ヨガなど無理なく続けられるものがおすすめです。
運動中や日中の水分補給も忘れずに。
目安は1日あたり1.2〜1.5リットルをこまめに飲むこと。
冷たい水よりも常温の水や白湯を選ぶと、内臓を冷やさず代謝アップにつながります。
この章のまとめ|生活リズムを整えることが最大の保湿ケア
乾燥肌を根本から改善するには、毎日の生活習慣を整えることがいちばんの近道です。
十分な睡眠、適度な運動、リラックス時間、そして正しい入浴。
どれも特別なことではありませんが、続けることで確実に肌のうるおいが変わります。
次の章では、乾燥肌さんに人気の「保湿力の高いスキンケアブランド」を紹介します。
第7章|乾燥肌に人気のスキンケア「ORBIS(オルビス)ディフェンセラ」
「塗る」だけでは物足りない人に。
オルビスが10年かけて研究開発した、新発想のスキンケアするトクホ。
今、オルビスで最も注目されているインナーケア商品です。
7-1. ディフェンセラが支持される理由
大人女性の2人に1人が悩むといわれる「肌の乾燥」。
その根本ケアとして人気なのが、飲むスキンケア「ディフェンセラ」です。
乾燥が気になる方、背中やすねまでカサつきやすい方に使いやすく、外側の保湿だけでは補いきれない部分のケアに向いています。
7-2. ひみつは「高純度セラミドの3段階バリア」
ディフェンセラに含まれる高純度のグルコシルセラミドが、肌に3段階のうるおいバリアを形成し、水分の蒸発を防ぎます。
| 特徴 | 肌の水分保持をサポートし、乾燥しにくい状態へ整える |
| 役割 | うるおいバリアを守り、外的刺激から肌を保護 |
高純度セラミドとは?
良質な玄米1トンからわずか1〜2gしかとれない希少なセラミドだけを採取し、さらに不純物を除いたものが「高純度セラミド」です。
食品に含まれる一般的なセラミドより体内へ吸収されやすく、うるおい実感につながりやすい点が特徴です。
7-3. 「飲むケア」にこだわる3つの理由
- 顔だけでなく、背中・ひじ・足先・すねなど全身にアプローチ
- 化粧水のように何度も塗り直す必要がなく、手間がかからない
- 時間も場所も選ばない。1日1包、15秒で続けられる
7-4. 実際に届いている喜びの声
「ひじの乾燥が気にならなくなりました!」(20代女性)
「期待通りの実感!」(30代女性)
乾燥ケアの新習慣として、多くのユーザーが継続しています。外側と内側を同時にケアしたい方にぴったりの商品です。
7-5. オルビス ディフェンセラのSNSでの声
※投稿の埋め込みが表示されない場合は、ページを再読み込みしてください。
全身乾燥する人は全員「オルビス」のディフェンセラを飲んだ方がいい。駄菓子のような美味しい粉を1日1包飲むだけで全身うるうる。カサカサもしっとり吸いつく手触り。かゆいスネもゴワゴワの手も顔も爆速で潤う。パラダイムシフトが起こる。あれこれ塗るより飲んだ方がはやい。わたしのビフォアフは
— すろーむ (@ssurrom777) December 7, 2025
年中乾燥肌だったけど、オルビスの飲むセラミド(ディフェンセラ)飲みだしてから全身潤ってる〜👶🏻🫧味は3種類で水なしで飲めるくらい美味しいです◎
皆さんがされてる乾燥対策なにかあれば教えてください🩶 pic.twitter.com/wWJaneMkuO
— momo (@__momobiyou) January 26, 2025
ケアセラいいかもしれんദ്ദി ˃ ᵕ ˂ )
乾燥感じにくい気が!
とりあえず飲みきってみよ〜❤︎美味しいから苦じゃない(*´༥`*)♡
#オルビス #ディフェンセラ
#飲むセラミド #インナーケア
#スキンケア #乾燥肌 pic.twitter.com/lDHVQOn2qe— こすお (@c0sme_0ta) February 12, 2025
オルビスのディフェンセラ、顔はクリームとかたくさん塗っちゃうから変化が分かりにくいんだけど、爪周りのガサガサなんかは明らかに改善してくるからほんと好き🙆♀️他のに浮気してたけど結局戻ってきた! pic.twitter.com/NDO8Xwkzjp
— ch千花🪿 (@ve_cosme09) March 29, 2025
7-6. オルビス ディフェンセラをチェック
公式ページでは、ディフェンセラの特徴や飲み方、続けやすいフレーバーなどを詳しく確認できます。
この章のまとめ|冬こそ「外側×内側のW保湿」を
乾燥肌は、放っておくとバリア機能が弱まり、外的刺激を受けやすくなります。
そんなときこそ、外側の保湿ケアに加えて、内側からのうるおいケアが重要です。
オルビスのディフェンセラは、毎日1包で続けられる手軽なインナーケアとして人気。
「塗るケアだけでは追いつかない」と感じる方にぴったりの乾燥対策です。
次の章では、ここまでの内容を整理し、今日から実践できる「乾燥対策チェックリスト」を紹介します。
第8章|今日から実践できる!乾燥対策チェックリスト
ここまで、乾燥肌の原因から部屋の乾燥対策、スキンケアまでを解説してきました。
最後に、毎日の生活の中で実践できる「乾燥対策チェックリスト」を紹介します。
今日からできる小さな工夫を積み重ねて、肌も喉も心地よく保ちましょう。
【1】部屋・環境の乾燥対策
| 対策内容 | ポイント |
|---|---|
| 加湿器を使う | 湿度は40〜60%を目安に。 加熱式は速効性が高く冬におすすめ。 |
| 濡れタオルや洗濯物を室内干し | 加湿器がないときの代用に最適。寝室にも効果的。 |
| 暖房の風を直接当てない | エアコンの風は乾燥の原因。 風向きを上向きに設定。 |
| 観葉植物を置く | 葉からの蒸散で自然加湿。 インテリアにも癒し効果にも良し。 |
| やかん・コップに水を置く | 気化で湿度を保つ昔ながらの方法。 冬の寝室にもおすすめ。 |
【2】スキンケア習慣の見直し
乾燥を防ぐには、化粧水やクリームの使い方も重要です。
「量」「タイミング」「重ね方」を意識するだけで、保湿力が格段に変わります。
- 洗顔はぬるま湯で10〜15秒以内に。 皮脂を落としすぎないのがポイント。
- 化粧水はたっぷり2〜3回に分けて。 手のひらで押し込むようになじませる。
- 乳液・クリームは必ず「ふた」として最後に。 油分でうるおいを閉じ込める。
- 日中の乾燥にはミスト化粧水。 オフィスや外出時に活用。
- 寝る前にリップ・ハンドクリームも忘れずに。 指先の乾燥もバリア機能を低下させます。
【3】食べ物・体の内側からのケア
外側のケアだけでなく、体の中からうるおいを保つ栄養補給も大切です。
| 栄養素 | 主な食品 | 効果 |
|---|---|---|
| ビタミンC | みかん・ブロッコリー・キウイ | コラーゲン生成をサポート |
| ビタミンE | アーモンド・アボカド・かぼちゃ | 血行を促進し、肌のターンオーバーを整える |
| オメガ3脂肪酸 | サバ・くるみ・えごま油 | 細胞膜を強化し、内側から保湿 |
| たんぱく質 | 鶏むね肉・豆腐・卵 | 肌の新陳代謝を高める |
【4】睡眠・生活習慣で整える
- 夜更かしを避けて、睡眠は6〜7時間を確保。 成長ホルモンが分泌され、肌の修復が促進されます。
- 水分をこまめにとる。 一気飲みではなく、1日8回ほどに分けるのが理想。
- ストレスを溜めない。 自律神経の乱れは乾燥や肌荒れの原因になります。
- 適度な運動で血行を促進。 代謝を上げることで、肌のターンオーバーも活性化。
まとめ|「うるおい習慣」を続けよう
乾燥は一日で解決するものではありません。
毎日の小さな積み重ねが、未来の肌をつくります。
「部屋」「スキンケア」「食事」「睡眠」それぞれの視点で見直すことで、冬の乾燥シーズンも快適に過ごせます。
うるおいを保つことは、美肌だけでなく、心の安定にもつながる大切なセルフケア。
今日からできることを一つずつ始めてみてくださいね。
関連記事