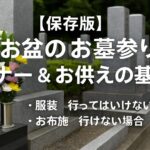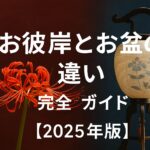「十五夜」は有名だけれど、実は秋にはもうひとつの月見「十三夜」、そして稲作文化と結びついた「十日夜(とおかんや)」があります。
2025年は十五夜=9月29日(月)、十三夜=10月11日(土)、十日夜=11月10日(月)。
三つの行事の意味と違い、由来、飾りやお供えまで一気に解説します。
\ まずは2025年の日付をサクッと確認 /
- 十五夜(中秋の名月):2025年9月29日(月)
- 十三夜(後の月・栗名月/豆名月):2025年10月11日(土)
- 十日夜(とおかんや):2025年11月10日(月)
十三夜は旧暦9月13日の月見行事で、「後(のち)の月」とも呼ばれます。
栗や豆を供える風習から「栗名月・豆名月」の別名も。
十五夜だけ・十三夜だけの片方しか見ないことは「片見月」とされ、縁起が悪いと伝えられてきました。
一方の十日夜は旧暦10月10日の収穫祭。
東日本を中心に、稲の刈り取りを終えて田の神様を送る行事として受け継がれています。
本記事では、2025年の正しい日付、それぞれの意味・由来・飾り(お供え)、そして十五夜との違いをわかりやすく整理。
秋の夜長をもっと深く楽しむための実用ガイドとしてご活用ください。
なお、十五夜の詳しい解説は こちらからどうぞ。
※日付は旧暦換算に基づき年ごとに変動します。本文では2025年の暦に合わせて解説しています。
この記事の目次です
十三夜とは?意味と由来

十三夜(じゅうさんや)とは、旧暦9月13日の夜に行われる日本の伝統的なお月見行事です。
十五夜(中秋の名月)が最も知られていますが、十三夜もそれに並ぶほど大切にされてきました。
十五夜のことを「前の月」、十三夜を「後の月」と呼び、両方をそろえて楽しむのが本来の姿とされています。
十三夜は秋の収穫と深く関わりがあり、特に栗や豆を供える風習があるため「栗名月」「豆名月」とも呼ばれてきました。
収穫したばかりの作物を月に供え、感謝の気持ちを表す意味合いが強いのです。
十五夜には里芋を供えることから「芋名月」とも呼ばれ、二つを合わせることで秋の恵みをまるごと祝う行事となります。
また、十五夜と十三夜はセットで楽しむのが習わしとされており、どちらか片方しか見ないことを「片見月(かたみづき)」と呼んで、縁起が悪いとされてきました。
このため昔の人々は、十五夜と十三夜の両方を見て初めて「月見が完成する」と考えていたのです。
十三夜は日本独自の行事であり、中国や他のアジア圏ではあまり見られません。
そのため「日本ならではの秋の月見」として特色があり、十五夜とあわせて紹介されることが多いのです。
月を愛でる文化の中でも、十三夜は「静かな秋の深まりを感じる行事」として現在も大切にされています。
2025年の十三夜はいつ?【結論:10月11日(土)】
2025年の十三夜(旧暦9月13日)
- 日付:2025年10月11日(土)
- 呼び名:後(のち)の月/栗名月・豆名月
- 意味:秋の実り(栗・豆など)に感謝し、月を愛でるお月見
十三夜は旧暦9月13日に行う行事のため、新暦では毎年日付が変動します。
2025年は10月11日(土)に該当。
十五夜(旧暦8月15日)の約1か月後にあたるこの夜には、満月の少し手前で丸みを帯びた月が昇ります。
これを「十三夜月(じゅうさんやづき)」と呼び、十五夜の満月とは異なる、ふっくらとしたやさしい姿を愛でるのが特徴です。
過去・翌年との比較
| 年 | 十三夜の日付 | 曜日 | メモ |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 10月16日 | 水 | 十五夜(9/17)の約1か月後 |
| 2025年 | 10月11日 | 土 | 週末で観月しやすい |
| 2026年 | 10月30日 | 金 | 年により10月下旬になることも |
観月のコツとしては、月の出から夜半前までが見やすく、空気が澄むと月面の陰影もくっきり。
お供えは栗・豆・お団子・旬果などを用意し、ススキ(稲穂の代わり)を飾ると雰囲気が出ます。
なお、同年の十五夜は9月29日(月)なので、両方そろえて楽しめば「片見月」を避けられます。
※日付は旧暦(太陰太陽暦)の換算により毎年変動します。本記事では2024〜2026年の対比で傾向を示しています。
十日夜とは?意味と由来

十日夜(とおかんや)とは、旧暦10月10日にあたる行事で、十五夜・十三夜と並ぶ秋の月見・収穫祭のひとつです。
十五夜や十三夜が月を愛でる行事であるのに対し、十日夜は稲作文化に根ざした収穫祭としての色合いが濃いのが特徴です。
この日は、刈り取りを終えた田んぼから「田の神様を山へ送り返す日」とされ、農村では古くから「収穫を終え、神様に感謝する節目の日」として大切にされてきました。
稲刈りを終えて実りを祝うため、地域によっては「農作業をねぎらう日」「田の神上げの日」とも呼ばれます。
十日夜は全国で共通する行事ではなく、特に東日本を中心に受け継がれています。
一方で、西日本では旧暦10月の亥の日に行われる「亥の子(いのこ)」という収穫祭が主流。
どちらも稲作と深く結びついており、収穫を神様に感謝する文化的背景は共通しています。
また、子どもたちが藁で作った「かかし」や「縄」を持って田んぼを練り歩いたり、田の神様を祀ったりする風習も各地に残っています。
こうした行事は地域色が強く、農耕文化の豊かさを伝える貴重な習わしです。
十五夜や十三夜が「月を眺めるお月見行事」であるのに対して、十日夜は「収穫を祝い、田の神様に感謝する祭り」である点が最大の違いです。
つまり、十日夜は月そのものよりも「農耕儀礼」の意味合いが強い行事といえます。
2025年の十日夜はいつ?【結論:11月10日(月)】
2025年の十日夜(旧暦10月10日)
- 日付:2025年11月10日(月)
- 意味:稲刈りを終えて田の神を山へ送り、収穫を感謝する行事
- 地域性:主に東日本で伝承、西日本では「亥の子(いのこ)」が主流
2025年の十日夜は11月10日(月)にあたります。
十五夜(9月29日)や十三夜(10月11日)よりもさらに遅い時期に行われるため、まさに秋の収穫を締めくくる行事といえます。
十五夜・十三夜との並び
| 行事 | 旧暦 | 2025年の日付 | 意味・特徴 |
|---|---|---|---|
| 十五夜 | 旧暦8月15日 | 9月29日(月) | 中秋の名月・芋名月 |
| 十三夜 | 旧暦9月13日 | 10月11日(土) | 後の月・栗名月・豆名月 |
| 十日夜 | 旧暦10月10日 | 11月10日(月) | 田の神を送る収穫祭 |
このように、十五夜・十三夜・十日夜はそれぞれ約1か月間隔で行われ、秋の収穫と月の巡りを祝う連続した行事となっています。
2025年はちょうど9月末から11月にかけて、秋の夜長を段階的に楽しめるのが特徴です。
十五夜との違いまとめ
「十五夜・十三夜・十日夜」は、すべて秋に行われるお月見・収穫行事ですが、それぞれ意味や背景が異なります。
まず十五夜は旧暦8月15日の夜に行われ、「中秋の名月」「芋名月」として広く知られています。
収穫期の里芋をお供えし、月を愛でる代表的なお月見です。
一方の十三夜は、十五夜から約1か月後の旧暦9月13日。
「後の月」とも呼ばれ、十五夜と対をなす存在です。
お供えには栗や豆を用いることから「栗名月」「豆名月」とも呼ばれ、十五夜に比べてややマイナーながらも、日本独自の風習として大切にされてきました。
そして十日夜は、旧暦10月10日に行われる稲作の収穫祭。
十五夜・十三夜が「月を見る行事」であるのに対して、十日夜は「田の神様を山へ送る農耕儀礼」の性格が強く、特に東日本で伝承されてきました。
西日本では「亥の子(いのこ)」という行事が同じ時期に行われており、地域によって特色が分かれます。
三つの行事を一覧で比較
| 行事 | 旧暦 | 2025年の日付 | 別名 | 意味・特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 十五夜 | 旧暦8月15日 | 9月29日(月) | 中秋の名月/芋名月 | もっとも有名なお月見。里芋やススキを供える。 |
| 十三夜 | 旧暦9月13日 | 10月11日(土) | 後の月/栗名月/豆名月 | 十五夜と並ぶ月見。片見月を避けるため両方楽しむのが吉。 |
| 十日夜 | 旧暦10月10日 | 11月10日(月) | 収穫祭/田の神上げ | 東日本中心の収穫祭。田の神を山へ送り感謝を捧げる。 |
このように、三つの行事は似ているようで実は目的と文化背景が異なることが分かります。
十五夜・十三夜は月見文化、十日夜は農耕儀礼。いずれも日本人が自然と共に暮らしてきた歴史を伝える大切な行事といえるでしょう。
知っておきたい豆知識
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 片見月 | 十五夜だけ、または十三夜だけを祝うこと。縁起が悪いとされ、昔の人は両方の月を眺めることを重んじた。 |
| 十三夜月 | 満月の少し手前でふっくらとした月。十五夜の満月とは異なる美しさがある。 |
| 地域差 | 東日本は「十日夜」、西日本は「亥の子」といったように、同じ時期でも文化が異なる。 |
| お供え物 | 十五夜は里芋、十三夜は栗や豆、十日夜は稲や収穫物と、行事ごとに供えるものが違う。 |
現代では「十五夜=中秋の名月」だけが有名ですが、十三夜や十日夜をあわせて知ることで、秋の風習がより立体的に理解できます。
とくに2025年は、9月29日 → 10月11日 → 11月10日と毎月行事が続くため、秋の夜長を段階的に楽しむのにぴったりです。
第6章:SNSで楽しむ十三夜・十日夜
※投稿の埋め込みが表示されない場合は、ページを再読み込みしてください。
水面…十三夜 pic.twitter.com/RMRjVpepCe
— あと (@atoreiyu200001) September 6, 2025
昨夜はヒヤガーデンで十三夜の美しい月を見ていた
#水彩の月
#十三夜
#ヒヤガーデン pic.twitter.com/78uDQgNcBs— ユメイロキリン (@yumeirokirin) September 5, 2025
今日の月
十三夜の月
綺麗だよ😍外を見てみてね✨ pic.twitter.com/6nmHlmaHng— Miu (@MiuUniverse) September 6, 2025
撮れたての夕方写真と月
⠀⠀ :::::::::::
:::::🌔::::::
::::::::::::
_
⊂⊂ ・)十日夜ウサ
/ |
⊂___u#イマソラ#ユウソラ#札幌#月#スマホ動画#スマホ写真#キリトリセカイ pic.twitter.com/nNt4S3W3cR— がろうさん (@garou3) September 3, 2025
今日の月
月齢13.4(十日夜の月)
夕焼けに染まる月ですね。#SV305C #SV165 #SVBONY #イマソラ #イマツキ pic.twitter.com/lTr33NaLPo
— follow8801 (@follow8801) August 8, 2025
※ご紹介した投稿の中には、本来の十三夜(旧暦9月13日=2025年は10月11日)とは関係なく、「月齢13日ごろの月」を指して「十三夜」と呼んでいるケースもあります。
行事としての十三夜は年1回だけですが、天文学的な「十三夜月」は毎月めぐってくるため、SNSでは両者が混在して投稿されています。
記事内では2025年の行事としての十三夜=10月11日(土)を正しい日付として解説しています。
第7章:よくある質問(Q&A)
Q1. 十三夜は毎年あるのですか?
はい、十三夜は旧暦9月13日の夜にあたるため、毎年必ずあります。
ただし新暦に換算すると日付は年ごとに変動します。2
025年は10月11日(土)、2026年は10月30日(金)にあたります。
一方で「十三夜月」という天文学的な呼び方は、毎月の月齢13日の月を指すため、SNSなどでは行事と混同されることがよくあります。
Q2. 十三夜だけを見ると「片見月」で縁起が悪いの?
はい、古くから「十五夜と十三夜をセットで見ること」が大切とされてきました。
どちらか片方だけを楽しむことを「片見月」といい、縁起が悪いと伝えられています。
とはいえ現代では「十五夜しか見られなかった」「十三夜は曇りで見えなかった」というケースも多いもの。
行事の意味を知り、できる範囲で楽しむ気持ちが大切です。
Q3. 十日夜は全国で行われているの?
十日夜は特に東日本を中心に伝わっている行事です。
西日本では「亥の子(いのこ)」という収穫祭が主流で、同じ時期に行われます。
つまり「十日夜=全国共通のお月見」ではなく、地域ごとの収穫儀礼として受け継がれているのが特徴です。
Q4. お月見団子は何個供えるの?
十五夜は15個、十三夜は13個、十日夜は10個とする説もありますが、地域や家庭によって異なります。
一般的には満月に見立てた丸い団子を奇数個(5個・9個・15個など)お供えするケースが多いです。
大切なのは数よりも「丸い形=月や収穫の象徴」として感謝を込めることです。
Q5. 2025年はどの順番で楽しむといいの?
2025年は9月29日(月)十五夜 → 10月11日(土)十三夜 → 11月10日(月)十日夜と、約1か月ごとに行事が続きます。
スケジュールを意識すれば、秋の夜長を3回にわけて楽しむことができる貴重な年です。
忙しくても1回でも参加できれば、季節を感じる良いきっかけになります。
第8章:風習の地域差
十五夜・十三夜・十日夜といったお月見行事は全国的に知られていますが、実際の風習は地域ごとに大きく異なります。ここでは代表的な違いを紹介します。
| 地域 | 特徴的な風習 |
|---|---|
| 東日本 | 十日夜が盛んで、稲刈りを終えた田の神を山へ送る行事として広く伝承。藁を使った飾りや子どもたちの行列など、農村文化の色合いが濃い。 |
| 西日本 | 十日夜よりも「亥の子(いのこ)」が主流。同じ時期に子どもたちが歌を歌いながら家々を回り、餅やお菓子をもらう行事が行われる。 |
| 関西地方 | お月見に「里芋」だけでなく「枝豆」「柿」を供える家庭も多く、秋の実りを総合的に祝う傾向が強い。 |
| 東北地方 | 月見団子を三方(さんぼう)に高く積み上げ、米どころらしい豊作祈願の意味をこめる習わしが残る。 |
| 沖縄・南西諸島 | 「ジュウグヤ」と呼ばれ、十五夜にブタ肉や餅を供えるなど独自色の強いお月見文化が存在する。 |
このように、同じ「十五夜」「十三夜」でも、供えるものや祝い方は地域によって大きく違います。
お月見は単なる行事ではなく、地域文化を映す鏡だといえるでしょう。
第9章:団子や飾り方の豆知識
お月見に欠かせないのが団子と飾り物。
十五夜・十三夜・十日夜では、供えるものに細かな違いがあります。
ここでは豆知識として整理してみましょう。
団子の数と意味
十五夜=15個、十三夜=13個、十日夜=10個とする説もありますが、必ずしも決まりではありません。
奇数は縁起が良いとされるため、9個や11個にする家庭もあります。
団子をピラミッド状に積むのは「月を模した丸い形が高い位置で月に近づくように」との願いが込められています。
ススキを飾る理由
お月見に欠かせないススキは、稲穂の代わりとされる植物です。
鋭い葉は魔除けの意味もあり、軒先に飾ると災いを避けられると信じられてきました。
十三夜や十日夜でも同様に、収穫感謝の象徴としてススキを飾る風習があります。
その他の供え物
- 十五夜:里芋・さつまいも・枝豆など「芋名月」の由来にちなむ食材
- 十三夜:栗や豆。「栗名月」「豆名月」の呼び名そのもの
- 十日夜:稲穂・新米・餅。田の神様への収穫感謝が中心
これらの供え物は「必ず用意しなければならない」ものではありません。
スーパーや和菓子屋で買える団子やスイーツを並べるだけでも立派なお月見になります。
大切なのは形や数の正確さではなく、月や自然に感謝する気持ち。
それを家族や仲間と共有することが、お月見行事の本質といえるでしょう。
まとめ|2025年は三つのお月見行事をそろえて楽しもう
本記事では、十五夜・十三夜・十日夜という三つのお月見行事について、2025年の日付や意味、由来の違いを詳しく解説しました。
改めて日付を整理すると以下のようになります。
- 十五夜(中秋の名月/芋名月):2025年9月29日(月)
- 十三夜(後の月/栗名月・豆名月):2025年10月11日(土)
- 十日夜(収穫祭/田の神上げ):2025年11月10日(月)
十五夜は最も有名なお月見であり、満月に近い月を愛でながら里芋や団子を供える風習が定着しています。
一方の十三夜は、十五夜から約1か月後に訪れる「後の月」。
栗や豆を供え、片見月を避けるために十五夜とあわせて祝うのが古来の習わしでした。
そして十日夜は、東日本を中心に伝わる農耕儀礼。稲の刈り取りを終え、田の神様に感謝を捧げる収穫祭です。
つまり三つの行事は、「月を愛でる文化」と「農作を感謝する文化」が組み合わさった日本独自の秋の風習だといえます。
中国から伝わった中秋の名月がベースでありながら、日本では十三夜や十日夜が加わり、より地域性豊かで多層的な文化として根づいてきました。
2025年は、9月末から11月にかけて約1か月ごとに行事が続くため、季節の移り変わりを感じながら順番に楽しむことができます。
十五夜で秋の始まりを祝い、十三夜で深まる秋を味わい、十日夜で収穫を締めくくる――まさに秋を三部構成で味わえる特別な年です。
現代の暮らしでは、月見団子やススキを準備する人は少なくなりましたが、スーパーや和菓子店、コンビニスイーツでも手軽に季節を楽しめます。
SNSには「#十五夜」「#十三夜」「#十日夜」などの投稿が並び、写真やコメントを通じて多くの人が秋の夜空を共有しています。
昔ながらの風習を少し取り入れるだけでも、日常に豊かな彩りを与えてくれるはずです。
2025年の秋は、ぜひ三つのお月見行事を意識してみてください。
家族や友人と月を眺めながら旬の味覚を味わえば、忙しい日常の中にも自然への感謝と季節感を取り戻すことができるでしょう。
※本記事で紹介した日付は、すべて2025年の暦に基づくものです。旧暦行事のため年ごとに日付が変動しますので、翌年以降は改めて確認してください。
関連リンク