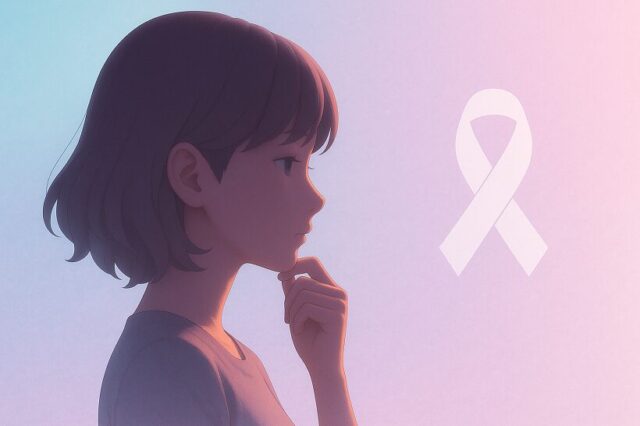
この記事の目次です
広末涼子さんの公表と世間の反響
公式発表の概要
公表内容
2025年5月2日、広末涼子さん(44)は所属事務所を通じて、公式サイト上で「双極性感情障害および甲状腺機能亢進症」と診断されたことを公表し、当面の芸能活動休止を発表しました。
同発表によれば、4月16日の勾留解除後に入院先の医療機関で診断を受け、現在は通院・自宅療養で心身の回復に専念しているとのことです。
ちなみによく聞く「双極性障害」との違いなんですが、「双極性感情障害」と同じ状態を指していて、診断基準の名称の違いによって呼び方が異なるだけです。
休止発表の背景
広末さんは4月8日に起きた交通事故・傷害容疑をめぐる逮捕・勾留を経て釈放されました。
その後の検査で今回の診断に至ったことから、事務所は「これまで『体調不良』としか説明できず、深く反省している」とコメント。
病気による責任回避の意図はないとし、引き続き警察調査にも誠実に対応するとしています。
SNS・メディアでの反応
Xトレンド入り状況
公表直後、「双極性感情障害」がXのトレンド入り(5月3日付)を果たし、多くのユーザーが関連投稿をシェア・議論。
以前の様々な言動からもしかしたらと思ってたけど…病気や障害の可能性があると分かっていたはずなのに面白がって報道してたテレビ局、コメンテーターは何か責任取るんでしょうか
広末涼子「双極性感情障害」を公表し全ての芸能活動休止発表「心身の回復に専念」甲状腺機能亢進症の診断も pic.twitter.com/2mVSj7JM83
— Samyin (@soulsaan) May 2, 2025
広末さんは病名まで明らかにしたのだから、マスコミはプライバシーを踏みにじる行為はやめて、ゆっくり治療に専念させて上げてほしい。お大事にしてください。
広末涼子「双極性感情障害」を公表し全ての芸能活動休止発表「心身の回復に専念」甲状腺機能亢進症の診断もhttps://t.co/NcwjYfGocC pic.twitter.com/fUa6lY8sEJ
— ダパン君 (@dapanblog) May 2, 2025
広末涼子さん
双極性感情障害 と 甲状腺機能亢進症
の診断を発表されましたね
双極性感情障害とは
気分の落ち込みを主とするうつ状態と
高揚気分を主とする
躁状態(そうじょうたい)
が繰り返されるとのこと
甲状腺機能亢進症 とは
甲状腺のホルモン分泌機能が
過剰に高まることで…— ⋆⸜⸝⋆★⋆⸜⸝⋆ (@dondeomasuA) May 2, 2025
広末涼子さんが双極性感情障害(躁鬱が交互に続く精神疾患)と甲状腺機能亢進症を公表。事務所の「本人の不調や苦しみを『体調不良』といった言葉で済ませてしまっていたことを/深く反省しております」という言葉が真摯で重い。著名人のメンタルヘルスケアが自己責任論からますます遠ざかることを祈る。
— 大島育宙【ドラマ/映画/エンタメの話】 (@zyasuoki_d) May 2, 2025
【発表】広末涼子が芸能活動休止 「双極性感情障害」を公表
事故当時や病院搬送された時の行動当てはまるね… pic.twitter.com/0JpiX2Esqn
— Sちゃん (@S1702587760766) May 2, 2025
著名人・専門家のコメント
- 常見陽平准教授(千葉商科大学・働き方評論家)
「メディアは広末さんの報道姿勢を今一度省みて、過熱報道の自制と正確な情報発信に努めるべきです。
正しい理解と支援なくして偏見は消えません」 - 和田秀樹医師(精神科医)
「躁状態は本人でも制御が難しく、双極性感情障害を疑うべき行動変化が見られた場合は、早期受診を強くお勧めします。
放置すると重症化リスクが高まります」 - 森田豊氏(医師・医療ジャーナリスト)
「双極性感情障害と甲状腺機能亢進症の併発は極めて稀で、まさに“ダブルパンチ”です。
身体的・精神的両側面の治療計画が不可欠となります」 - 吉田尚記アナウンサー(ニッポン放送)
「広末さんの公表は、芸能界のタブーを破り『誰もが悩みを抱える』という普遍的メッセージを届けました。
多くの人がメンタルヘルスを考えるきっかけになるでしょう」
双極性感情障害とは何か
診断基準と主な症状
DSM-5による定義
DSM-5では、双極性障害は「躁病エピソード(I型)」と「軽躁病エピソード+抑うつエピソード(II型)」に大別され、気分の高揚と落ち込みが交互に現れる状態を指します。
躁状態の特徴
-
異常な高揚感・多弁
-
睡眠欲求の減少
-
衝動的な行動増加
うつ状態の特徴
-
持続的な気分の落ち込み
-
意欲・集中力の著しい低下
-
自己評価の低下傾向
発症メカニズムとリスク要因
国際的診断基準(DSM-5/ICD-11)では、過去に一度でも躁/軽躁あるいは抑うつエピソードが存在したかをまず確認し、遺伝的素因やストレス環境が相互に影響すると考えられています。
若年・女性発症の傾向
急速交代型(rapid cycling)は女性や若年層に多いとされ、12か月間に4回以上の気分エピソードを示す場合に該当します。
甲状腺機能亢進症との併発について
甲状腺機能亢進症の基礎知識
甲状腺機能亢進症(バセドウ病など)は、甲状腺ホルモンが過剰に分泌される疾患で、代謝亢進による動悸・体重減少・発汗過多などを伴います。
双極性障害との関係性
甲状腺ホルモン過剰による興奮症状が、躁状態と類似するため、併存すると診断や治療が複雑化することが指摘されています。
治療・ケアのポイント
抗甲状腺薬(チアマゾール等)によるホルモン抑制や、必要に応じた放射性ヨウ素治療・手術を組み合わせ、総合的に症状をマネジメントします。
最新の治療法・医療トレンド
薬物療法
気分安定薬
リチウム、バルプロ酸製剤などが基本。
長期的な再発予防効果が期待されます。
抗うつ薬
抑うつエピソードにはSSRIやSNRIが用いられますが、躁転リスクに留意が必要です。
心理療法(認知行動療法ほか)
認知の修正と行動パターン変容を目指すCBTは、双極性障害にも一定の有効性が報告されています。
新しい神経刺激療法・先進治療
反復経頭蓋磁気刺激(rTMS)は、薬物療法抵抗性の抑うつエピソードに対して先進医療Bに認定され、双極性障害への応用も研究中です。
日常生活でできるセルフケア
食事・栄養管理の工夫
バランスの取れた食事と規則正しい食習慣が、気分の安定に寄与します。
運動習慣と睡眠の質向上
毎日+10分の軽い運動(ウォーキングやストレッチ)が、ストレスホルモンを抑制し良質な睡眠を促します。
ストレスモニタリングと記録
「こころの耳」などの厚労省ガイドラインを参照し、日々の気分変動をメモすると早期対応につながります。
家族・友人のサポート方法
情緒的サポートや情報提供が本人のセルフケア継続を後押しします。
職場・社会での支援策
産業医や事業所内のケア体制
産業医面談やストレスチェック結果のフィードバックを活用し、早期支援体制を整備します。
休職・復職プログラムのしくみ
段階的勤務や復職支援プログラムを導入し、無理のない職場復帰をサポートします。
公的支援制度・相談窓口
精神保健福祉センターや専門相談ダイヤルを活用し、医療・福祉サービスとの連携を図ります。
有名人カミングアウトがもたらす意義
過去の事例比較
-
キャサリン・ゼタ=ジョーンズ (Catherine Zeta-Jones)
2011年に双極性感情障害II型を公表し、クリニックでの短期入院を経て「誰もが助けを求める権利がある」と語った勇気ある告白が大きな反響を呼びました。 -
デミ・ロヴァート (Demi Lovato)
2011年、自身のSNSで双極性感情障害と摂食障害を明かし、診断後には「安心した」とコメント。
その率直さが同世代を中心に共感を集め、メンタルヘルス理解の広がりに貢献しました。 -
スティーヴン・フライ (Stephen Fry)
2006年のBBCドキュメンタリー『The Secret Life of the Manic Depressive』で、自身のサイクロチミア(軽躁うつ)を赤裸々に告白。
精神疾患に対する偏見を打破し、後続のカミングアウトを後押しするきっかけとなりました。 -
ロビー・ウィリアムズ (Robbie Williams)
同ドキュメンタリーにも出演し、“華やかなキャリアの裏側”を見せる形で自らの心の闇を共有。
大勢のファンに「誰もが悩みを抱える」というメッセージを届けました。 -
キャリー・フィッシャー (Carrie Fisher)
俳優・作家として活躍しながら双極性感情障害を公表。
ベストセラー小説や映画『スター・ウォーズ』出演と並行して語った闘病体験は、今なお多くの読者・視聴者に勇気を与えています。
日本ではいまだ「双極性感情障害」を公表する有名人は非常に少なく、欧米ほどカミングアウト事例が多くありません。
現状、広末涼子さんが最も注目度の高い先駆的な公表例と言えるでしょう。
もし日本人事例をあえて探すなら、次のようなケースがあります(いずれも双極性障害の公表というより、メンタルヘルスのカミングアウト寄りですが…)
-
坂本龍一(ミュージシャン)
うつ病や聴覚障害、がん闘病を公表し、精神面の揺らぎもメディアで言及。
双極性ではないものの、メンタルヘルスの当事者として発信した先駆例です。 -
泉谷しげる(歌手・俳優)
長年のうつ病治療歴を明かし、躁うつを含む精神疾患の理解促進に貢献。
診断名称までは公開していませんが、幅広い病状を包み隠さず語りました。 -
高橋源一郎(作家)
かつて「抑うつ状態」を自己言及し、創作への影響やセルフケア法をエッセイで共有。
学術的な双極性障害ではないものの、自身の気分の揺れを率直に語った例です。
ただし、本格的に「双極性感情障害」を公表している日本人著名人はまだほとんどおらず、そうした点でも広末涼子さんのカミングアウトは歴史的と言えます。
今後、日本から双極性障害を公式に告白する事例が増えていくことを願うばかりです。
メンタルヘルス理解促進への影響
広末さんの告白は、疾患への偏見払拭と早期受診促進の機会となり得ます。
今後の社会的ムーブメントへの期待
メディア報道やSNS議論を通じて、メンタルヘルス支援体制の社会的改善が加速することが期待されます。
まとめ
広末涼子さんの公表が教えること
公表を契機に「隠すべきことではない」というメッセージが広まり、早期診断と適切治療の重要性が浮き彫りになりました。
正しい知識とやさしい眼差しを持つために
疾患への正確な理解と、当事者への思いやりある対応こそが、社会全体の支援力を高める鍵です。
広末さんの勇気ある公表は、たった一つの“声”として始まったかもしれません。しかしその波紋は瞬く間に広がり、多くの人が自分自身や身近な人の心の健康について考えるきっかけとなりました。
-
偏見をなくす一歩
「見えない病気」に対する誤解やタブーを打ち破り、声を上げやすい空気をつくる──これが公的カミングアウトの最大の意義です。 -
情報の力を味方に
正確な知識がなければ、適切なケアも支援も始まりません。信頼できる医療機関や専門家の情報にアクセスし、自らの判断を裏づけましょう。 -
“あなたのそば”でできるサポート
家族・友人・同僚ができることは小さな一歩で十分です。-
話を「聴く」姿勢を持つ
-
慌てず、非難せずにそっと寄り添う
-
専門機関や相談窓口を一緒に探す
-
-
コミュニティの力
当事者グループや支援団体のオンラインサロン、地域のサポートネットワークに参加することで、お互いの体験と知恵を分かち合えます。
広末さんが示してくれたのは「ひとりで抱え込まない勇気」。これを私たち一人ひとりが受け取り、広めることで、誰もが安心して助けを求められる社会をつくることができます。
──今、この瞬間から。
まずは「知る」こと、そして「寄り添う」ことから始めましょう。
参考資料
- 朝日新聞:広末涼子さん「双極性感情障害」などと診断 芸能活動休止を発表
(https://www.asahi.com/articles/AST525G3BT52UCVL03LM.html?utm_source=chatgpt.com) -
テレビ朝日:広末涼子が当面の休養を発表、双極性感情障害および甲状腺機能亢進症と診断
(https://news.tv-asahi.co.jp/news_geinou/articles/900024048.html?utm_source=chatgpt.com) -
DSM-5-TR 診断基準解説【十三メンタルクリニック】
(https://juso-mental.com/bipolar-disorder?utm_source=chatgpt.com) -
国立精神・神経医療研究センター:rTMS による双極性障害治療研究
(https://www.ncnp.go.jp/activities/ar2021-06.html?utm_source=chatgpt.com) -
厚生労働省:こころの耳(セルフケアガイド)
(https://kokoro.mhlw.go.jp/?utm_source=chatgpt.com)


