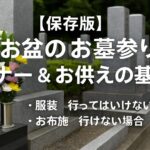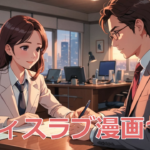2025年の十五夜(中秋の名月)は9月29日(月)です。
毎年日付が変わるので「今年はいつ?」と気になる方も多いですよね。
十五夜とは、旧暦8月15日の夜に月を鑑賞し、豊作を祈る日本の伝統行事。
別名「中秋の名月」とも呼ばれ、秋の夜空に輝く満月を愛でながら、月見団子や里芋などをお供えする習慣があります。
この記事では、十五夜の由来や食べ物の意味、全国の観月イベント、さらに現代の「月見グルメ」までをまとめました。
2025年の十五夜を楽しむための参考にしてください。
この記事の目次です
十五夜とは?由来と歴史
十五夜とは、旧暦8月15日の夜にお月見をする日本の伝統行事のことです。
現在の暦に換算すると、9月中旬から10月上旬ごろにあたります。
2025年は9月29日(月)が十五夜にあたります。
この行事の起源は中国にさかのぼります。
古代中国では「中秋節」として、月を鑑賞しながら詩を詠んだり宴を開いたりする文化がありました。
平安時代に日本へ伝わると、貴族たちの間で「観月の宴」が催され、やがて庶民にも広まりました。
十五夜は「芋名月(いもめいげつ)」とも呼ばれます。
これは収穫した里芋を月に供える風習から来ており、秋の実りに感謝する意味が込められています。
稲作だけでなく、里芋や栗、枝豆など季節の作物をお供えする地域もあります。
つまり十五夜は、月を愛でるだけでなく、自然の恵みに感謝し、豊作を祈願する大切な行事なのです。
十五夜と中秋の名月の違い
「十五夜」と「中秋の名月」という言葉はよく混同されがちですが、実は意味に少し違いがあります。
まず「十五夜」とは、旧暦8月15日の夜そのものを指します。
一方で「中秋の名月」とは、秋の真ん中(旧暦8月15日)に見える月を表現した呼び方です。
多くの場合は同じ日を指しますが、厳密には異なる概念なのです。
また、十五夜=必ず満月というわけではありません。
旧暦と新暦のずれによって、満月の日付と十五夜の日付が1〜2日ほど前後する年もあります。
2025年の場合、十五夜(9月29日)と満月はほぼ同じタイミングで重なりますが、必ずしも毎年そうなるとは限りません。
「十五夜なのに満月じゃないの?」と不思議に思う方がいるのは、この暦のズレが原因です。
さらに、日本の秋のお月見行事は十五夜だけではありません。
十五夜から約1か月後の旧暦9月13日にあたる「十三夜(じゅうさんや)」もあり、こちらは「後(のち)の月」と呼ばれています。
十五夜と並んで大切にされてきた行事で、片方だけを見るのは「片見月」とされ縁起が悪いとも言われてきました。
また、十三夜には栗や豆を供える風習があり、「栗名月」「豆名月」とも呼ばれています。
秋の実りに感謝する意味合いが強く、十五夜とセットで楽しむのが古くからの習わしです。
さらに地域によっては「十日夜(とおかんや)」と呼ばれる旧暦10月10日の収穫祭もあり、稲作文化と深く結びついています。
このように十五夜と中秋の名月は、単なる言葉の違いにとどまらず、月の満ち欠けや農耕のリズムに根ざした季節文化を映し出しています。
俳句や和歌では「名月」「望月」「秋の月」など様々な表現で詠まれており、日本人の心の中で特別な存在として大切にされてきました。
現代では「十五夜=中秋の名月=お月見」として広く使われていますが、その背景にはこうした暦や文化の違いがあることを知ると、秋の夜空を見上げる楽しみがさらに深まります。
十五夜の風習と食文化
十五夜といえば、まず思い浮かぶのは「月見団子」ではないでしょうか。
月見団子は、丸い形を月に見立てて作られ、収穫への感謝と無病息災を祈る意味があります。
一般的には白い団子を積み上げて供えますが、その数にも決まりがあります。
十五夜には「15個」を供えるのが基本とされ、三方(さんぽう)と呼ばれる台にピラミッド型に並べるのが伝統的なスタイルです。
ただし地域によっては12個(1年の月の数)や、1個だけ大きな団子を乗せて「満月」を表現するなど、バリエーションも見られます。
お供え物は団子だけではありません。
ススキを花瓶に生けて月に供える風習も広く伝わっています。
ススキは稲穂に似ていることから「豊作祈願」の象徴とされ、さらに鋭い葉が魔除けの役割を持つとも信じられてきました。
収穫前の稲穂がまだ手に入らなかった時代に、代わりにススキを飾ったことが習慣化したとも言われています。
また「芋名月(いもめいげつ)」という別名の通り、十五夜には里芋をはじめとした秋の作物を供える風習があります。
里芋は親芋と子芋が連なることから「子孫繁栄」の象徴ともされ、縁起の良い食べ物として重宝されてきました。
地域によっては栗や枝豆、柿や梨といった秋の果物を供える場合もあり、秋の実りを感謝する収穫祭としての性格が強く表れています。
十五夜の食文化は、家庭ごと地域ごとにさまざまです。
関東では白い団子が主流ですが、関西ではあんこで包んだ「おはぎ風」の団子を供える地域もあります。
沖縄では「ふちゃぎ」と呼ばれる小豆をまぶした餅を十五夜に食べる習慣があり、全国各地で多様な月見料理が息づいています。
現代の十五夜グルメ(マック・モス・ケンタの月見バーガーなど)
近年では、十五夜の季節に合わせて大手ファストフードチェーンが「月見」をテーマにした限定商品を発売するのも恒例行事となっています。
例えばマクドナルドの「月見バーガー」は卵を月に見立てた定番メニューで、秋の風物詩として毎年話題になります。
モスバーガーも「月見フォカッチャ」など独自の月見シリーズを展開し、SNSで大きな注目を集めています。
ケンタッキーも2025年には「月見チキンフィレバーガー」「月見ツイスター」といった限定商品を販売しており、チキンと卵を組み合わせたボリューム満点の月見グルメが登場します。
※投稿の埋め込みが表示されない場合は、ページを再読み込みしてください。
ついにマクドナルドの月見バーガーの季節がくる…
なんと8年ぶりにソースがリニューアル!#月見バーガー#とろ旨すき焼き月見#チーズ月見#トリプルビーフのとろ旨すき焼き月見#月見マフィン#瀬戸内レモンペッパーソース#あんバターとおもちの月見パイ… pic.twitter.com/RllMadyNSE— マクドナルド (@McDonaldsJapan) August 25, 2025
2025【月見バーガー】をまとめたよ!
マクドナルド・ロッテリア・ケンタッキー‥
みんなはどこに食べに行く? pic.twitter.com/S6mUGsOx23— BuzzFeedKawaii (@BuzzFeedKawaii) September 2, 2025
おっひる~!
✨✨
月見バーガーの季節がやって参りました!
とろ旨すき焼き月見 うんまっ!
#マクドナルド pic.twitter.com/sVG7pYgOKM— ももたろ (@momotanoro) September 3, 2025
ケンタッキーで月見なう。
少し高いけど、ボリュームあって美味しい pic.twitter.com/NAj7kYzQVG— ひさ@乗り鉄/登山ブログ (@kz_hisa) September 3, 2025
これらは伝統的なお月見とは直接関係はありませんが、卵の黄身を満月に見立てるという発想はまさに十五夜の文化を現代に引き継いだもの。
家族や友人と気軽に楽しめる新しいお月見のスタイルとして定着しています。
このように、十五夜の風習と食文化は古くからの団子や里芋にとどまらず、現代ではファストフードやスイーツなどにも広がっています。
昔ながらの伝統と現代的なアレンジが共存しているのが、十五夜ならではの魅力と言えるでしょう。
十五夜のお団子レシピ&アレンジ
十五夜といえば欠かせないのが「月見団子」。
シンプルな白い団子はもちろん、地域や家庭によってバリエーションも豊富です。
ここでは基本の作り方から、現代風のアレンジまでご紹介します。
基本の月見団子(白団子)
材料は白玉粉と水だけという、とてもシンプルなレシピです。
1. 白玉粉をボウルに入れ、少しずつ水を加えながら耳たぶくらいの固さになるまでこねる。
2. 一口大に丸めて沸騰したお湯でゆでる。
3. 団子が浮いてきたらさらに1〜2分加熱し、冷水にとって冷やす。
4. 水気を切って器に盛り付ければ完成。
積み上げるときは15個を三方にピラミッド状に並べるのが伝統的なスタイルです。
アレンジ①:みたらし団子風

子どもから大人まで人気のアレンジが「みたらし団子風」。
しょうゆ・砂糖・みりん・片栗粉で作るタレをとろりとかければ、食べやすさも抜群です。
甘じょっぱいタレともちもち食感の団子は、おやつとしてもおすすめ。
アレンジ②:あんこ団子

月見団子にこしあんや粒あんをのせたり、包んだりするスタイル。
関西地方では十五夜に「おはぎ風」のあん団子を供える地域もあります。
あんこの甘みが加わることで、より満足感のある一品に。
アレンジ③:きな粉やごま団子

香ばしいきな粉や黒ごまをまぶすのも人気。
見た目が華やかになるだけでなく、栄養価も高まります。
最近は黒ごま団子を「夜空」、白団子を「満月」に見立てて盛り付けるなど、ビジュアルを工夫する家庭も増えています。
アレンジ④:SNS映えデコ団子

現代風に楽しむなら、カラフルな団子やウサギ型のアレンジもおすすめです。
かぼちゃパウダーを混ぜれば黄色、抹茶を加えれば緑、紫芋パウダーで紫と、秋らしい彩りが出せます。
SNSでは「月とうさぎ」をイメージしたデコ団子が人気で、#十五夜 #月見団子 の投稿は毎年話題に。
子どもと一緒に作れば、思い出に残るお月見になります。
※投稿の埋め込みが表示されない場合は、ページを再読み込みしてください。
2日遅れになってしまったけど、ぐでたまのお月見だんご
ずり落ちそうなんだわ〜#ぐでたま #サンリオ #月見団子 pic.twitter.com/m6H04hpGTe— ねむねむ (@nemunemugude) September 19, 2024
【つぶやき】
今夜は中秋の名月
ですが長崎は雷雨☔⚡
帰宅すると妻がお団子を作ってくれていました#十五夜 #中秋の名月 #団子 #月見団子 #和菓子 #手作り #公式つぶやき部 #長崎一番 かま~ぼこ♪ pic.twitter.com/EzbXSD82ek
— かまぼこ 長崎一番 (@N_ichiban) September 21, 2021
#月見 pic.twitter.com/EGUoqSXlKk
— 水菜 (@fuchanlove) September 17, 2024
このように月見団子は伝統を守るだけでなく、アレンジ次第で楽しみ方が広がります。
2025年の十五夜は、定番の白団子と一緒に自分好みのアレンジ団子も試してみてはいかがでしょうか。
全国の十五夜イベント2025
十五夜は家庭で月を眺めて楽しむだけでなく、全国各地で観月祭やお月見イベントが開催されています。
2025年も各地で趣向を凝らしたイベントが予定されており、伝統文化とエンターテインメントを一緒に楽しむことができます。
東京:六本木ヒルズ「観月会」
都心で本格的なお月見が体験できるのが、六本木ヒルズで毎年行われる「観月会」。
芝生広場に座ってススキや灯籠に囲まれながら月を鑑賞できます。
和楽器の演奏や茶会なども催され、都会の真ん中にいながら秋の夜長をゆったり過ごせます。2025年も9月7日(日)を中心に開催予定です。
先日のホラーっぽくてテンションがあがった場所は、六本木ヒルズ屋上のスカイデッキでした!(の登るところ)
お月見しようと思って行ってみたら超良かった
「中秋の名月 観月会」を開催していて、天体望遠鏡でお月様見れたし、解説もあり、何よりも天気が良くて夜風が気持ち良くて最高でした pic.twitter.com/8ROqZ3UOpq— まりお (@marioioiooo) September 12, 2022
京都:下鴨神社「名月管絃祭」
京都では、雅な雰囲気の中で月を楽しむ「名月管絃祭」が下鴨神社で行われます。
舞楽や和楽器の演奏が奉納され、境内を流れる御手洗川に浮かべられた船から響く音色は幻想的そのもの。
秋の夜空と雅楽の調べが調和する様子はまさに平安絵巻のようで、毎年多くの参拝者や観光客を魅了しています。
下鴨神社の名月管絃祭に行ってました。
月きれいに見えたよー!! pic.twitter.com/k0zJYiCfS5— みづは (@miz_iro_ff14) September 17, 2024
奈良:中秋の名月祭(春日大社・興福寺)
古都奈良でも、春日大社や興福寺などで中秋の名月祭が開催されます。
特に猿沢池から五重塔を背景に月を眺める光景は絶景と評判。
伝統的な法要や雅楽の奉納もあり、静かな雰囲気の中で古都らしいお月見を体験できます。
「采女神社・猿沢池にのぼる月/采女祭」 (奈良県奈良市)
采女神社は、奈良公園内にある春日大社の末社です!猿沢池は、特に名月で知られる場所の一つで、中秋の名月に行われる例祭「采女祭」と相まって日本百名月に認定されたそうです。#日本夜景遺産 #日本百名月 #神社 #采女祭 #采女神社 pic.twitter.com/WZgxdFZS7P
— 尾川 達哉@建築士を目指す元法学部生 (@Sh_ogawa2024) December 3, 2024
明日の奈良講座に備えて前泊。今日は中秋の名月しばらく観ることができなくなる興福寺五重塔と素晴らしいコラボを観ることができました。そして采女祭。初めて、雅楽の音色の響くなか、猿沢の池に浮かぶ管絃船も観ることができました。#私は奈良派 pic.twitter.com/RXvqPN5O75
— bigaku24 (@narafan24) September 29, 2023
その他の地域
このほか、全国の寺社や庭園でも十五夜イベントが行われています。
東京・池上本門寺や、名古屋・徳川園、福岡・太宰府天満宮など、各地の名所で観月祭が開かれ、ライトアップや音楽演奏が楽しめます。
地方の公園や科学館では天体観測イベントも開催され、望遠鏡を使って月や惑星を観察することができます。
このように、十五夜の夜は全国で多彩なイベントが行われています。
2025年はぜひお近くの観月祭やお月見イベントに足を運び、秋の夜空と伝統文化を満喫してみてください。
家庭で楽しむ十五夜の過ごし方
十五夜は全国のイベントに出かけるだけでなく、家庭でも十分に楽しめる行事です。
屋外に出なくても、ちょっとした工夫で特別な一夜にすることができます。
ここでは、家族・子ども・カップル・一人暮らし、それぞれに合った楽しみ方をご紹介します。
ベランダや庭で気軽に月見

都会に住んでいても、ベランダや庭から月を眺めるだけで立派なお月見になります。
ススキや秋の花を飾り、月見団子や果物をお供えすれば、簡単に「自宅観月会」が完成。
お酒やお茶を片手に、静かに夜空を見上げる時間は日常のリセットにもつながります。
子どもと楽しむお月見工作
保育園や幼稚園でも十五夜は季節の行事として親しまれています。
家庭でも折り紙でうさぎを折ったり、画用紙で月や星を切り抜いて飾ったりすると、子どもと一緒に楽しめます。
最近では100円ショップで「お月見ガーランド」や「うさぎの壁面飾り」なども販売されており、手軽に雰囲気を演出できます。
おうちカフェ風の月見スイーツ
市販の和菓子やスイーツを「月見風」にアレンジするのもおすすめ。
丸いプリンやチーズケーキを満月に見立てたり、黄身餡やカスタードを使ったスイーツで「月」を表現したりすれば、見た目も楽しくなります。
SNSにアップするなら、黒いお皿や竹かごを使って和の雰囲気を出すと映えやすいです。
天体観測を楽しむ

十五夜は月を鑑賞する行事ですが、星や惑星を観察するのもおすすめです。
天体望遠鏡や双眼鏡がなくても、スマホアプリを使えば星座や惑星の位置を確認できます。
2025年は土星や木星も見やすい位置にあるため、十五夜の夜空は見どころがいっぱいです。
子どもにとっても科学への興味を広げるきっかけになります。
カップルや友人と「月見ディナー」
カップルや友人同士なら、ちょっと特別な「月見ディナー」を楽しむのも素敵です。
卵を使った料理(親子丼、オムライス、月見そば)や、秋の味覚(栗ご飯、きのこ汁、さつまいもスイーツ)を取り入れれば、食卓から十五夜を演出できます。
照明を落としてキャンドルを灯すと、よりロマンチックな雰囲気に。
一人暮らしでも気軽に
一人暮らしの方も、十五夜は小さな楽しみを持てる日です。
コンビニやスーパーで月見団子や秋限定スイーツを買って、ベランダや窓辺で月を眺めるだけでも十分。
「自分だけの十五夜」を気軽に楽しむのも現代的なスタイルです。
このように、十五夜の過ごし方は家庭やライフスタイルに合わせて無限に広がります。
大切なのは、秋の夜空を見上げ、自然の恵みに感謝する気持ち。
特別な準備がなくても、少しの工夫で忘れられない一夜になるでしょう。
十五夜に関するQ&A
十五夜は毎年同じ日ですか?
いいえ、十五夜の日付は毎年変わります。
十五夜は旧暦8月15日を指すため、新暦では9月中旬から10月上旬の間にずれ込みます。
2025年は9月29日(月)ですが、2024年は9月17日(火)、2026年は9月25日(金)となります。
毎年「今年はいつ?」と話題になるのはこのためです。
十五夜と満月は同じですか?
必ずしも同じではありません。
旧暦と天体の動きのズレにより、十五夜の日と満月の日が1〜2日ずれることもあります。
十五夜に少し欠けた月が見える年もありますが、古来「名月」とは必ずしも完璧な満月ではなく、少し欠けた月にも趣があるとされてきました。
なぜ団子を供えるのですか?
丸い団子は月を象徴しており、月への感謝や豊作祈願の意味が込められています。
団子の数は「15個」が基本ですが、12個(1年の月数)や1個の大きな団子で満月を表す地域もあります。
地域差が大きく、あんこやきな粉でアレンジされることも多いです。
なぜススキを飾るのですか?
ススキは稲穂に似ていることから「豊作の象徴」とされ、魔除けの意味もあります。
昔は稲穂がまだ収穫前だったため、代わりにススキを飾ったのが始まりです。
月明かりに照らされたススキは風情があり、十五夜を彩る定番の飾りとなっています。
十五夜と十三夜の違いは?
十五夜は旧暦8月15日、一方で十三夜は旧暦9月13日に行われるお月見です。
十三夜は「後の月(のちのつき)」とも呼ばれ、十五夜と同じように月を愛でる習慣があります。
両方を見てこそ縁起が良いとされ、「片見月」は不吉とされてきました。
2025年の十三夜は10月11日(土)です。
曇りや雨の日はどうすればいい?
天候が悪くても、お供えや飾りをして行事を楽しむことができます。
雲の切れ間から月が顔を出すこともありますし、見えなくても「月はそこにある」と信じて祈りを捧げるのが十五夜の心です。
最近ではオンライン配信で天体観測を楽しめるサービスもあります。
十五夜に食べるものは団子以外にありますか?
はい。里芋や栗、枝豆などの秋の収穫物を供える地域もあります。
沖縄では小豆をまぶした「ふちゃぎ」、東北ではきのこ汁やけんちん汁を食べる習慣が残っています。
現代では月見バーガーや月見うどんなども「十五夜フード」として人気です。
まとめ|2025年の十五夜を楽しもう
2025年の十五夜(中秋の名月)は9月29日(月)。
旧暦に基づく行事のため毎年日付が変わり、「今年はいつ?」と気になる方も多いですが、これで安心です。
十五夜はただ月を眺めるだけでなく、収穫に感謝し、自然の恵みを祝い、家族や地域のつながりを大切にする行事です。
月見団子やススキを供える伝統、里芋や栗などを食べる風習は、今も各地に息づいています。
一方で、マクドナルドやケンタッキーなどファストフードの月見メニュー、SNS映えするカラフル団子やうさぎモチーフなど、現代的な「月見文化」も広がりを見せています。
伝統とトレンドが共存するのも、十五夜の魅力のひとつです。
全国では多彩な観月イベントが開かれます。
遠出しなくても、ベランダで月を見ながら団子を味わったり、子どもと工作を楽しんだりと、家庭での楽しみ方も無限にあります。
2025年の十五夜は、ぜひ空を見上げてみてください。
満ち欠けの月に思いを重ね、自然と向き合う時間は、忙しい日常に豊かさをもたらしてくれるはずです。
来月10月6日には「十三夜」も待っています。
二度のお月見を楽しみながら、実りの秋を感じてみてはいかがでしょうか。
よろしければこちらもご覧ください。
関連リンク
- 【2025年最新版】お盆のお墓参り完全マナー|服装・お布施・NG日・行けないときの対処法
- 【12/10まで最大11,000円OFF】人気おせち通販2026|早割ラストチャンス&在庫情報まとめ
- お盆帰省の手土産おすすめ10選|お供えにも喜ばれる“日持ち&センス良し”ギフトを厳選【2025】
- 【2025年完全版】七夕の由来・風習・イベントまとめ|願い事の意味や織姫と彦星の物語まで
- レモン彗星2025|いつ・どこで見える?方角と見頃・撮影法
- お彼岸とお盆の違い完全ガイド|意味・由来・お参り・食べ物まで徹底解説【2025年版】
- オリオン座流星群2025|見頃はいつ?時間・方角・観測ガイド
- 紅葉ライトアップ全国ガイド|開催日・時間・名所・混雑回避まとめ【2025】
- 京都の紅葉ライトアップ|清水寺・高台寺・東寺ほかおすすめランキング&12月の穴場まで徹底ガイド
- 【2025→2026】年賀状の最終受付はいつまで?郵便局・コンビニ・宅配を完全比較
- 2025年の最強開運日「12月21日」は天赦日×一粒万倍日!やるべきこと・避けること完全ガイド