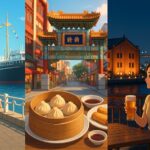1923年9月1日に発生した関東大震災を教訓に制定された「防災の日」。
毎年この時期は台風や豪雨被害も多く、災害に備える意識を高める大切な日とされています。
しかし、いざ「防災グッズを揃えよう」と思っても、
- 何をどれくらい用意すればいいのか?
- 女性の一人暮らしや高齢者家庭はどんな備えが必要か?
- 真夏の停電やゲリラ豪雨にも対応できるのか?
と、迷う方も多いのではないでしょうか?
この記事では、【2025年最新】の情報をもとに「防災の日に本当に必要なもの15選」 を分かりやすく紹介します。
非常食や停電グッズだけでなく、防犯や衛生面までカバーした「あると安心のアイテム」を厳選しました。
今年の防災の日をきっかけに、あなたの家庭の備えを一度見直してみませんか?
この記事の目次です
- 1 第1章|防災の日とは?
- 2 第2章|備えの考え方とチェックリスト
- 3 第3章|必須グッズ&便利アイテム15選
- 3.1 1. 飲料水・保存水
- 3.2 2. 非常食(アルファ米・レトルト・栄養バー)
- 3.3 3. モバイルバッテリー・ポータブル電源
- 3.4 4. 懐中電灯・ランタン(手回し/ソーラー)
- 3.5 5. 簡易トイレ・衛生用品
- 3.6 6. 多機能ラジオ(手回し/ソーラー/ライト/サイレン)
- 3.7 7. 防水リュック・非常用バッグ
- 3.8 8. 防犯ブザー・窓ロック(女性の一人暮らし)
- 3.9 9. 冷却タオル・携帯扇風機(真夏の災害)
- 3.10 10. レインウェア/ポンチョ・防水袋(ゲリラ豪雨)
- 3.11 11. カセットコンロ・ガスボンベ
- 3.12 12. 救急セット・常備薬
- 3.13 13. マスク・手指消毒・ティッシュ
- 3.14 14. 書類・現金・連絡カード
- 3.15 15. ペット用防災グッズ
- 4 第4章|SNSの声
- 5 \ 編集部おすすめの防災かばん /
- 6 まとめ|防災の日は“備えを点検する日”
- 7 関連リンク
第1章|防災の日とは?
9月1日の「防災の日」は、1923年(大正12年)に発生した関東大震災を教訓に制定された記念日です。
この震災ではマグニチュード7.9の直下型地震が発生し、死者・行方不明者10万人を超える甚大な被害となりました。
その後も日本各地で大地震や台風被害が繰り返され、1959年の伊勢湾台風の甚大な被害も重なり、1960年に政府が9月1日を「防災の日」と定めました。
防災の日は、単に地震だけではなく「あらゆる自然災害に備える日」として位置づけられています。
特に9月は台風シーズンの真っ只中であり、ゲリラ豪雨や高潮・洪水などの水害リスクも高まる時期です。
そのため自治体や学校では毎年、防災訓練や避難訓練が行われ、多くの家庭でも備蓄や避難経路の確認を行う重要な節目になっています。
なぜ「9月1日」なのか?
- 1923年9月1日の関東大震災を忘れないため
- 台風・豪雨・高潮など気象災害が集中する季節に重なるため
- 防災意識を高める啓発活動を全国で一斉に行いやすいため
さらに、9月1日は「防災の日」だけでなく、8月30日から9月5日までが防災週間に指定されています。
この期間には各地で訓練やキャンペーンが行われ、自治体や企業、学校が連携して「備え」を確認する習慣が根づいています。
つまり、防災の日は単なる記念日ではなく行動する日というのが本来の意味なのです。
日常生活ではつい忘れがちな「もしもの備え」。
ですが、毎年9月1日をきっかけに、家庭の備蓄・避難経路・災害連絡手段を改めて見直すことが、命を守る第一歩につながります。
- 毎年この時期は台風・線状降水帯の発生が増える
- 会社・学校・自治体でも避難訓練や備蓄点検を実施
- 家庭でも「持ち出し」「在宅避難」の両方を想定することが大切
参考リンク(公的データ・指針)
第2章|備えの考え方とチェックリスト
防災対策の基本は「ライフラインが止まる」ことを前提に準備することです。
地震や台風では電気・水道・ガス・通信が同時に途絶えるケースが多く、復旧までに数日〜1週間かかることも珍しくありません。
そのため、最低3日分、可能であれば1週間分の備蓄が推奨されています。
在宅避難と避難所生活の違い
最近では、コロナ禍以降「避難所に行かず自宅で過ごす=在宅避難」を選ぶ人が増えています。
在宅避難はプライバシーが守られ、感染症リスクも低い一方で、電気・水道・トイレなどをすべて自力で確保しなければなりません。
一方、避難所は食料や水が配給される可能性があるものの、物資不足や混雑、感染症の不安があります。
どちらを選ぶにしても「最低限の備え」を自宅で準備しておくことが不可欠です。
ローリングストック法
災害用の食料や水を「特別に買って保管する」だけだと、気づいたら賞味期限切れになりがちです。
そこで推奨されているのがローリングストック法。
普段から食べているレトルト食品や缶詰、飲料水を少し多めに買い置きし、使ったら補充するサイクルを回す方法です。
日常生活の延長で備蓄ができるため、無駄なく効率的にストックを維持できます。
忘れがちな備蓄品リスト
- ラップやアルミホイル:皿にかぶせれば洗い物が不要に
- 軍手や厚手の手袋:片付けや避難時に必須
- 乾電池・モバイルバッテリー:サイズや端子を確認
- ビニール袋:簡易トイレや防水対策に多用途
- ホイッスル:閉じ込められた時に居場所を知らせる
企業・自治体での備え
自治体や企業も、防災計画の一環として3日分の備蓄を基準にしています。
特に企業はBCP(事業継続計画)の観点から、従業員がオフィスに留まる場合に備えた水や食料を確保しています。
こうした公的機関・民間企業の基準を参考に、家庭でも「3日〜1週間」を目安にすると安心です。
第3章|必須グッズ&便利アイテム15選
1. 飲料水・保存水
災害時に最も重要なのは「水」です。
人は水がないと3日程度しか生きられないとされ、飲料水の確保は生命線になります。
内閣府の指針では1人1日3リットルを目安とし、最低3日分(できれば1週間分)の備蓄が推奨されています。
長期保存水(5〜10年保存可能)をケース単位で購入しておくと安心。
調理や歯磨き・手洗いなど生活用水も別に必要なので、ペットボトル水やポリタンクに準備しておきましょう。
- 保存水は「飲料用」と「生活用」に分けて確保する
- 期限が近いものはローリングストックで消費・補充
2. 非常食(アルファ米・レトルト・栄養バー)

災害時はコンビニやスーパーに商品が並ばず、物流も止まることがあります。
そのため、すぐに食べられる非常食の備えが欠かせません。
アルファ米はお湯や水を注ぐだけでご飯になる便利な食品で、5年保存可能な商品もあります。
レトルト食品や缶詰、栄養補助バーを組み合わせれば、飽きずに栄養バランスを取ることができます。
子どもや高齢者には柔らかい食品、アレルギー対応食品を選ぶのも大切です。
- 主食・おかず・甘いものを組み合わせるとストレス軽減
- 非常食は年に1度「試食」して味や食べやすさを確認
アルファ米とは?
アルファ米とは、一度炊いたお米を急速乾燥させた保存食のことです。
お湯や水を加えるだけで、炊きたてに近いご飯を手軽に再現できます。
常温で長期保存が可能(5年〜7年の商品も)なので、防災用の非常食として最も普及しています。
- お湯を注げば約15分、水でも60分で食べられる
- 種類が豊富(白飯・五目ごはん・カレー味など)
- 軽量で持ち運びやすく、アウトドアにも活用できる
3. モバイルバッテリー・ポータブル電源
停電時にスマホが使えなくなると、情報収集や家族との連絡が困難になります。
そのため、大容量のモバイルバッテリー(10,000mAh以上)やポータブル電源を準備しておくことが必須です。
最近はソーラーパネル付きや手回し充電対応の製品もあり、長期停電でも活用できます。
在宅避難を想定するなら、扇風機やIH調理器などにも使えるポータブル電源が安心です。
- 容量・充電速度・ポート数を確認して購入
- 普段からスマホ充電に使い「動作確認」をしておく
4. 懐中電灯・ランタン(手回し/ソーラー)

夜間の停電は想像以上に不便で危険です。
懐中電灯やランタンは、避難時や在宅避難中に必須となります。
乾電池式のほか、手回し充電やソーラー式なら電池切れの心配もありません。
枕元には小型ライト、リビングにはランタン、と使い分けると安心です。
吊り下げ型のLEDランタンは部屋全体を明るく照らせるため、避難所でも重宝されます。
- 乾電池のサイズ(単1・単3など)は事前に統一しておく
- 夜間の避難に備え「両手が使えるヘッドライト」も有効
5. 簡易トイレ・衛生用品
災害時に多くの人が困るのが「トイレ」です。断水や下水道の停止で水洗トイレが使えなくなると、衛生環境が悪化し感染症リスクが高まります。
凝固剤と処理袋を組み合わせた簡易トイレは必須アイテム。
加えてウェットティッシュ、消臭剤、生理用品、乳幼児用おむつなども備えておくと安心です。
1人あたり1日5回程度を目安に計算し、家族分を揃えておきましょう。
- トイレ対策は「水より先に尽きる」と言われるほど重要
- 消臭・防臭効果のある袋を選ぶと衛生的
6. 多機能ラジオ(手回し/ソーラー/ライト/サイレン)

災害時はスマホの通信が不安定になり、インターネットにアクセスできないこともあります。
そんな時に頼りになるのが防災ラジオです。
気象庁や自治体からの緊急情報を確実に受け取れるため、避難の判断にも直結します。
最近のモデルはラジオ機能だけでなく、LEDライト・サイレン・スマホ充電ポートを備えた多機能タイプが主流。
電源も手回し充電・ソーラー・乾電池の3WAY対応が多く、停電が長引いても活用できます。
- FM/AMに加えて「ワイドFM対応」だと情報源が増えて安心
- USB充電可能なタイプならスマホの緊急充電にも対応
7. 防水リュック・非常用バッグ
避難の際は両手が空く防水リュックが必須です。
大雨や津波の避難時に荷物が濡れると意味がないため、防水性はとても重要。
非常持ち出し袋として、市販のセットを活用するのも良いですが、自分や家族に合わせて中身をカスタマイズするのが理想です。
仕切りやポーチで小分けすれば、必要なものがすぐに取り出せて混乱を防げます。
リュックのサイズは20〜30L程度が目安。
重すぎると避難の妨げになるため、背負って歩ける範囲で調整しましょう。
- 防水カバーやスタッフサックで中身を水から守る
- 家族の人数分を用意し、子どもにも軽量バッグを持たせる
8. 防犯ブザー・窓ロック(女性の一人暮らし)
災害時は停電や避難所生活で、防犯リスクが高まります。
特に女性の一人暮らしでは、避難所のプライバシー確保や自宅待機時の安全対策が欠かせません。
防犯ブザーは緊急時に大きな音を出して周囲に危険を知らせる道具。
また、自宅で在宅避難をする場合は、窓や玄関に後付けできる補助ロックを設置すると安心感が増します。
夜間照明や覗き見防止シートも、心理的な安心につながります。
- 女性の単身世帯や高齢者世帯は「防犯+防災」を意識する
- 避難所では貴重品は常に身につけ、ブザーを手元に置く
9. 冷却タオル・携帯扇風機(真夏の災害)

真夏に停電が起こると、エアコンが使えず熱中症の危険が急増します。
冷却タオルは水に濡らすだけで気化熱によって体を冷やせるアイテムで、避難所や在宅避難で重宝します。
また、乾電池式やUSB充電式の携帯扇風機も、空気を循環させて体感温度を下げる効果が期待できます。
高齢者や子どもは暑さに弱いため、夏場の防災グッズには必ず加えておきたいところです。
- 冷却タオルは軽量・繰り返し使えるタイプを選ぶ
- 携帯扇風機は「乾電池対応」だと停電時も安心
10. レインウェア/ポンチョ・防水袋(ゲリラ豪雨)
災害は天候を選びません。
台風やゲリラ豪雨の避難時にレインウェアやポンチョがあるかどうかで安全性が大きく変わります。
傘では両手が塞がるため、必ずレインウェアを用意しましょう。
特に上下分かれた防水タイプは動きやすく避難に適しています。
スマホや貴重品は防水袋(ドライバッグ)に入れて持ち運ぶと、水没による故障や紛失を防げます。
避難所に入ってからも、濡れた衣類を入れる袋として役立ちます。
- 子ども用レインコートも忘れずに準備
- ポンチョは背中にリュックを背負ったまま羽織れるタイプが便利
11. カセットコンロ・ガスボンベ
停電やガス供給の停止が長引くと、温かい食事をとることが難しくなります。
そんなときに活躍するのがカセットコンロです。
お湯を沸かしたり、レトルト食品を温めたり、簡単な調理が可能になります。
ガスボンベは1本で約60分程度使用可能とされ、3日分なら1人あたり3〜5本が目安です。
ただし高温になる場所や火気の近くでの保管は避け、定期的に使用・交換してストックを循環させましょう。
- 災害用に「防風タイプ」のカセットコンロがおすすめ
- ボンベの使用期限(製造から約7年)を必ず確認する
12. 救急セット・常備薬

怪我や病気は災害時にも避けられません。応急処置ができるように救急セットを常備しましょう。
絆創膏・消毒液・ガーゼ・テーピングに加え、体温計や爪切りも役立ちます。
また、持病がある方は最低1週間分の常備薬を用意し、お薬手帳や処方内容のコピーも一緒に保管することが推奨されています。
避難所では医療体制が整うまで時間がかかることもあるため、自分で対応できる備えが必要です。
- 持病薬は必ず「かかりつけ医」に相談して予備を確保
- 小分けケースに「誰の薬か」を明記すると混乱を防げる
13. マスク・手指消毒・ティッシュ
感染症対策はコロナ禍以降、災害時でも必須となりました。
避難所のように人が密集する環境ではマスク・消毒液・ティッシュがあるかどうかで健康リスクが変わります。
粉じんやほこりの吸入を防ぐ意味でも役立ち、アレルギーを持つ人には特に重要。
また、避難所での「ちょっとした生活の不便」を解決するためにも、多めに用意しておきたいアイテムです。
- 布マスクよりも不織布マスクを推奨
- アルコール消毒はスプレーとジェルの2種類を持つと使い分けできる
14. 書類・現金・連絡カード
災害時は電子決済が使えなくなることがあります。
そのため、必ず現金(特に小銭)を用意しておきましょう。
自動販売機や店舗でのお釣りが不足することもあるためです。
さらに、身分証明書・健康保険証・銀行口座や保険関連のコピーをファイルにまとめ、「緊急連絡カード」を作成して家族全員が携帯すると安心です。
スマホに情報を保存するだけでなく、紙に書いて持ち歩くことが停電時には有効です。
- コピーは耐水性のクリアファイルに入れて保管
- 家族の集合場所・連絡手段を事前に話し合っておく
15. ペット用防災グッズ

ペットも大切な家族です。
災害時には人間だけでなくペット用の備えも必要になります。
フード・飲料水・トイレ用品・キャリーケース・ワクチン証明書などをセットにして保管しましょう。
避難所によってはペット同伴が制限される場合もあるため、自治体のガイドラインを確認しておくことも大切です。
普段からキャリーに慣れさせておくことで、いざという時のストレスを減らせます。
- 7日分のフードと水を目安に備蓄
- 首輪や迷子札、マイクロチップ情報を最新に更新
第4章|SNSの声
実際に防災グッズを備えている人の声は、とても参考になります。
ここでは、X(旧Twitter)に投稿された実際の声をいくつか紹介します。
「防災用ライト?あるよ」って言ってる人
このタイプは持ってない確率100%
火も電池もいらない。
水と塩で光る緊急ライト。 pic.twitter.com/vz2DHwj9ff— いくみ⛑️ (@193fp) August 20, 2025
本家より厚焼きな「たべっ子どうぶつ」の防災用ビスケットが良い… 賞味期限は製造日から5年あり非常食に◎(詳細はスレッドへ🦒🐇🦣🦁) pic.twitter.com/SC82rWLFKZ
— ふわふわさんଳ (@fuwa_shop) August 25, 2025
⚠️【防災特集ウィーク】📢
9月1日は「防災の日」。
日用品の“ラップ”が、実は防災グッズとして大活躍するのをご存じですか?今回は「ラップの意外な活用術 3選」をご紹介します。
1️⃣ 怪我の応急処置に
傷口を覆って止血や汚れ防止に役立ちます。2️⃣ 寒いときの腹巻き代わりに… pic.twitter.com/nPiHb0SIKb
— Yoshino Power Japan 【公式】 (@yoshino_power) August 26, 2025
防災用ストックはお菓子がほんと優秀。
いざという時こそ「好きな味」が力になる。備えるってこういうことじゃない? pic.twitter.com/X4uNqUfHLG— いくみ⛑️ (@193fp) August 21, 2025
公式サイトのマニュアルとあわせて、こうしたみんなの声を参考に自分に合った防災グッズを揃えておくと安心です。
\ 編集部おすすめの防災かばん /
「防災グッズを一つずつ揃えるのは大変…」という方におすすめなのが、
防災士&消防士が監修した【あかまる防災かばん】です。
- ✅ 充実の44アイテムを専門家が厳選
- ✅ カジュアルでおしゃれだから家に置いても違和感なし
- ✅ 10年間の交換保証付きで長期安心
特に30代女性・子育て世帯に人気で、
新築祝い・地震対策・親族へのプレゼントにも選ばれています。
防災の日(9月1日)や点検日のタイミングで検討する人も多数!
まとめ|防災の日は“備えを点検する日”
9月1日の「防災の日」は、関東大震災の教訓を忘れず、日常から防災意識を高めるために制定された大切な記念日です。
日本は地震・台風・豪雨などの自然災害が多く、いつどこで被害に遭うか分かりません。
だからこそ「普段からの備え」が命を守ります。
この記事では、防災の考え方から具体的な備蓄方法、必須アイテム15選までを紹介しました。
水や食料はもちろん、停電対策・衛生管理・防犯対策までカバーすることが、家族や大切な人を守る第一歩です。
そして、防災グッズは一度揃えて終わりではなく、「点検・更新」を繰り返していくことが重要です。
「何から揃えればいいか分からない」という方は、専門家監修の防災セットを活用するのもおすすめ。
必要なものが一式まとまっているので、初心者でもすぐに防災対策を始められます。
今年の防災の日をきっかけに、あなたの家庭の備えを点検・強化してみてください。
備えあれば憂いなし。
小さな一歩が、大きな安心につながります。
こちらもどうぞ
関連リンク