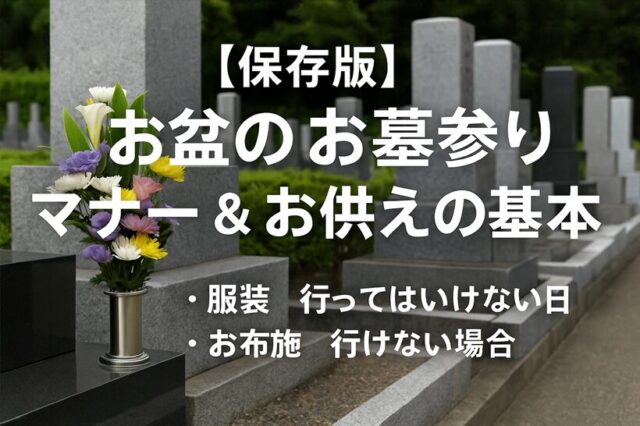
お盆は、先祖や故人を供養する大切な時期です。
特に「お墓参り」は、日本の伝統的な行事として多くの家庭で行われています。
しかし、「お盆のお墓参りのマナー」や「正しい服装」「行ってはいけない日」など、意外と知られていないルールや注意点も多いものです。
また、遠方や高齢、仕事の都合でお墓参りに行けない場合の対処法や、オンライン供養・墓参り代行、墓じまいといった現代ならではの選択肢も増えています。
この記事では、
「お盆 お墓参り マナー」
「お盆 お墓参り 服装」
「お墓参り 行けない場合」
「墓じまい」
などのキーワードに沿って、服装や持ち物、お供えの選び方、時期や時間帯、地域や宗派による違いまで、初心者にもわかりやすく解説します。
さらに、トラブルを避けるためのポイントや、お盆に行けない場合の供養方法まで網羅。
2025年最新版として、お盆のお墓参りに関する知識と実践マナーを総まとめします。
この記事の目次です
第1章:お盆のお墓参りの意味と由来
お盆とは?
お盆とは、毎年8月(地域によっては7月)に行われる、日本の伝統的な仏教行事です。
正式には「盂蘭盆会(うらぼんえ)」と呼ばれ、先祖の霊を家に迎えて供養し、再び見送る期間を指します。
お盆の期間は、家族や親戚が集まり、仏壇やお墓をきれいにして供物を捧げ、線香をあげることで先祖への感謝と敬意を表します。
お盆にお墓参りをする意味
お盆にお墓参りをする意味は、単なる習慣ではありません。
先祖の霊を迎えるためにお墓を掃除し、心を込めて供養することで、家族の絆を確認し、日々の無事を感謝する大切な時間となります。
また、故人や先祖の存在を思い出すことで、自分のルーツを再確認し、精神的な安らぎを得られるともいわれています。
お盆のお墓参りの由来は古く、仏教の教えと日本古来の祖霊信仰が融合して生まれました。
盂蘭盆会の起源は、お釈迦様の弟子・目連尊者が亡き母を救うために供養を行ったという「盂蘭盆経(うらぼんきょう)」の説話にさかのぼります。
この教えが中国を経て日本に伝わり、祖先を供養する行事として定着しました。
現代では宗派や地域によってお盆の過ごし方やお墓参りの時期は異なりますが、「先祖に感謝し、家族のつながりを大切にする」という根本的な意味は変わりません。
第2章:お盆のお墓参りの正しい時期と時間帯

お盆のお墓参りはいつ行くべき?
お盆のお墓参りは、一般的にお盆期間中の「迎え盆」または「送り盆」に行うのが習わしです。
多くの地域では8月13日が迎え盆、16日が送り盆とされ、13日または14日にお墓を訪れて先祖の霊をお迎えし、15日または16日に再びお墓を訪れて見送ります。
ただし、地域や宗派によって時期は異なります。
東京や一部の地域では旧暦に基づき、7月13日〜16日にお盆を行う「新盆(しんぼん)」スタイルが一般的です。
自分の地域の風習を事前に確認しておくことが大切です。
お墓参りに適した時間帯
お墓参りの時間帯は、午前中から日中にかけてが良いとされています。
理由は、日没後は霊が迷いやすいとされることや、防犯面・安全面からも明るい時間帯の方が望ましいためです。
また、朝の涼しいうちに参拝することで、夏場の熱中症リスクも軽減できます。
お墓参りに行ってはいけない日はある?
一部の地域では、お彼岸やお盆以外の忌日や命日以外の日に参ることを避ける風習がありますが、多くの場合は都合のつく日程で構いません。
現代では、家族全員が集まりやすい日を優先し、お盆前後にずらしてお墓参りを行うケースも増えています。
まとめ:日程よりも気持ちが大切
先祖を敬う気持ちを第一にし、無理のない日程と時間帯で参拝することが、お盆のお墓参りでは何よりも大切です。
第3章:お盆のお墓参りの服装マナー
お盆のお墓参りにふさわしい服装とは?
お盆のお墓参りの服装は、法事ほどの厳格さは必要ありませんが、派手すぎず落ち着いた色合いが基本です。
黒・グレー・ネイビー・ベージュなどの控えめな色を選び、柄物や鮮やかな色は避けるのが無難です。
女性の場合はワンピースやブラウスにロングスカート、パンツスタイルでも問題ありませんが、露出の多い服や短すぎるスカートは避けましょう。
男性は襟付きシャツやポロシャツにチノパンやスラックスなど、きちんと感のある服装がおすすめです。
夏場のお墓参りの服装選びのポイント
お盆は真夏の行事ですので、熱中症対策も大切です。
通気性の良い麻や綿素材の服を選び、色も黒一色よりはネイビーやグレーなど熱を吸収しすぎない色が快適です。
帽子や日傘も活用しましょう。
ただし、あまり派手なデザインや蛍光色は避け、落ち着いた印象を心がけてください。
靴と足元のマナー
お墓参りは砂利道や階段を歩くことが多く、足元が滑りやすい場合もあります。
そのため、ヒールの高い靴やサンダルは避け、歩きやすく安定感のある靴を選びましょう。
女性の場合、ローヒールのパンプスやスニーカー、男性は革靴や落ち着いたスニーカーが無難です。
墓地によっては水を使って掃除を行うため、靴が濡れることもあります。
防水スプレーを事前にかけておくと安心です。
まとめ:清潔感と機能性を両立する
お盆のお墓参りの服装は、先祖への敬意を表すための「きちんと感」と、真夏でも快適に過ごせる「機能性」を両立させることがポイントです。
第4章:お墓参りの持ち物チェックリスト

基本的な持ち物
お盆のお墓参りでは、先祖の霊を供養し、お墓をきれいに保つための道具や供え物を用意します。忘れ物がないよう、事前にチェックリストを作っておきましょう。
- 線香・ろうそく・マッチ(ライター):お供えの基本。風が強い日は風防付きライターが便利です。
- お花:菊やカーネーションなど、香りが強すぎない花がおすすめ。
- お供え物:果物、お菓子、故人が好きだった飲み物など。カラスや猫に荒らされないよう、持ち帰るのがマナーです。
- 掃除道具:ほうき、雑巾、バケツ、軍手など。
夏のお墓参りで役立つ持ち物
真夏のお墓参りは日差しや熱中症のリスクが高いため、暑さ対策グッズも忘れずに持っていきましょう。
- 帽子・日傘:直射日光を避け、熱中症予防に。
- 冷感タオル:首元を冷やすことで体温上昇を防ぎます。
- ペットボトルの水やスポーツドリンク:水分補給はこまめに。
- 虫よけスプレー:蚊やアブなどの虫対策に必須。
あると便利なアイテム
お墓参りをより快適に、スムーズに行うためにあると助かるアイテムもあります。
- 折りたたみ椅子:長時間の作業や高齢の方が休憩する際に便利。
- 防水スプレー:靴やバッグの汚れ防止に。
- ビニール袋:ごみや使用済みの花を持ち帰るため。
まとめ:持ち物は事前準備がすべて
お墓参りは限られた時間で行うことが多いため、必要な持ち物を事前に揃えておくことで、心穏やかに先祖を供養できます。
特に夏場は暑さ対策と虫よけ対策を忘れずに行いましょう。
第5章:お墓参りの作法と流れ
お墓参りの基本的な流れ
お盆のお墓参りは、先祖への感謝と供養の気持ちを表す大切な行事です。地域や宗派によって多少異なりますが、一般的な流れは次の通りです。
- 墓前に到着したら一礼:まずは静かに手を合わせ、挨拶をします。
- 掃除:墓石や花立、周囲の雑草を取り除き、きれいに整えます。
- お花・お供え物を供える:お花は左右対称に挿し、お供え物は正面に置きます。
- 線香・ろうそくを灯す:火をつけ、手を合わせて祈ります。火を吹き消すのではなく、手であおいで消すのがマナーです。
- 合掌・お参り:胸の前で手を合わせ、感謝の気持ちを伝えます。
お参りの際のマナー
お墓参りでは、周囲や他の参拝者への配慮も大切です。
次のポイントを意識しましょう。
- 大声で話したり、笑い声を上げたりしない
- お供え物はそのまま放置せず持ち帰る
- 墓石や備品を傷つけない
- ペット同伴の場合は墓地の規則を確認する
お墓参りで避けたいNG行為
何気ない行動がマナー違反となることもあります。
特に次のような行為は避けましょう。
- お酒をかける(墓石を傷める原因になります)
- ジュースやコーヒーをかける
- 線香の火を口で吹き消す
- 派手な写真撮影をする
まとめ:心を込めて丁寧に
お墓参りは作法を守ることが目的ではなく、先祖を敬う気持ちを形にする場です。
正しい手順とマナーを知ることで、心から落ち着いて供養ができるでしょう。
第6章:お盆のお墓参りに行けないときの対応

行けない理由はさまざま
お盆にお墓参りをしたくても、遠方に住んでいたり、体調や仕事の都合で行けないことがあります。
近年は高齢化や核家族化も進み、「行きたくても行けない」ケースが増えています。
代わりにできる供養方法
- 仏壇での供養:自宅の仏壇やお位牌に手を合わせ、お線香やお花を供える。
- お寺へのお参り:菩提寺や近くのお寺に参拝し、先祖や故人の供養をお願いする。
- 法要や読経を依頼:お寺に連絡し、お盆の期間に合わせて読経や回向(えこう)を行ってもらう。
近年増えている新しいサービス
時代の変化に合わせ、直接お墓に行けない人のための便利なサービスも増えています。
- 代理墓参りサービス:専門業者が代わりに墓石の清掃やお参りをして、写真や報告書を送ってくれる。
- オンライン供養:インターネット越しに僧侶が読経を行い、動画やライブ配信で供養の様子を確認できる。
- 墓じまい・永代供養:お墓の維持が難しい場合、墓じまいや永代供養を選ぶ人も増えている。
お寺とのやり取りや手続きが不安な場合は、専門業者の代行を利用するのも安心です。
▶お寺とのトラブル・離檀・墓じまい代行はおまかせ【わたしたちの墓じまい】
気持ちを込めることが大切
お墓参りの本質は「距離や形ではなく、故人を想う心」です。直接お墓に行けなくても、感謝や祈りの気持ちを持ち続けることが何よりの供養になります。
第7章:お墓参りで気をつけたい服装・持ち物マナー
服装の基本
お墓参りでは、派手すぎず清潔感のある服装が基本です。お盆の時期は暑いですが、露出の多い服やカジュアルすぎる装いは避けましょう。
- 色は黒・紺・グレーなど落ち着いた色合い
- ジーンズや派手な柄物は避ける
- ノースリーブや短すぎるスカートは控える
- 帽子やサングラスはお参り時には外す
夏場の服装ポイント
猛暑の中でのお参りは熱中症対策も重要です。長袖の薄手シャツや通気性の良い素材を選び、日傘や水分補給も忘れずに。
持ち物リスト
お墓参りに必要な持ち物を事前に準備しておくと、現地で慌てずに済みます。
- 生花(地域や季節に合わせて)
- お線香・ろうそく・マッチやライター
- お供え物(故人が好きだった食べ物など)
- 掃除道具(ほうき、雑巾、ゴミ袋)
- 虫よけスプレー
- タオルやウェットティッシュ
服装や持ち物で避けたいNG例
知らず知らずのうちにマナー違反となってしまうこともあります。
- 派手なアクセサリーや香水
- 動きにくいヒールやサンダル
- 大量のお供えを置きっぱなしにする
まとめ
服装や持ち物は、故人や周囲の人への敬意を表す大切な要素です。
派手さよりも「清潔感」と「動きやすさ」を優先し、気持ちよくお参りできる準備を整えましょう。
第8章:お墓参りに行ってはいけない日・時間帯

仏教的な考え方から見た避けたほうがよい日
お墓参りは基本的にいつ行っても構いませんが、宗派や地域の風習によっては避けたほうが良いとされる日があります。
- 友引(ともびき):六曜のひとつで、「友を引く」という意味から葬儀を避ける習慣があります。お墓参りそのものは禁止ではありませんが、気にする方もいます。
- 仏滅:仏教的には関係が薄いですが、縁起を気にする人の中には避ける人も。
- 雨の日や台風の日:宗教的な理由ではなく、安全面から控えるべき日です。
時間帯に関するマナー
お墓参りは日の高いうち、特に午前中から昼過ぎにかけて行うのが一般的です。
夕方や夜間は避けるほうが望ましいとされています。
- 午前中が望ましい:仏事は「午前中に済ませる」とされる地域も多く、涼しい時間帯なので作業もしやすい。
- 夕方〜夜は避ける:防犯面、安全面の理由に加え、暗い時間にお墓参りをすることを不吉とする風習もあります。
地域や家庭の風習も尊重する
現代では日にちや時間帯をあまり気にしない人も増えていますが、親族や地域によっては特定の日を避ける習慣が根強く残っています。
事前に家族や年長者に確認しておくと安心です。
まとめ
お墓参りは「絶対に行ってはいけない日」があるわけではありませんが、風習や安全面を踏まえて選ぶことが大切です。
時間帯は明るく安全なうちに、お参りできる日程を調整しましょう。
第9章:お墓参りにまつわるよくある質問(Q&A)
Q1. お墓参りは年に何回行けばいいですか?
決まった回数はありませんが、一般的には以下のタイミングで行く家庭が多いです。
- 春彼岸(3月)
- お盆(8月)
- 秋彼岸(9月)
- 命日や月命日
遠方の場合は年に1〜2回でも問題ありません。大切なのは、故人を思い出し手を合わせる気持ちです。
Q2. お墓参りに適した服装は?
法事や法要を伴う場合は喪服や礼服が基本ですが、通常のお墓参りでは黒や紺、グレーなど落ち着いた色の服装であれば問題ありません。
露出の多い服や派手な柄は避けましょう。
また、墓地は足元が悪い場合が多いため、歩きやすい靴をおすすめします。
Q3. お墓参りに持っていくものは?
最低限あると良いものは以下です。
- お花(故人が好きだった花でも可)
- お線香・ロウソク・マッチまたはライター
- お供え物(お菓子や果物など)
- お墓掃除用の道具(タオル、ブラシ、バケツなど)
- 数珠
現地の売店で揃えられる場合もありますが、事前に準備すると安心です。
Q4. お供え物はそのまま置いて帰っていいの?
基本的には持ち帰るのがマナーです。
動物や鳥に荒らされる原因になり、墓地の管理にも支障が出ます。
お参り後は感謝の気持ちを込めて持ち帰りましょう。
Q5. 宗派によってお参りの作法は違いますか?
作法や読経の内容は宗派によって異なりますが、一般的な流れは共通しています。
- お墓の掃除
- お花やお供え物を供える
- お線香やロウソクを灯す
- 合掌して故人を偲ぶ
詳細な作法は、菩提寺や親族に確認しておくと安心です。
Q6. お墓参りのときに写真を撮ってもいいですか?
禁止されているわけではありませんが、他の方のお墓や参拝中の姿が写らないよう配慮が必要です。
また、SNSに投稿する場合は故人や家族のプライバシーに十分注意しましょう。
Q7. 行けない場合はどうすればいい?
体調不良や遠方で行けない場合は、命日やお盆に合わせて自宅で手を合わせたり、代理墓参りサービスを利用する方法もあります。
近年はオンライン供養や墓じまいなどの選択肢も増えています。
お寺とのやり取りや離檀・墓じまいを検討している場合は、専門業者のサポートを受けるとスムーズです。
第10章:地域別風習とお墓参りの豆知識
地域別に見るお盆とお墓参りの違い
お盆のお墓参りは全国共通の文化ですが、地域によって時期ややり方に違いがあります。
旅行や引っ越しで他地域のお盆行事に参加する際は、事前に確認しておくと安心です。
- 北海道・東北:8月13~16日が中心ですが、北海道では寒冷地特有の気候を考慮して短期間で行う場合も。盆踊りや灯籠流しが盛ん。
- 関東:東京や一部地域では7月13~16日に行う「新盆(しんぼん)」が一般的。それ以外の関東地方は8月が主流。
- 北陸:お盆と合わせて花火大会が行われることも多く、夜にお墓参りする習慣がある地域も。
- 中部・近畿:京都では大文字焼き(五山送り火)が有名。お墓参りは送り火の前後に行う家庭が多い。
- 中国・四国:精霊流しや盆提灯を飾る文化が根強い。お墓の前でお弁当を広げる風習が残っている地域も。
- 九州・沖縄:沖縄は旧暦7月13〜15日に行うため、毎年日程が変わる。エイサーやごちそうを囲む独自文化が魅力。
お供えの選び方と豆知識
お供えは故人や家族の好みに合わせるのが基本ですが、真夏のお盆では傷みにくい品を選ぶことも大切です。
- 傷みにくい食べ物:和菓子(落雁・羊羹)、日持ちする果物(りんご・メロン)
- 飲み物:冷たい麦茶やミネラルウォーター、缶コーヒーなど個別包装タイプ
- 花:菊、リンドウ、スターチスなど暑さに強い花が長持ちします
- 線香・ローソク:風が強い日は太めのローソクや短い線香が便利
ワンポイント: 生菓子やカットフルーツは供え時間を短くし、持ち帰っていただくのが衛生的です。
お墓参りで注意したいトラブルと対策
- 暑さ対策:真夏は炎天下での墓石掃除が熱中症の原因に。帽子・日傘・水分補給を忘れずに。
- 虫刺され:蚊やアブが多く発生するため、虫よけスプレーや長袖を用意。
- カラスや動物被害:お供え物を置きっぱなしにすると荒らされることがあるため、持ち帰るのが基本。
- 盗難:花立やお供えが持ち去られるケースもあるため、貴重品や高価な品は避ける。
こうしたポイントを押さえることで、お盆のお墓参りをより快適かつ安全に行うことができます。
第11章:まとめ|お盆のお墓参りは心をつなぐ大切な時間

お盆のお墓参りは、単なる習慣ではなく、家族やご先祖様との心をつなぐ大切な時間です。
服装や持ち物、行ってはいけない日や作法といった基本を押さえることで、より丁寧で気持ちのこもったお参りができます。
近年では、代理墓参りサービスやオンライン供養、墓じまい・永代供養といった新しい選択肢も登場し、ライフスタイルや状況に合わせた供養が可能になりました。
お墓参りの形は変わっても、「感謝の心」を持ち続けることが何より大切です。
今年のお盆は、家族や親族と一緒にお墓参りに出かけて、故人との思い出を語り合ってみてはいかがでしょうか。
遠方や多忙で行けない場合でも、自宅で手を合わせたり、サービスを活用して供養の気持ちを伝えることができます。
よろしかったらシェアしてくださいね
ページ下部のシェアボタンを使えば、X(旧Twitter)やInstagramで簡単にシェアできます。
あなたの経験や思い出を投稿して、みんなと「お墓参り文化」をつなげていきましょう。
リンク






